з§ҒгҒҹгҒЎгҒ®иӮүдҪ“гҖҒгҒқгҒ—гҒҰеҝғгҒЁгҒҜгҖҒжң¬жқҘгҖҒдҪ•гҒ®гҒҹгӮҒгҒ«гҒӮгӮӢгҒ®гҒ гӮҚгҒҶгҒӢгҖӮ
еӢ•зү©зҡ„з”ҹеӯҳгҒ®зҠ¶ж…ӢгҒ«з«ӢгҒЎиҝ”гҒЈгҒҰиҖғгҒҲгҒҰгҒҝгӮӢгҒ«гҖҒгҒқгӮҢгҒҜз”ҹеӯҳгҒ®гҒҹгӮҒвҖ• з”ҹгҒҚ延гҒігӮӢгҒҹгӮҒгҒ®йҒ“е…·гҒЁгҒ—гҒҰгҒӮгҒЈгҒҹгҒ«йҒ•гҒ„гҒӘгҒ„гҖӮ
йЈІгҒҝж°ҙгҒ®е…ҘгҒЈгҒҹ瓶гӮ’й ӯгҒ«д№—гҒӣгҒҰй•·гҒ„и·қйӣўгӮ’жӯ©гҒҸгҖӮ
д»•з•ҷгӮҒгҒҹзҚІзү©гӮ’жӢ…гҒ„гҒ§еұ…дҪҸең°гҒҫгҒ§йҒӢгҒ¶гҖӮ
гҒқгҒ®йҡӣгҖҒзҚІзү©гӮ„ж°ҙгӮ’йҒӢгҒ¶гҒ“гҒЁгҒҢзӣ®зҡ„гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҒқгӮҢгӮ’йҒӢгӮ“гҒ§гҒ„гӮӢиӮүдҪ“гҒҜдё»йЎҢгҒ«гҒҜгҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҖӮ
гҒӮгӮӢгҒ„гҒҜгҖҒйҒ“гҒ«иҝ·гҒ„гҖҒжҮёе‘ҪгҒ«иҖғгҒҲгҒӘгҒҢгӮүгҖҒйҒ“гӮ’иҫҝгӮӢгҖӮ
гҒқгҒ®йҡӣгҒ«гӮӮгҖҒзӣ®зҡ„гҒЁгҒӘгӮӢгҒ®гҒҜгҖҒз„ЎдәӢгҖҒеұ…дҪҸең°гҒҫгҒ§гҒҹгҒ©гӮҠзқҖгҒҸгҒ“гҒЁгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒиҖғгҒҲгҒҰгҒ„гӮӢж„ҸиӯҳиҮӘдҪ“пјҲжҖқиҖғгҒҷгӮӢиғҪеҠӣгҒқгӮҢиҮӘдҪ“пјүгҒҢдё»йЎҢгҒЁгҒӘгӮӢгӮҸгҒ‘гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҖӮ
зҸҫд»ЈгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒиӮүдҪ“гҖҒгҒӮгӮӢгҒ„гҒҜж„ҸиӯҳгҒқгҒ®гӮӮгҒ®гҒҢдё»йЎҢгӮ„зӣ®зҡ„гҒЁгҒ•гӮҢгӮӢгҖӮ
гҒқгҒ®жңҖгҒҹгӮӢгӮӮгҒ®гҒЁгҒ—гҒҰгҖҒгғңгғҮгӮЈгғҜгғјгӮҜгӮ„зһ‘жғігҒҢгҒӮгӮӢгҖӮ
гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгҒқгӮӮгҒқгӮӮгҒ®еҮәзҷәзӮ№гҒЁгҒ—гҒҰгҖҒгҖҢиҮӘеҲҶгҒ®иә«еҝғгҒқгҒ®гӮӮгҒ®гҒҢдё»йЎҢгғ»зӣ®зҡ„гҒЁгҒӘгӮӢгҒ“гҒЁиҮӘдҪ“гҖҒжң¬жқҘгҖҒжҷ®йҖҡгҒ®гҒ“гҒЁгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҖҚгҒЁгҒ„гҒҶиӘҚиӯҳгӮ’гӮӮгҒЈгҒҰгҒҜгҒҳгӮҒгӮӢгҒ®гҒҜиүҜгҒ„гҒ“гҒЁгҒ гҒЁжҖқгҒҶгҖӮ
жҢҮеҗ‘жҖ§
з”ҹзү©гҒҜгҖҒз”ҹеӯҳгҒ®гҒҹгӮҒгҖҒеӨҡгҒҸгҒ®иЎҢзӮәпјҲиЎҢеӢ•пјүгӮ’гҒӘгҒҷгҖӮ
жҺўзҙўгҒ—гҖҒиЎЁзҸҫгҒ—гҖҒеҠҙеғҚгҒ—гҖҒжҚ•йЈҹгҒ—гҖҒгҒЁгҒҚгҒ«йҖғгҒ’йҡ гӮҢгҖҒжҲҰгҒҶгҖӮ
гҒқгӮҢгӮүе…·дҪ“зҡ„гҒӘзӣ®зҡ„пјҲеҜҫиұЎпјүгӮ’гӮӮгҒЈгҒҹиЎҢзӮәгҒ®йҡӣгҖҒз§ҒгҒҹгҒЎгҒ®иә«дҪ“гҒҜйҖҸжҳҺгҒ«гҒӘгӮҠгҖҒиЎҢзӮәгҒ®иғҢеҫҢгҒ«йҡ гӮҢгҒҹгҒӢгҒҹгҒЎгҒ§еғҚгҒҸгҖӮ
дҪ•гҒӢгҒ®еҜҫиұЎгӮ’пјҲиҰ–иҰҡгӮ’гӮӮгҒЈгҒҰпјүиҰіеҜҹгҒ—гӮҲгҒҶгҒЁгҒҷгӮӢгҖӮ
гҒқгҒ®гҒЁгҒҚгҖҒиҮӘиә«гҒ®з”ЁгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢиҰ–иҰҡж©ҹж§ӢиҮӘдҪ“вҖ• гҒҹгҒЁгҒҲгҒ°гҖҒзңјзҗғгҒ®ж§ӢйҖ гӮ„и„ігҒ®иЎҢгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢиҰ–иҰҡжғ…е ұеҮҰзҗҶвҖ• гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰиҖғгҒҲгӮӢеҝ…иҰҒгҒҜгҒӘгҒ„гҖӮ
гҒқгӮҢгӮүгҒҜз·ҸгҒҳгҒҰгҖҒйҖҸжҳҺеҢ–гҒ•гӮҢгҖҒз„ЎеҢ–гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰе……е…ЁгҒ«еғҚгҒҸгҖӮ
йҒӮиЎҢгҒҷгҒ№гҒҚиЎҢзӮәгҒ«еҗ‘гҒ‘гҖҒеӯҳеңЁе…ЁдҪ“гҒҢзөұдёҖгҒ•гӮҢгҖҒгҒҫгҒЁгҒҫгҒЈгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒгҒқгҒ®жҷӮгҖ…гҒ®еҜҫеҮҰгҒҷгҒ№гҒҚе…·дҪ“зҡ„еҜҫиұЎпјҲдәӢиұЎпјүгҒ®гҒҝгҒҢж„ҸиӯҳгҒ«гҒ®гҒјгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ
гҒқгӮҢгҒҜгҖҒеҝғиә«гҒҢжҢҮеҗ‘жҖ§гӮ’жҢҒгҒЈгҒҰеғҚгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢе§ҝгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
гғҸгӮөгғҹпјҲгҒӮгӮӢгҒ„гҒҜгғҠгӮӨгғ•пјүгӮ’дҪҝгҒЈгҒҰдҪ•гҒӢгӮ’еҠ е·ҘгҒҷгӮӢе ҙйқўгӮ’иҖғгҒҲгҒҰгҒҝгӮҲгҒҶгҖӮ
гҒқгҒ“гҒ«гҒҜгҖҒ
гғ»гғҸгӮөгғҹпјҲгғҠгӮӨгғ•пјүгӮ’жҸЎгӮӢиә«дҪ“
гғ»пјҲйҒ“е…·гҒЁгҒ—гҒҰгҒ®пјүгғҸгӮөгғҹгҖҒгғҠгӮӨгғ•
гғ»пјҲгҒқгҒ®йҒ“е…·гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰеҠ е·ҘгҒ•гӮҢгӮӢеҜҫиұЎгҒЁгҒ—гҒҰгҒ®пјүзҙ жқҗ
гҒ®дёүгҒӨгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮ
йҖҡеёёгҒ®пјҲгҒҶгҒҫгҒҸгҒ„гҒЈгҒҰгҒ„гӮӢпјүе ҙйқўгҒ§гҒҜгҖҒиӘҚиӯҳгҒ•гӮҢгӮӢгҒ№гҒҚгҒҜгҖҢеҜҫиұЎгҒЁгҒ—гҒҰгҒ®еҠ е·Ҙзү©гҖҚгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒиҮӘгӮүгҒ®иә«дҪ“гӮӮгҖҒгғҸгӮөгғҹгӮӮгҖҒгҒқгӮҢгӮ’жҸЎгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢжүӢгӮӮгҖҒж„Ҹиӯҳгғ»иӘҚиӯҳгҒ•гӮҢгӮӢеҝ…иҰҒгҒҜгҒӘгҒ„гҖӮ
пјҲгҒҹгҒЁгҒҲгҒ°пјүеҲҮгӮҠйҖІгӮҒгҒӨгҒӨгҒӮгӮӢзҙҷпјҲеҲҮгӮҠзөөпјүгҒ«е…ЁзҘһзөҢгӮ’йӣҶдёӯгҒ—зҙ°е·ҘгӮ’гҒҷгҒҷгӮҒгӮӢгҖӮ
гҒЁгҒ“гӮҚгҒҢгҖҒгҒӮгӮӢжҷӮзӮ№гҒ§гғҸгӮөгғҹгҒ®иӘҝеӯҗгҒҢжӮӘгҒ„гҒЁж„ҹгҒҳгӮӢгҖӮ
гҒқгҒ®зһ¬й–“гҖҒиӘҚиӯҳгҒ•гӮҢгӮӢеҜҫиұЎгҒҜпјҲеҠ е·ҘгҒҷгӮӢйҒ“е…·гҒ§гҒӮгӮӢпјүгғҸгӮөгғҹиҮӘдҪ“гҒ«з§»гӮӢгҖӮ
гҒқгӮҢгҒҢз„ҰзӮ№еҢ–гҒ•гӮҢгҖҒж„ҸиӯҳгҒ®дё»йЎҢгҖҒиӘҚиӯҳеҜҫиұЎгҒЁгҒӘгӮӢгҖӮ
гҒ—гҒ°гӮүгҒҸиҰіеҜҹгҒ—гҒҰгҒҝгҒҰгҖҒе•ҸйЎҢгҒҜгғҸгӮөгғҹиҮӘдҪ“гҒ«гҒӘгҒҸгҖҒгғҸгӮөгғҹгҒ®жҸЎгӮҠж–№иҮӘдҪ“гҒҢгҒҠгҒӢгҒ—гҒ„гҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢгҖҒгҒЁжҖқгҒ„иҮігӮӢгҖӮ
гҒҷгӮӢгҒЁж„ҸиӯҳгҒ®з„ҰзӮ№гҒҜгҖҒжүӢпјҲжҸЎгӮҠж–№пјүгҒқгҒ®гӮӮгҒ®гҒ«з§»гӮӢгҖӮ
гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒпјҲгӮӮгҒ—гҒӢгҒ—гҒҰпјүзңҹгҒ®еҺҹеӣ гҒҜгҖҒиҮӘеҲҶгҒ®еә§гӮҠж–№гҖҒе§ҝеӢўгҒқгҒ®гӮӮгҒ®гҒ«гҒӮгӮӢгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢвҖҰгҒЁжҺўзҙўгҒҜз¶ҡгҒҸгҖӮ
гҒқгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гҖҒе•ҸйЎҢи§ЈжұәгҒ®гҒҹгӮҒгҖҒж„ҸиӯҳгҒҜеҪ·еҫЁгҒ„гҖҒиӘҚиӯҳгҒ®з„ҰзӮ№гҒҜ移гӮҠгҖҒдё–з•ҢгҒҜе§ҝгӮ’еӨүгҒҲгҒҰж„ҸиӯҳгҒ«жҳ гҒҳгҒҰгӮҶгҒҸгҖӮ
вҖҰжңҖеҫҢгҒ«гҖҒйҒ•е’Ңж„ҹгҒ®еҺҹеӣ гҒҢеҲӨжҳҺгҒҷгӮӢгҖӮ
ж„ҸиӯҳгҒҜеҶҚгҒіеҲғе…ҲгҒ®ж„ҹиҰҡгҒ«жҲ»гӮҠгҖҒеҲҮгӮҠзҙҷзҙ°е·ҘгҒҜз¶ҡгҒ„гҒҰгҒ„гҒҸгҖӮ
з§ҒгҒҹгҒЎгҒҜж—ҘгҖ…гҖҒгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘиӘҚиӯҳгҒ®иҮӘеңЁгҒӘз„ҰзӮ№еҢ–гҒЁеүҚжҷҜгҒ®еҫ№еә•гҒ—гҒҹйҖҸжҳҺеҢ–гӮ’еҪ“гҒҹгӮҠеүҚгҒ«з”ҹгҒҚгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ
гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгҒӮгӮӢзү№е®ҡгҒ®е ҙйқўпјҲзҠ¶жіҒгғ»еҜҫиұЎпјүгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒгҒқгӮҢгҒҢж©ҹиғҪдёҚе…ЁгӮ’иө·гҒ“гҒҷгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮ
гҒқгӮҢгҒҢеёёж…ӢеҢ–гҒ—гҖҒй•·жңҹгҒ«жёЎгҒЈгҒҰеҸҚеҫ©гҒ•гӮҢгӮӢе ҙеҗҲгӮӮгҒӮгӮӢгҖӮ
з§ҒгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгғңгғҮгӮЈгғҜгғјгӮҜпјҲгҒӮгӮӢгҒ„гҒҜзһ‘жғіпјүгҒЁгҒҜгҖҒгҒқгҒ®дёҚе…·еҗҲгҒ«д»Ӣе…ҘгҒ—и§ЈжұәгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®жүӢж®өгҒ®дёҖгҒӨгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
гҒқгҒ“гҒ«гҒҜгҖҒгҒ“гҒ®е•ҸйЎҢгӮ’и§Јж¶ҲгҒ—гҖҒж©ҹиғҪгӮ’з ”гҒҺжҫ„гҒҫгҒ—зЈЁгҒҚгҒӮгҒ’гӮӢгҒҹгӮҒеҝ…иҰҒгҒӘзҹҘиҰӢгҒЁе…·дҪ“зҡ„ж–№жі•гҒҢиҙ…жҪӨгҒ«йӣҶз©ҚгҒ•гӮҢгҒҰгҒӮгӮӢгҖӮ
жӢЎејөжҖ§
гӮ«гғ©гғҖгӮ’гҒӨгҒӘгҒҗгҖҒгӮ«гғ©гғҖгҒ«гҒЁгҒҠгҒҷ
гҒӨгҒӘгҒҗпјҲз№ӢгҒҗгҖҒзөҶгҒҗпјүгҖӮ
гҒЁгҒҠгҒҷпјҲеҫ№гҒҷгҖҒйҖҸгҒҷпјүгҖӮ
з№ӢгҒ„гҒ§йҖҸгҒҷгҖҒеҫ№гҒ—гҒҰзөҶгҒҗгҖӮ
дҪ“е№№гҒЁжң«жўўгӮ’гҒӨгҒӘгҒҗгҖӮ
дёӢи…ҝгҒЁдёҠдҪ“гӮ’гҒӨгҒӘгҒҗгҖӮ
и¶іиЈҸгҒӢгӮүгҒӨгҒӘгҒҗгҖӮ
жҢҮе…ҲгҒӢгӮүгҒӨгҒӘгҒҗгҖӮ
иҮӘиә«дҪ“гҒ®гҖҒдҪ“иЎЁйқўгҒЁгҒ„гҒҶијӘйғӯз·ҡгғ»еўғз•Ңз·ҡгҒ®гҒӘгҒӢгҒ§гҒ®зөұеҗҲпјҲгҒІгҒЁгҒҫгҒЁгҒҫгӮҠгҒ«гҒӘгӮӢпјү
гғңгғҮгӮЈгғҜгғјгӮҜзҡ„гҒӘж¬Ўе…ғ
гғўгғҺпјҲйҒ“е…·пјүгҒЁгҒӨгҒӘгҒҗ
жҺҢгҒЁгҒ„гҒҶгӮўгӮҝгғғгғҒгғЎгғігғҲгӮ’йҖҡгҒ—гҒҰгҒ®йҒ“е…·е…Ҳз«ҜгҒҫгҒ§гҒ®иә«дҪ“/ж„ҸиӯҳгҒ®жӢЎејөгҖҒиә«дҪ“гҒёгҒ®еҸ–гӮҠиҫјгҒҝгҖҒе‘‘гҒҝиҫјгҒҝгҖӮйҒ“е…·гҒЁгҒ®иһҚеҗҲгғ»зөұеҗҲ
гғ’гғҲгҒЁгҒ„гҒҶз”ҹзү©зЁ®гҒ«йЎ•и‘—гҒӘзү№жҖ§гҖҒгҒқгӮҢгӮ’зЈЁгҒҸдҪңжҘӯгҖӮ
гғ’гғҲгҒҜгҖҒжҺҢгҒЁдә‘гҒҶжҺҘз¶ҡеҷЁе®ҳгӮ’дҪҝгҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒж§ҳгҖ…гҒӘйҒ“е…·гӮ’иҮӘеҲҶгҒ®иә«дҪ“(ж„ҸиӯҳгҖҒгӮӨгғЎгғјгӮёпјүгҒ«еҸ–гӮҠиҫјгӮ“гҒ§дҪҝгҒҶгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҖӮиә«дҪ“гҒ®жӢЎејөгҒҢиЎҢгҒҲгӮӢгҖӮпјҲжқ–гҒ®гҒҹгҒЁгҒҲпјү
гҖҢжҢҒгҒӨгӮӮгҒ®(йҒ“е…·)гӮ’еӨүгҒҲгӮӢгҒҹгҒігҒ«гҖҒиҮӘеҲҶгҒ®иә«дҪ“гҒқгҒ®гӮӮгҒ®гӮ’гӮ°гғӢгғ§гӮ°гғӢгғ§гҒЁеӨүеҪўгҒ•гҒӣгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҖӮ
йҒ“е…·гӮ’жҢҒгҒЈгҒҰгҒ®зЁҪеҸӨгҒЁгҒҜгҖҒгҒқгӮҢгӮ’гҒ„гҒӢгҒ«иә«дҪ“гҒ«еҸ–гӮҠиҫјгӮ“гҒ§дҪҝгҒҲгӮӢгҒӢгҖҒгҒ®гҖҢиә«дҪ“гҒ®жӢЎејөгҖҚгҒ®е…·дҪ“зҡ„иЁ“з·ҙгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
гҒқгҒ®гҒҶгҒҲгҒ§гҖҒйҖҶгҒ«иҮӘеҲҶгҒ®иә«дҪ“пјҲжң«з«ҜйғЁеҲҶпјүгӮ’гҖҒеӨ–зҡ„йҒ“е…·гҒЁгҒ—гҒҰдҪҝгҒҶгҖҒгҒЁгҒ„гҒҶеұ•й–ӢгӮӮгҒӮгӮӢгҖӮ
иҮӘиә«гҒ®дҪ“иЎЁйқўгҖҒеә§йқўгҖҒеҜҫиұЎгҒЁгҒ®жҺҘи§ҰйқўгӮ’йҖҡгҒ—гҒҰгҒ®иһҚеҗҲпјҲгҒҹгҒЁгҒҲгҒ°гҖҒйҰ¬гҖҒгғҗгӮӨгӮҜгҖҒиҮӘеӢ•и»ҠгҒӘгҒ©пјүгӮӮеҸҜиғҪгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
иә«дҪ“и«–пјҲйҒ“е…·и«–пјүзҡ„гҒӘж¬Ўе…ғ
д»–иҖ…гҒЁгҒӨгҒӘгҒҗ
д»–иҖ…гҒ®иә«дҪ“гҒЁгҒӨгҒӘгҒҗпјҲд»–иҖ…гҒёгҒЁгҒҠгҒҷпјүгҖҒд»–иҖ…гҒ«еғҚгҒҚгҒӢгҒ‘гӮӢгҖҒзү©зҗҶзҡ„гҒ«ж”Ҝй…ҚгҒҷгӮӢгҖӮ
иә«дҪ“зҡ„жҺҘи§ҰгҒӮгӮҠгҒӢгӮүжҺҘи§Ұз„ЎгҒ—гҒёгҖӮ
дё»гҒ«гҖҒиә«дҪ“зҡ„жҺҘи§ҰгӮ’йҖҡгҒ—гҒҰгҒ®д»–иҖ…гҒЁгҒ®зөұеҗҲпјҲгҒІгҒЁгҒҫгҒЁгҒҫгӮҠгҒ«гҒӘгӮӢпјү
жӯҰиЎ“зҡ„гғ»зӨҫдјҡй–ўдҝӮи«–зҡ„гҒӘж¬Ўе…ғ
еӨ–з•ҢпјҲдё–з•ҢпјүгҒЁгҒӨгҒӘгҒҗ
дә”ж„ҹгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰзҹҘиҰҡгҒ•гӮҢгҒҰгӮӢеӨ–зҡ„иӘҚиӯҳеҜҫиұЎгҒЁгҒ®гҒӨгҒӘгҒҺгҖӮ
гӮӨгғЎгғјгӮёгӮ’д»ӢеңЁгҒ•гҒӣгҒҰгҒ®гҖҢдё–з•ҢгҖҚгҒЁгҒ®гҒӨгҒӘгҒҺгҖӮ
ж„ҸиӯҳгҒ®ж”ҫгҒЎгҒЁгҖҒдё–з•ҢгҒЁгҒ®гӮҖгҒҷгҒігҖӮ
ж„ҸиӯҳгҒ®жӢЎејөгҒЁгҒ„гҒҶгҒӢгҒҹгҒЎгҒ§гҒ®еӨ–зҡ„дё–з•ҢгҒЁгҒ®иһҚеҗҲгғ»зөұеҗҲпјҲжӢЎж•ЈгҒЁйЈІгҒҝиҫјгҒҝгҖҒгҒІгҒЁгҒӨгҒ«гҒӘгӮӢпјү
й–Ӣж”ҫжҖ§гҒ®ж„ҸиӯҳпјҲдё–з•ҢиӘҚиӯҳпјүгҖҒж„ҸеҝөгҖҒгӮӨгғЎгғјгӮёеҠӣгҖӮ
зһ‘жғізҡ„пјҲд»Ҹж•ҷзҡ„пјүгҒӘж¬Ўе…ғ
гҒ“гҒ®гғ—гғӯгӮ»гӮ№гҒҜгҖҒгҖҢиҮӘе·ұгҒ®еўғз•Ңз·ҡгҒ®жјёйҖІзҡ„жӢЎејөгҖҚгҒЁдә‘гҒҶж„Ҹе‘ігҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҒҜж®өйҡҺзҡ„гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
гҒқгӮҢгҒҜгҖҒеүҚжҷҜгҒЁгҒӘгӮӢеӣһи·ҜгҒ®йҖҸжҳҺеҢ–пјҲж„ҸиӯҳгҒ®й–ӢгҒ‘еҫ№гҒ—пјүгҒЁгҖҒе…Ҳз«ҜгҒ§иӘҚиӯҳеҜҫиұЎгҒЁгҒӘгӮӢдәӢиұЎгҒЁгҒ®зӣҙжҺҘжҺҘи§Ұж„ҹгӮ’дјҙгҒҶгҖҒйҖЈз¶ҡзҡ„гҒ§еҗҢиіӘгҒ®дҪ“йЁ“гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒе®ҹи·өзҡ„гҒӘйӣЈжҳ“еәҰгҒҢж®өйҡҺзҡ„гҒ«дёҠгҒҢгӮӢгӮҸгҒ‘гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҖӮ
гҒқгӮҢгҒҜгҖҒпјҲйҡҺеұӨгғ»йҡҺж®өгҒЁиЁҖгҒҶгӮҲгӮҠгӮӮпјүгӮ«гғЎгғ©гҒ®гӮәгғјгғ гӮӨгғігғ»гӮўгӮҰгғҲгҒ®ж“ҚдҪңгҒ«дјјгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒгҒқгҒ“гҒ«зӣҙз·ҡзҡ„гғ»е№ійқўзҡ„гҒӘж„Ҹе‘ігҒ§ж®өйҡҺгҒЁиЁҖгҒҲгӮӢгӮӮгҒ®гҒҜгҒӘгҒ„гҖӮ
гҒ“гҒ®еҝғиә«гҒҢжҢҒгҒӨжӢЎејөжҖ§гӮ’гҖҒгҖҢзөұеҗҲзҡ„гҖҚгҒЁгҒ„гҒҶиЁҖи‘үгҒ§гӮӮгҒЈгҒҰиЎЁгҒҷгҒ“гҒЁгӮӮгҒ§гҒҚгӮӢгҖӮ
гҖҢзөұеҗҲзҡ„гҖҚгҒЁдә‘гҒҶиЁҖи‘үгҒ«гӮӮгҖҒе№ҫгҒӨгӮӮгҒ®ж¬Ўе…ғгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮ
иә«дҪ“зөұеҗҲпјҲиә«дҪ“гҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢзөұеҗҲпјү
иә«дҪ“гҒ®дёӯпјҲиә«гҒ®гҒҶгҒЎпјүгҒ§гҒ®ж–ӯзүҮгҒ®зөұеҗҲгҖӮ
иә«дҪ“гҒ®йғЁеҲҶгҒЁйғЁеҲҶгҒ®дёҚиӘҝе’ҢгҒ®и§Јж¶ҲгҖӮиә«дҪ“гҒ®еҗ„йғЁеҲҶгҒ®зөұеҗҲгҖӮиә«дҪ“е…ЁдҪ“гҒЁгҒ—гҒҰгҒ®зөұеҗҲгҖӮ
еҝғиә«зөұеҗҲпјҲеҝғиә«гҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢзөұеҗҲпјү
иә«гҒЁеҝғгҒЁгҒ®ж–ӯзүҮеҢ–гғ»еҲҶйӣўгҒ®зөұеҗҲгҖӮ
иә«дҪ“гҒЁж„ҸиӯҳпјҲиә«гҒЁеҝғгҖҒгӮ«гғ©гғҖгҒЁгӮігӮігғӯпјүгҒ®гғҒгӮ°гғҸгӮ°гҒ•гғ»дёҚиӘҝе’ҢгҒ®и§Јж¶ҲгҖҒж„ҸиӯҳгҒЁиә«дҪ“гҒ®зөұеҗҲгҖӮ
еӯҳеңЁзөұеҗҲпјҲеӯҳеңЁгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢзөұеҗҲпјү
иҮӘе·ұгҖҒеӨ–з•ҢгҖҒд»–иҖ…пјҲзӨҫдјҡз©әй–“пјүгҖҒгҒқгӮҢгӮүгҒҷгҒ№гҒҰгӮ’еҗ«гӮ“гҒ зөұеҗҲгҖӮ
йҖҡиә«гҒ«иЎҢгҒҚжёЎгӮӢж°—гҒҘгҒҚгҖҒе…Ёиә«гҒ®еҚ”иӘҝгҒ—гҒҹеӢ•гҒҚгҖҒгҒӘгҒ©гҖӮ
гҒ“гӮҢгӮүгҒҜеҲҘзЁ®гҒ®гӮӮгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒз·©гӮ„гҒӢгҒ«йҖЈз¶ҡгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ
* еҸӮиҖғеӣіжӣё
гҖҺз„Ўеўғз•Ң иҮӘе·ұжҲҗй•·гҒ®гӮ»гғ©гғ”гғји«–гҖҸгҖҖгӮұгғігғ»гӮҰгӮЈгғ«гғҗгғји‘—
е…ЁдҪ“жҖ§
гҒ“гҒ®е®ҹи·өгӮ’йҖҡгҒ—гҒҰзӣ®жҢҮгҒ•гӮҢгӮӢгҒ®гҒҜгҖҒгҖҢгҒӮгӮӢпјҲеҗҚгҒҘгҒ‘йӣЈгҒ„пјүдёҖгҒӨгҒ®зҠ¶ж…ӢгҖҚгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
гҒқгҒ“гҒ§гҒҜгҖҒиә«дҪ“/ж„ҸиӯҳгҒҜжёҫ然дёҖдҪ“гҒЁгҒӘгӮҠгҖҒж·ұгҒҸзөҗгҒ°гӮҢгҒҰеңЁгӮӢгҖӮ
гҒқгӮҢгҒҜпјҲд»ҘдёӢгҒ«иҝ°гҒ№гӮӢпјүеӨҡгҒҸгҒ®еҜҫз«Ӣй …гҒЁгҖҒгҒқгӮҢгӮүгҒ®ејҒиЁјжі•зҡ„гҒӘзөұеҗҲгӮ’еӯ•гӮ“гҒ§гҒҠгӮҠгҖҒ
гҒқгӮҢгӮүгҒҢзӣёдә’гҒ«жү“гҒЎж¶ҲгҒ—еЈҠгҒ—еҗҲгҒҶгҒ“гҒЁгҒҢгҒӘгҒ„гҒҫгҒҫеҗҢжҷӮжҲҗз«ӢгҒҷгӮӢдәӢж…ӢгҒҢжҲҗз«ӢгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ
йҮҚгҒ•гҒЁи»ҪгҒ•пјҲжө®гҒҚгҒЁжІҲгҒҝпјү
гғ„гғӘгғјгғһгғігғўгғҮгғ«гҒЁгғҒгғјгӮҝгғјгғўгғҮгғ«
еҸҚгӮҠпјҲеүҚеӮҫпјүгҒЁдёёгӮҒпјҲеҫҢеӮҫпјү
и…°гҒЁи…№пјҲи…°и…№еҗҢйҮҸпјү
дјёй•·жҖ§пјҲй–Ӣж”ҫжҖ§пјүгҒЁең§зё®жҖ§пјҲжұӮеҝғжҖ§пјү
еј•ејөеҠӣпјҲеҮқзё®пјүгҒЁж”ҫж•ЈеҠӣпјҲй–Ӣж”ҫгҖҒж”ҫгҒӨж–№еҗ‘жҖ§пјү
еӢ•гҒЁдёҚеӢ•пјҲгғўгғ“гғӘгғҶгӮЈпјқеҸҜеӢ•жҖ§гҒЁгӮ№гӮҝгғ“гғӘгғҶгӮЈпјқе®үе®ҡжҖ§пјү
дҪ“е№№гҒЁжң«жўў
еҶ…гҒЁеӨ–пјҲеҶ…еӨ–еҗҲдёҖпјү
еһӮзӣҙгҒЁж°ҙе№іпјҲйүӣзӣҙгҒЁжЁӘж–ӯгҖҒжӯЈдёӯйқўгҒЁеҒҙдёӯйқўгҖҒз«ӢеҶҶгҒЁжЁӘеҶҶпјү
е……е®ҹж„ҹгҒЁж„ҹиҰҡгҒ®з„ЎгҒ•
еҲҶеҢ–гҒЁзөұеҗҲпјҲеҖӢеҲҘйғЁеҲҶгҒ®еҸҜеӢ•жҖ§гҒЁе…ЁдҪ“гҒ®йҒӢеӢ•йҖЈйҺ–пјү
зІҫзҘһпјҲж„ҸиӯҳпјүгҒЁиӮүдҪ“пјҲиә«дҪ“йҒӢеӢ•пјү
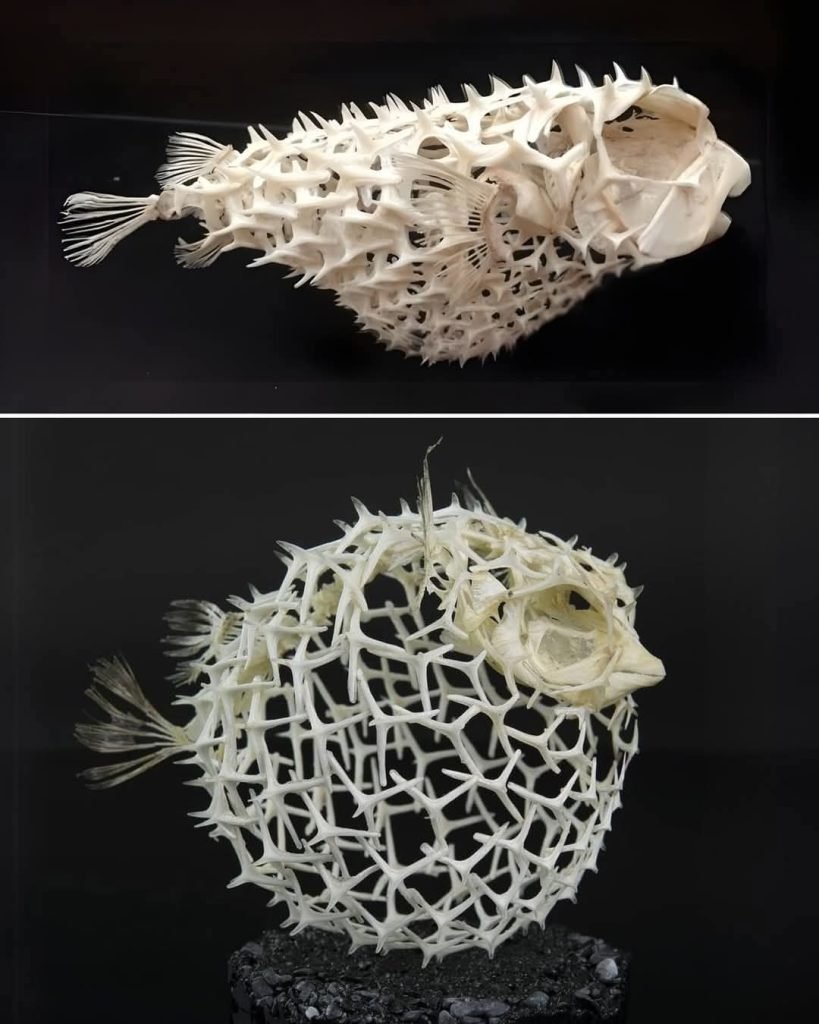
з”»еғҸгҒ®гғҸгғӘгӮ»гғігғңгғігҒ«е–©гҒҲгӮҢгҒ°гҖҒеҗ‘гҒӢгҒ„еҗҲгҒ„еҜҫз«ӢгҒҷгӮӢдәҢгҒӨгҒ®гғҲгӮІгҒҢжӢ®жҠ—гҒ—еҸҚзҷәгҒ—гҒҰдёҖгҒӨгҒ®гӮ»гғғгғҲгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҖӮ
гҒқгҒ®гӮ»гғғгғҲгҒҢгҖҒгҒҫгҒҹеҲҘгҒ®гӮ»гғғгғҲгҒЁжӢ®жҠ—гҒ—гҖҒгҒқгҒ“гҒ«еӨ–еҗ‘гҒҚгҒ®жӢЎејөжҖ§гҒ®ж§ӢйҖ гҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҖӮ
гҒқгҒ®гғҗгғҚпјҲж’“гҒҝпјүгӮ’еҶ…еңЁгҒ—гҒҹгғҶгғігӮ»гӮ°гғӘгӮЈгғҶгӮЈж§ӢйҖ гҖҒгҖҢејөгӮҠгҖҚгҒ®еј·еәҰгҒЁеӨ§гҒҚгҒ•пјҲж§ӢйҖ дҪ“гҒ®иҰҸжЁЎгҖҒгӮ№гӮұгғјгғ«пјүгҒҢйҢ¬еҠҹгҒ®зҝ’зҶҹеәҰеҗҲгҒ„гҒ®жҢҮжЁҷгҒЁгҒӘгӮӢгҖҒгҒЁгҒ„гҒҶгӮӨгғЎгғјгӮёгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
е®ҹйҡӣгҒ®иЁ“з·ҙгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒгҒқгӮҢгӮүгӮ’дёҖжҢҷгҒ«жҲҗз«ӢгҒ•гҒӣгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҖҒеҺҹзҗҶзҡ„гҒ«еҸ¶гӮҸгҒӘгҒ„гҖӮ
ж•…гҒ«гҖҒеҖӢгҖ…дәәгҒ®жҢҒгҒӨе…·дҪ“зҡ„иӘІйЎҢгғ»ж®өйҡҺгҒ«еҝңгҒҳгҒҰгҖҒгҒӮгӮӢиҰҒзҙ гӮ’еүҚжҷҜгҒ«еј•гҒҚеҮәгҒ—гҖҒпјҲе…ЁдҪ“жҖ§гӮ’еӨұгҒ„еҒҸгӮҠгӮ’з”ҹгӮҖгҖҒгҒЁгҒ„гҒҶиӘ№гӮҠгӮ’иҰҡжӮҹгҒ®гҒҶгҒҲгҒ§пјүгҖҢйҢ¬еҠҹгҖҚгҒЁе‘јгҒ°гӮҢгӮӢе…·дҪ“зҡ„иЁ“з·ҙгҒ«зөҗе®ҹгҒ•гҒӣгҖҒе®ҹи·өиҖ…гҒ®еүҚгҒ«жҸҗеҮәгҒ•гӮҢгӮӢгҖӮпјҲйҖҶгҒ«гӮӮиЁҖгҒЈгҒҰгҒҠгҒ“гҒҶгҖӮгҒҷгҒ№гҒҰгҒ®е…·дҪ“еҢ–гҒ•гӮҢгҒҹйҢ¬еҠҹгҒҜгҖҒеёёгҒ«еҝ…гҒҡгҖҒеҒҸгӮҠгғ»гғһгӮӨгғҠгӮ№гҒ®йғЁеҲҶгҖҒгҒӨгҒҫгӮҠзӣІзӮ№гӮ’еӯ•гӮ“гҒ§гҒ„гӮӢгҖӮгҒқгӮҢгҒҜгҖҒгҒқгҒ®жң¬иіӘдёҠгҖҒе…ҚгӮҢгҒҲгҒӘгҒ„йҷҗз•ҢгҒ§гҒӮгӮӢпјү
гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгҒқгӮҢгӮүгҒҜеёёгҒ«гҖҒе”ҜдёҖзӣ®жҢҮгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖҢгҒӮгӮӢзҠ¶ж…ӢгҖҚгӮ’е®ҹзҸҫгҒ•гҒӣгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®ж–№дҫҝгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒе…ЁдҪ“жҖ§гӮ’гҖҒпјҲзҸҫеңЁгҒ®еҝ…иҰҒгҒ«еҝңгҒҳгҒҰпјүйҷҗе®ҡгҒ•гӮҢгҒҹз«Ӣе ҙгҒӢгӮүеҲҮгӮҠеҸ–гӮҠгғ»еҲҮгӮҠеҮәгҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҒ«йҒҺгҒҺгҒӘгҒ„гҖӮ
жңҖзөӮзҡ„гҒ«гҖҒгҒҷгҒ№гҒҰгҒҜе…ЁдҪ“жҖ§гҒ®гҒӘгҒӢгҒ«еҶҚгҒіжә¶гҒ‘еҺ»гӮҠгҖҒеӣһеҸҺгҒ•гӮҢгӮӢгҒ№гҒҚгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮҚгҒҶгҖӮ
йҒЎиЎҢгҒЁжөҒеҮә
гҒқгҒ“гҒ«гҒҜгҖҒжң¬жәҗпјҲж №жәҗпјүпјқеҺҹзҗҶжҖ§гҒёеҗ‘гҒӢгҒҠгҒҶгҒЁгҒҷгӮӢеј·гҒ„ж„ҸжҖқгҒҢеӯҳеңЁгҒҷгӮӢгҖӮ
еӨҡгҒҸгҒ®е…·дҪ“зҡ„жҠҖиЎ“гҒҢз”ҹгҒҝеҮәгҒ•гӮҢгӮӢжң¬жәҗпјҲжәҗй ӯпјүгҒёгҒЁйҒЎиЎҢгҒ—гҖҒе§ӢеҺҹгҒёиҫҝгӮҚгҒҶгҒЁгҒҷгӮӢж–№еҗ‘жҖ§гҒҢгҖӮ
еӨҡгҒҸгҒ®еҜҫжҘөгҒҷгӮӢиҰҒзҙ гӮ’еҗ«гӮ“гҒ гҒҢж•…гҒ«гҖҒиЁҖиӘһеҢ–гҒ—иӘ¬жҳҺгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеҸ¶гӮҸгҒӘгҒ„гҖҒгҖҢгҒӮгӮӢдёҖгҒӨгҒ®иә«еҝғгҒ®пјҲйҒӢеӢ•пјүзҠ¶ж…Ӣгғ»гҒӮгӮҠгҒ•гҒҫгҖҚгҒҢжңүгӮӢгҖӮ
гҒқгҒ“гҒ«иҮігӮӢгҒҹгӮҒгҖҒгҒқгӮҢгӮ’иӘ¬жҳҺгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®ж–№дҫҝпјҲгғ’гғігғҲгҒ®гҒІгҒЁгҒӨпјүгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒеӨҡж§ҳгҒ§еӨҡеҪ©гҒӘе…ҘеҸЈгҖҒе…·дҪ“еҢ–гҒ—гҒҹйҢ¬еҠҹжі•гҒҢпјҲж–ӯзүҮгҒЁгҒ—гҒҰпјүеүөеҮәгҒ•гӮҢгӮӢгҖӮ
гҒҢгҖҒгҒқгӮҢгӮүгҒҜеёёгҒ«гҖҒгҒӮгӮӢгҒІгҒЁгҒӨгҒ®е…ЁдҪ“гӮ’жҢҮгҒ—зӨәгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ
гҒқгҒ®е…ЁгҒҰгҒҢгҖҒгҒӮгӮӢдёҖгҒӨгҒ®дёӯеҝғзӮ№гҖҒгҒӮгӮӢжӣ°гҒҸиЁҖгҒ„йӣЈгҒ„дёҖзӮ№гӮ’еҝ—еҗ‘гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ
еӨӘйҷҪпјҲеӨ•ж—ҘпјүгҒҢгҖҒгҒқгӮҢгҒһгӮҢгҒ®е ҙжүҖгҒӢгӮүгҖҒгҒқгӮҢгҒһгӮҢгҒ®дё»дҪ“гҒҢзңәгӮҒгҒҰгӮӮгҖҒеёёгҒ«гҖҒеҗ„дәәгҒ®зңҹжӯЈйқўгҒ«гҖҒиә«дҪ“гҒ®дёӯеҝғгҒ«гҖҒеҸҺж–ӮгҒ—гҒҰиҰӢгҒҲгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҖӮ
е…ЁгҒҰгҒ®пјҲеӨҡж§ҳгҒӘпјүйҢ¬еҠҹжі•гҒҜгҒҷгҒ№гҒҰгҖҒдёҖгҒӘгӮӢе…ЁдҪ“гҒӢгӮүгҒ®еҲҶеҢ–гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
гҒҹгҒ гҒ—гҖҒгҖҢеӨҡгҖҚгӮӮеҝ…иҰҒгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
гҖҢеӨҡгҖҚгӮ’еӨұгҒ„гҖҒгҖҢдёҖгҖҚгҒ®гҒҝгҒ—гҒӢж®ӢгҒЈгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„дҪ“зі»гҒҜгҖҒгҒқгҒ®е®ҹз”ЁжҖ§пјҲе…·дҪ“жҖ§пјүгӮ’еӨұгҒҶгҖӮ
еҶ…е®№гҒ®еҘҘж·ұгҒ•гҒЁгҖҒе…·дҪ“зҡ„гҒӘж–№жі•и«–гҒ®еӨҡж§ҳгҒ•гҖҒеј•гҒҚеҮәгҒ—гҒ®еӨҡгҒ•гҖҒеҸ–гҒЈжҺӣгҒӢгӮҠгҒ®еӨҡгҒ•гҒ®дёЎз«ӢгҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
жұӮгӮҒгӮүгӮҢгӮӢгҒ№гҒҚгҒҜгҖҒеҸҜиғҪгҒӘйҷҗгӮҠгҒ®гҖҢж·ұгҒ•гҖҚгҒЁгҖҢеҲҶгҒӢгӮҠгӮ„гҒҷгҒ•гғ»е…ҘгӮҠгӮ„гҒҷгҒ•гҖҚгҒ®дёЎз«ӢгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҖҢдёҖ/еӨҡгҖҚгҒЁгҒ®жӢ®жҠ—гғ»зҹӣзӣҫзҡ„зөұдёҖгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
гҒқгӮҢгҒҜеҗҢжҷӮгҒ«гҖҒгҒӮгӮүгӮҶгӮӢиә«дҪ“жҠҖиғҪгҖҒиә«дҪ“дҪңжі•гҒ«пјҲйҒ©з”ЁзҜ„еӣІгҒҢйҷҗгӮүгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁз„ЎгҒҸпјүй–ӢгҒӢгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гӮӮгҒӮгӮӢгҖӮ
гҒқгҒ“гҒҜгҖҒзһ‘жғігҖҒгғңгғҮгӮЈгғҜгғјгӮҜгҖҒеҶ…иҰігҖҒжӯҰиЎ“гҖҒиёҠгӮҠгҖҒжІ»зҷӮгҖҒгғ’гғјгғӘгғігӮ°гҖҒ科еӯҰгҖҒе“ІеӯҰгҒӘгҒ©гҖҒгҒҷгҒ№гҒҰгҒҢжңӘеҲҶеҢ–гҒӘе§ӢеҺҹзӮ№гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҒӮгӮүгӮҶгӮӢжҠҖжі•гҖҒжҠҖиЎ“гҖҒеһӢгҖҒеӢ•гҒҚгҖҒжҙһеҜҹгҒҢгҖҒгҒқгҒ“гҒӢгӮүз”ЈгҒҝеҮәгҒ•гӮҢз¶ҡгҒ‘гӮӢеӯҳеңЁгҒ®зҠ¶ж…Ӣпјқж„ҸиӯҳгҒ®ж¬Ўе…ғгҒ§гӮӮгҒӮгӮӢгҖӮ
жІўеұұгҒӮгӮӢжІігҒ®ж”ҜжөҒгҒ«гҒ„гӮӢгҒЁгҖҒгҒқгӮҢгҒһгӮҢгҒ®йўЁжҷҜгҒҜйҒ•гҒ„гҖҒеҲҘгҒ®е ҙжүҖгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«ж„ҹгҒҳгӮүгӮҢгӮӢгҖӮ
гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгҒқгӮҢгӮүдёҖгҒӨдёҖгҒӨгӮ’жәҗжөҒгҒҫгҒ§йҒЎиЎҢгҒ—дёҒеҜ§гҒ«иҫҝгӮӢгҒӘгӮүгҖҒгҒҷгҒ№гҒҰгҒҢжөҒгӮҢеҮәгҒҰгҒҸгӮӢжәҗгҖҒгҒқгӮҢгӮүгҒҢжңӘгҒ еҲҶгҒӢгӮҢгҒӘгҒ„е§ӢеҺҹзӮ№гҒ«иҮігӮӢвҖ• гҒқгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘж„ҹиҰҡгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
гҒқгӮҢгҒҜ科еӯҰгҒЁиҠёиЎ“гӮ’гҒӨгҒӘгҒҗгӮӮгҒ®вҖ• гҖҢеҶ…зңҒгғ»еҶ…иҰіиӘҚзҹҘ科еӯҰпјҲ脳科еӯҰпјүгҖҚгҒЁгҒ—гҒҰгҒ®гҖҢеҝғгҒ®з§‘еӯҰгҖҚгҒ®иҰіеҜҹгғ»е®ҹйЁ“гғ»иҮЁеәҠгҒ®зҸҫе ҙгҒ§гҒӮгӮҠгҒӨгҒӨгӮӮгҖҒеҗҢжҷӮгҒ«гҖҒеҚіиҲҲгҒ®йҹіжҘҪгҖҒиҲһиёҸгҖҒзөөз”»гҖҒи©©гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒжІ»зҷӮгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒжҮәжӮ”гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒзҘһгҒёгҒ®еҘүзҙҚзү©гҒ§гҒӮгӮӢгӮҲгҒҶгҒӘдҪ•гҒӢвҖ•
иҮӘе·ұгҒ®еҝғиә«гҒ«еӮ¬гҒ•гӮҢгӮӢгҒӮгӮүгӮҶгӮӢеҮәжқҘдәӢгӮ’зһ¬й–“жҜҺгҒ«иҠұй–ӢгҒӢгҒӣгҖҒи§Јж¶ҲгҒ•гҒӣгҒҰгӮҶгҒҸгҖҒйҖ”ж–№гӮӮгҒӘгҒҸз№Ҡзҙ°гҒӘжҠҖиЎ“пјҲгӮөгӮӨгӮігғҶгӮҜгғҺгғӯгӮёгғјпјүгҒ§гҒӮгӮӢгҒЁеҗҢжҷӮгҒ«гҖҒзһ¬й–“зһ¬й–“жӣҙж–°гҒ•гӮҢгӮӢгҖҒз§ҒгҒ®иә«еҝғгғ»зҹҘиҰҡгғ»жҖқиҖғгғ»ж„ҹжғ…гӮ’жқҗж–ҷгҒЁгҒ—гҒҰж§ӢзҜүгҒ•гӮҢгӮӢгҖҒж°—гҒҘгҒҚгҒ«гӮҲгӮӢеӯҳеңЁгҒ®иҠёиЎ“гҒ§гҒӮгӮӢгӮҲгҒҶгҒӘдҪ•гҒӢгҖҒгҒӘгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ

