й•·гҒ„гҒ“гҒЁгҖҒеІёгӮ’иҰӢеӨұгҒҶеӢҮж°—гҒӘгҒ—гҒ«гҖҒж–°гҒ—гҒ„еӨ§йҷёгӮ’зҷәиҰӢгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒӘгҒ©гҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҖӮ
гҒ“гҒ®з« гҒ§гҒҜгҖҒзҰ…пјҲж—Ҙжң¬еӨ§д№—д»Ҹж•ҷгғ»зҰ…е®—пјүгҖҒгғҙгӮЈгғ‘гғғгӮөгғҠгғјпјҲдёҠеә§д»Ҹж•ҷпјүгҖҒеҶ…иҰіпјҲж—Ҙжң¬еӨ§д№—д»Ҹж•ҷгғ»жө„еңҹе®—пјүгҒ®еҝғиӯҳи«–пјҲж„ҸиӯҳгҒ®зҗҶи«–пјүгӮ’дё»йЎҢгҒЁгҒҷгӮӢгҖӮ
гҒқгҒ®йҡӣгҖҒзҰ…гӮ’гҖҢиһҚеҗҲгғўгғҮгғ«гҖҚгҒ®е®—ж•ҷвҖ• йҒ“ж•ҷгҒӢгӮүгӮўгғүгғҙгӮЎгӮӨгӮҝгҒҫгҒ§гҖҒдё–з•ҢгҒ«ж•ЈеңЁгҒҷгӮӢдё»е®ўгҒ®еҲҶйӣў-иһҚеҗҲгӮ’еҹәжң¬и»ёгҒЁгҒҷгӮӢзҘһз§ҳдё»зҫ©зҡ„ж•ҷгҒҲвҖ• гҒ®зІҫиҸҜгҒ®гҒІгҒЁгҒӨгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒ
еҶ…иҰігӮ’гҖҒпјҲгӮӯгғӘгӮ№гғҲж•ҷгҒӘгҒ©дёҖзҘһж•ҷгҒ®дјқзөұгӮ’гӮӮеҗ«гӮҒгҒҹпјүзө¶еҜҫиҖ…пјҲзҘһд»ҸпјүгҒ«гӮҲгӮӢж•‘жёҲгӮ’иӘ¬гҒҸгҖҒиҮӘеҠӣпјҲжӮҹгӮҠпјүгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢд»–еҠӣпјҲж•‘гҒ„пјүгҒ®ж•ҷгҒҲгҒ®жқұжҙӢзҡ„гҒӘе®ҢжҲҗж…ӢпјҲеҲ°йҒ”зӮ№пјүгҒ®гҒІгҒЁгҒӨгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒжүұгҒҶгҖӮ
гғҙгӮЈгғ‘гғғгӮөгғҠгғјгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒдёҠиЁҳгҖҒдәҢиҖ…гҒЁгҒҜйҒ•гҒ„гҖҒдё–з•ҢгҒ«пјҲжҷ®йҒҚзҡ„гҒ«пјүиҮӘ然зҷәз”ҹзҡ„гҒ«еӯҳеңЁгҒҷгӮӢгҖҢиһҚеҗҲгғўгғҮгғ«гҖҚгҒ®е®—ж•ҷгҒЁгҒҜз•°гҒӘгҒЈгҒҹгҖҢзү№з•°дҫӢгҖҚгҒ§гҒӮгӮӢгҒЁгҒ®иӘҚиӯҳгҒ®гӮӮгҒЁгҖҒгҒқгҒ®е®ҹи·өзҗҶи«–/жҠҖжі•гҒ®и§ЈжһҗгӮ’йҖІгӮҒгӮӢгҖӮ
гҒ“гӮҢгҒҜгҖҒгҒқгӮҢгӮүдёүиҖ…гӮ’йҖҡгҒ—гҒҰгҖҢе®—ж•ҷе…ЁдҪ“гҖҚгӮ’иҰӢжҚ®гҒҲгӮҲгҒҶгҒЁгҒҷгӮӢи©ҰгҒҝгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒж•…гҒ«гҖҒгҖҢе®—ж•ҷзҡ„гӮўгғ—гғӯгғјгғҒгҖҚгҒЁгҒ®гӮҝгӮӨгғҲгғ«гӮ’д»ҳгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒ“гҒ®з« гҒҜгҖҒдёүйғЁж§ӢжҲҗгӮ’гҒЁгӮӢгҖӮ
гҒҫгҒҡгҖҒзҰ…пјҲеӨ§д№—д»Ҹж•ҷпјүгҒЁгғҙгӮЈгғ‘гғғгӮөгғҠгғјпјҲдёҠеә§д»Ҹж•ҷпјүгҒҢжҢҒгҒӨеҝғиӯҳи«–гҒ®жҜ”ијғгӮ’дёӯеҝғгҒЁгҒ—гҒҹгҖҒ第дёҖйғЁгҖӮ
ж¬ЎгҒ«гҖҒзҰ…гғ»гғҙгӮЈгғ‘гғғгӮөгғҠгғјзһ‘жғіпјҲиҮӘеҠӣй–ҖпјүгҒЁеҶ…иҰігғ»гӮӯгғӘгӮ№гғҲж•ҷпјҲд»–еҠӣй–ҖпјүгҒЁгҒ®жҜ”ијғгӮ’дё»и»ёгҒЁгҒ—гҒҹгҖҒ第дәҢйғЁгҖӮ
жңҖеҫҢгҒ«гҖҒжҚЁ(upekkhДҒ)гҒЁж…ҲжӮІ(MettДҒ)гҒӘгҒ©гҖҒеҲ°йҒ”ең°зӮ№гҒЁгҒ—гҒҰгҒ®гҖҢеўғең°гҖҚгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰеҲҶжһҗгӮ’гҒҠгҒ“гҒӘгҒҶгҖҒ第дёүйғЁгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
гҖҗзӣ®ж¬ЎгҖ‘
第дёҖйғЁ
0гҖҖеӯҳеңЁи«–зҡ„гғ»иӘҚиӯҳи«–зҡ„гғ»иЁҖиӘһи«–зҡ„
1гҖҖжі•гҒЁжҰӮеҝө(paГұГұatti)
2гҖҖдә”иҳҠгҒЁе…ӯй–Җ/зёҒиө·
3гҖҖеҝө(Sati)гҒЁе®ҡ(SamДҒdhi)
4гҖҖз„Ўеёёгғ»иӢҰгғ»з„ЎжҲ‘пјҲдёүзӣёпјүгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰ
第дәҢйғЁ
第дёүйғЁ
жҚЁ(upekkhДҒ)гҒЁж…ҲжӮІ(MettДҒ)
еӯҳеңЁи«–зҡ„гғ»иӘҚиӯҳи«–зҡ„гғ»иЁҖиӘһи«–зҡ„
гҒ“гҒ“гҒӢгӮүгҖҒд»Ҹж•ҷгҒ®е®ҹи·өзҗҶи«–гӮ’йҖҡжҷӮзҡ„гҒ«пјҲжҷӮй–“и»ёгҒ«жІҝгҒЈгҒҰгҖҒжӯҙеҸІзҡ„гҒ«пјүеҲҶжһҗгҒ—гҒҰгҒ„гҒҸгҒ«гҒӮгҒҹгӮҠгҖҒгҖҢгғ‘гғ©гғҖгӮӨгғ гҖҚгҒЁгҒ„гҒҶжҰӮеҝөпјҲи§ЈжһҗиЈ…зҪ®пјүгӮ’е°Һе…ҘгҒ—гҒҰгҒҝгҒҹгҒ„гҖӮ
гҒқгӮҢгҒҜгҖҒгҒӮгӮӢжҷӮд»ЈгҒ®гӮӮгҒ®гҒ®иҰӢж–№гғ»иҖғгҒҲж–№гӮ’ж”ҜгҒҲгҖҒжҲҗз«ӢгҒ•гҒӣгҒҰгҒ„гӮӢгҖҢиӘҚиӯҳгҒ®жһ зө„гҒҝгҖҚгҒ®еҰӮгҒҚгӮӮгҒ®вҖ• е–©гҒҲгҒ°гҖҒзӣёж’ІгҒЁдә‘гҒҶ競жҠҖгҒ®еҸ–гӮҠзө„гҒҝгҒҜеңҹдҝөгҒ®дёҠгҒ§иЎҢгӮҸгӮҢгӮӢгҖӮгҒқгӮҢгҒЁеҗҢгҒҳгӮҲгҒҶгҒ«гҖҒгӮҸгӮҢгӮҸгӮҢгҒҢзҹҘзҡ„жҺўжұӮгӮ’иЎҢгҒҶйҡӣгҖҒгҒқгҒ®е®ҹи·өгӮ’з„ЎиҮӘиҰҡзҡ„гҒ«пјҲеүҚжҸҗгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒеёёгҒ«/ж—ўгҒ«пјүж”ҜгҒҲгҒҰгҒ„гӮӢеңҹеҸ°гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгӮӮгҒ®вҖ• гҒқгӮҢгӮ’гҖҒгҒ“гҒ“гҒ§гҒҜгҖҢгғ‘гғ©гғҖгӮӨгғ гҖҚгҒЁе‘јгҒ¶гҖӮ
и©ігҒ—гҒҸгҒҜгҖҒгҖҺгғ‘гғ©гғҖгӮӨгғ гҒЁгҒҜдҪ•гҒӢ гӮҜгғјгғігҒ®з§‘еӯҰеҸІйқ©е‘ҪгҖҸгҒӘгҒ©гӮ’гҒ”иҰ§гҒ„гҒҹгҒ гҒҚгҒҹгҒ„гҖӮ
1 еӯҳеңЁи«–зҡ„-е•ҸйЎҢиЁӯе®ҡпјҲгғ‘гғ©гғҖгӮӨгғ пјү
е®Үе®ҷгҒҜпјҲгҒқгҒ—гҒҰгҖҒз§ҒгҒҹгҒЎгҒҜпјүдҪ•гҒ§гҒ§гҒҚгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒӢгҖӮ
дё–з•ҢгҒ«зңҹгҒ«еӯҳеңЁгҒҷгӮӢгӮӮгҒ®пјҲеҺҹиіӘж–ҷпјүгҒҜдҪ•гҒӢгҖӮ
дҪ•гҒҢжң¬еҪ“гҒ«пјҲе®ҹдҪ“гҒЁгҒ—гҒҰпјүеӯҳеңЁгҒҷгӮӢгҒ®гҒӢгҖӮ
гҒЁгҒ®е•ҸгҒ„гҒ«е§ӢгҒҫгӮӢжҺўжұӮгҖӮ
гҒқгҒ®зӯ”гҒҲгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒеҸӨд»ЈгҒ®е®—ж•ҷе“ІеӯҰгҒҢжҢҒгҒӨгҖҒдә”еӨ§пјҲдә”гҒӨгҒ®ж №жң¬зү©иіӘпјүи«–гҒҢгҒӮгӮҠгҖҒгӮўгғјгғҲгғһгғі/гғ–гғ©гғ•гғһгғіжҖқжғігҒҢгҒӮгӮҠгҖҒйҒ“ж•ҷзҡ„гҒӘжҖқиҖғгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒгҒқгҒ®жөҒеҮәпҪһеҶҚеҗҲдёҖ/еҶҚиһҚеҗҲгҒҢе®—ж•ҷзҡ„гҒӘе®ҹи·өиӘІйЎҢгҒЁгҒ—гҒҰжұӮгӮҒгӮүгӮҢгҒҹгҖӮ
дә”еӨ§ – Wikipedia
дә”еӨ§е…ғзҙ – Wikipedia
иҮӘ/д»–пјҲдё–з•Ңгғ»зҘһпјүеҲҶйӣў вҶ’ иҮӘ/д»–пјҲдё–з•Ңгғ»зҘһпјүиһҚеҗҲгҒёгҖӮ
еҲҶйӣў/иһҚеҗҲгғўгғҮгғ«гҖӮ
е…ЁдҪ“гҒЁеҖӢдәәгҒ®еҗҲдёҖгҖӮ
зҸҫиұЎдё–з•ҢпјҲд»–гғ»жңүгғ»дәҢе…ғпјүгҒӢгӮүгҖҒз„Ўгғ»дёҖиҖ…гғ»дёҖе…ғгҒёгҒ®её°е…ҘгҖӮ
гҒқгҒ“гҒӢгӮүгҖҒзө¶еҜҫз„ЎгҒ®гғҸгӮҝгғ©гӮӯгҒЁгҒ—гҒҰгҒ®зҸҫиұЎдё–з•ҢпјҲеҰҷжңүпјүгҒёгҒ®жөҒеҮәгҖӮ
е·®еҲҘ вҶ’ е№ізӯү вҶ’ е№ізӯүеҚіе·®еҲҘгҖӮ
жҲ‘гҒҜзҘһгҒӘгӮҠпјҒ
2 иӘҚиӯҳи«–зҡ„-е•ҸйЎҢиЁӯе®ҡпјҲгғ‘гғ©гғҖгӮӨгғ пјү
з§ҒгҒҹгҒЎгҒҜгҖҒгҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«дё–з•ҢгӮ’иӘҚиӯҳгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒӢпјҹ
з§ҒгҒҹгҒЎгҒ®дё–з•ҢгӮ’иӘҚиӯҳгҒҷгӮӢд»•зө„гҒҝгҒҜгҒ©гҒҶгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒӢпјҹ
гҒқгҒ—гҒҰгҖҒгҒ©гҒ“гҒ§е•ҸйЎҢпјҲгғҗгӮ°гғ»гӮЁгғ©гғјгғ»иӢҰгҒ—гҒҝпјүгҒҢз”ҹгҒҳгӮӢгҒ®гҒӢпјҹ
гҒЁгҒ®е•ҸгҒ„гҒ«еҹәгҒҘгҒ„гҒҹжҺўжұӮгҖӮ
иӘҚиӯҳгҒ®ж§ӢйҖ гҒЁгҖҒгҒқгӮҢгҒҢжҢҒгҒӨгӮЁгғ©гғјпјҲгғҗгӮ°пјүгҒ®и§ЈжҳҺ
гҖҢдё–з•ҢгҒқгҒ®гӮӮгҒ®гҖҚгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒгҒқгӮҢгӮ’иӘҚиӯҳгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢиҮӘиә«гҒ®еҒҙгҖҒиӘҚиӯҳгҒ®ж§ӢйҖ гҒ®и§ЈжҳҺгҒҢдёӯеҝғгҒЁгҒӘгӮӢгҖҒеҺҹе§Ӣд»Ҹж•ҷгҒ«д»ЈиЎЁгҒ•гӮҢгӮӢз«Ӣе ҙгҖӮ
дё–з•ҢгҒ®е§ӢгҒҫгӮҠгӮ’ж„Ҹиӯҳ(иӘҚиӯҳ)гҒ®е§ӢгҒҫгӮҠгҒ«гҒҠгҒҸгҖӮ
иӘҚиӯҳгҒ®йҷҗз•ҢгҒҢдё–з•ҢгҒ®йҷҗз•Ңз·ҡ
и¶…гҖҢиҰіеҝөпҪЈи«–гҖҒи¶…гҖҢе”ҜиӯҳпҪЈи«–
гғһгғғгғҸе“ІеӯҰпјҲж„ҹиҰҡиҰҒзҙ дёҖе…ғи«–пјүгҒЁгҒ®иҰӘе’ҢжҖ§ вҶ’ гӮЁгғ«гғігӮ№гғҲгғ»гғһгғғгғҸ – Wikipedia
зҸҫд»ЈиӘҚзҹҘ科еӯҰгҒЁгҒ®иҰӘе’ҢжҖ§пјҲеҶ…зҡ„гғ»еҶ…иҰіиӘҚзҹҘ科еӯҰпјү
гҒҝгҒӘгҒ•гӮ“гҖҒгӮҸгҒҹгҒ—гҒҜгҖҢдёҖеҲҮгҖҚгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰи©ұгҒқгҒҶгҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгӮҲгҒҸиҒһгҒ„гҒҰдёӢгҒ•гҒ„гҖӮгҖҢдёҖеҲҮ гҖҚгҒЁгҒҜгҖҒгҒҝгҒӘгҒ•гӮ“гҖҒгҒ„гҒЈгҒҹгҒ„дҪ•гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒӢгҖӮ
гҒқгӮҢгҒҜгҖҒзңјгҒЁзңјгҒ«иҰӢгҒҲгӮӢгӮӮгҒ®гҖҒиҖігҒЁиҖігҒ«иҒһгҒ“гҒҲгӮӢгӮӮгҒ®гҖҒйј»гҒЁйј»гҒ«еҢӮгҒҶгӮӮгҒ®гҖҒиҲҢгҒЁиҲҢгҒ«е‘ігӮҸгӮҸгӮҢгӮӢгӮӮгҒ®гҖҒиә«дҪ“гҒЁиә«дҪ“гҒ«жҺҘи§ҰгҒ•гӮҢгӮӢгӮӮгҒ®гҖҒеҝғгҒЁеҝғгҒ®дҪңз”ЁгҒ®гҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒ“гӮҢгҒҢгҖҢдёҖеҲҮгҖҚгҒЁе‘јгҒ°гӮҢгӮӢгӮӮгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮиӘ°гҒӢгҒҢгҒ“гҒ®гҖҢдёҖеҲҮгҖҚгӮ’еҗҰе®ҡгҒ—гҖҒгҒ“гӮҢгҒЁгҒҜеҲҘгҒ®гҖҢдёҖеҲҮгҖҚгӮ’иӘ¬гҒ“гҒҶгҒЁдё»ејөгҒҷгӮӢгҒЁгҒҚгҖҒгҒқгӮҢгҒҜзөҗеұҖгҖҒиЁҖи‘үгҒ гҒ‘гҒ«зөӮгӮҸгӮүгҒ–гӮӢгӮ’еҫ—гҒӘгҒ„гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
гҒ•гӮүгҒ«еҪјгӮ’е•ҸгҒ„и©°гӮҒгӮӢгҒЁгҖҒгҒқгҒ®дё»ејөгӮ’иӘ¬жҳҺгҒ§гҒҚгҒҡгҖҒз—…гҒ«еҖ’гӮҢгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҒӢгӮӮзҹҘгӮҢгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮдҪ•ж•…гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒӢгҖӮдҪ•ж•…гҒӘгӮүгҖҒеҪјгҒ®дё»ејөгҒҢеҪјгҒ®зҹҘиӯҳй ҳеҹҹгӮ’и¶ҠгҒҲгҒҰгҒ„гӮӢгҒӢгӮүгҒ§гҒҷгҖӮ
пјҲSanyutta-Nikaya 33.1.3 пјү
гҖҺгҒ“гҒЁгҒ°гҒЁжҖқиҖғгҖҸеІ©жіўж–°жӣё
гҖҺиЁҖиӘһгҒ®жң¬иіӘ-гҒ“гҒЁгҒ°гҒҜгҒ©гҒҶз”ҹгҒҫгӮҢгҖҒйҖІеҢ–гҒ—гҒҹгҒӢгҖҸ
3 иЁҖиӘһи«–зҡ„-е•ҸйЎҢиЁӯе®ҡпјҲгғ‘гғ©гғҖгӮӨгғ пјү
иЁҖи‘үпјҲиЁҖиӘһгғ»жҰӮеҝөпјүгҒҜгҒ„гҒӢгҒ«гҒ—гҒҰжҲ‘гҖ…гҒ®иӘҚиӯҳгӮ’еҪўдҪңгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒӢпјҹ
иЁҖиӘһзҡ„иӘҚиӯҳгӮ’зөҢз”ұгҒ—гҒӘгҒ„дё–з•ҢгҒқгҒ®гӮӮгҒ®гҒЁгҒҜпјҹ
иЁҖиӘһгҒҜеҰӮдҪ•гҒ«гҒ—гҒҰгҖҒиҝ·гҒ„гӮ’з”ҹгҒҝеҮәгҒҷпјҲдё–з•ҢгӮ’гҒӮгӮӢгҒҢгҒҫгҒҫгҒ«иҰӢгҒҲгҒӘгҒҸгҒҷгӮӢпјүгҒ®гҒӢпјҹ
гҒӘгҒ©гҒ®е•ҸйЎҢиЁӯе®ҡгҒ§зҗҶи«–зҡ„/е®ҹи·өзҡ„жҺўз©¶гҒҢиЎҢгӮҸгӮҢгӮӢгҖӮ
д»ЈиЎЁзҡ„гҒ«гҒҜгҖҒгҖҺдёӯи«–гҖҸпјҲгғҠгғјгӮ¬гғјгғ«гӮёгғҘгғҠпјүгҒӢгӮүе§ӢгҒҫгӮӢз«Ӣе ҙгҖӮ
гҖҢиә«(гҒҝ)еҲҶгҒ‘ж§ӢйҖ гҖҚгҒЁгҖҢиЁҖ(гҒ“гҒЁ)еҲҶгҒ‘ж§ӢйҖ гҖҚгҖҖдёёеұұеңӯдёүйғҺ
дёёеұұгҒ•гӮ“гҒҜгҒ“гҒ®жң¬гҒ§гҖҒгҖҢиә«(гҒҝ)еҲҶгҒ‘ж§ӢйҖ гҖҚгҒЁгҖҢиЁҖ(гҒ“гҒЁ)еҲҶгҒ‘ж§ӢйҖ гҖҚгҒЁгҒ„гҒҶиЁҖи‘үгӮ’з”ЁгҒ„гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҖҢиә«еҲҶгҒ‘гҖҚгҒ®ж–№гҒҜгҖҒгҒҹгҒЁгҒҲгҒ°дәәй–“д»ҘеӨ–гҒ®еӢ•зү©гҒ«гӮӮе…ұйҖҡгҒҷгӮӢгҖҒжң¬иғҪзҡ„гҒӘдё–з•ҢиҰігҒ§гҒҷгҖӮдәәй–“гҒҜгҒқгӮҢгҒЁгҒҜйҒ•гҒҶдё–з•ҢиҰігӮ’жҢҒгҒЎиҫјгҒҝгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒқгӮҢгҒҢиЁҖиӘһгҒ«гӮҲгӮӢгҖҢиЁҖеҲҶгҒ‘гҖҚгҒ§гҒҷгҖӮгӮҪгӮ·гғҘгғјгғ«зҡ„гҒЁиЁҖгҒ„гҒҫгҒҷгҒӢгҖҒж§ӢйҖ дё»зҫ©зҡ„гҒЁиЁҖгҒ„гҒҫгҒҷгҒӢгҖҒд»ҠгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒҜгғҺгӮ№гӮҝгғ«гӮёгғјгҒ®еҜҫиұЎгҒ«гӮӮгҒӘгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒгҖҢиЁҖиӘһгҒЁгҒ„гҒҶйҒ“е…·гӮ’гӮӮгҒЈгҒҰгҒ“гҒ®дё–гӮ’еҲҶзҜҖгҒҷгӮӢгҖӮгҒқгӮҢгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰеҲқгӮҒгҒҰдәӢзү©гҒҢе®ҹдҪ“еҢ–гҒҷгӮӢгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶгӮҲгҒҶгҒӘзҷәжғігҒ§гҒҷгҒӯгҖӮ
гҒқгҒ—гҒҰгҖҒдёёеұұгҒ•гӮ“гҒҜгҖҒжң¬иғҪзҡ„гҒӘгҖҢиә«еҲҶгҒ‘ж§ӢйҖ гҖҚгҒӢгӮүйҖёи„ұгҒ—гҒҹгҖҢиЁҖеҲҶгҒ‘ж§ӢйҖ гҖҚгҒЁгҒ„гҒҶгҖҢйҒҺеү°гҖҚгҒ“гҒқгҒҢгҖҒдәәй–“гҒ®гҖҢж–ҮеҢ–гҖҚгҒ гҒЁиӘһгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
жқұжҙӢе“ІеӯҰгҒ®е…ұжҷӮзҡ„ж§ӢйҖ еҢ–
дә•зӯ’дҝҠеҪҰгҒҢгҒ„гҒҶгҖҢгӮігғҲгғҗгҖҚгҒҜгҒӮгӮӢдәӢзү©гӮ’жҢҮзӨәгҒҷгӮӢйҒ“е…·гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҖӮгӮҖгҒ—гӮҚгҖҒгҖҢгӮігғҲгғҗгҖҚгҒҢж··жІҢгҒӢгӮүе®ҹеңЁгӮ’е‘јгҒіиө·гҒ“гҒҷеүөйҖ зҡ„гӮЁгғҚгғ«гӮ®гғјгҒ гҒЁеҪјгҒҜгҒ„гҒҶгҖӮ
гҖҺж„ҸиӯҳгҒЁжң¬иіӘвҖ• зІҫзҘһзҡ„жқұжҙӢгӮ’зҙўгӮҒгҒҰгҖҸ дә•зӯ’ дҝҠеҪҰ
гҖҺзҰ…д»Ҹж•ҷвҖ• ж №жәҗзҡ„дәәй–“гҖҸ дёҠз”° й–‘з…§
гҖҺгғҸгӮӨгғҮгӮ¬гғјпјқеӯҳеңЁзҘһз§ҳгҒ®е“ІеӯҰгҖҸ еҸӨжқұе“ІжҳҺгҖҖгҖҖеҗҢгҖҺжІҲй»ҷгҖҸпјҲи«–ж–Үпјү
гғ»еӨ§д№—д»Ҹж•ҷгҒ®гҖҢеүөйҖ зҡ„иӘӨиӘӯгҖҚгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰ
пјҠ Art of AwarenessгҒ®зҗҶи«–ж§ӢжҲҗе…ЁдҪ“гҒЁгҒ—гҒҰгҒҜгҖҒд»ҘдёӢгҒ®гӮӮгҒ®гҒЁгҒӘгӮӢгҖӮ
- еӯҳеңЁи«–зҡ„и»ўжҸӣ
- иӘҚиӯҳи«–зҡ„и»ўжҸӣ
- иЁҖиӘһи«–зҡ„и»ўжҸӣ
- и§ЈйҮҲеӯҰзҡ„и»ўжҸӣ
- иҮӘ然主зҫ©зҡ„пјҲз”ҹзү©еӯҰзҡ„пјүи»ўжҸӣ
- иә«дҪ“и«–зҡ„и»ўжҸӣ
д»ҘдёӢгҖҒжі•гҒЁжҰӮеҝөпјҲгғ‘гғігғӢгғЈгғғгғҶгӮЈ/ж–ҪиЁӯпјүгҖҒдә”иҳҠ/е…ӯй–ҖпјҲзёҒиө·пјүгҖҒеҝөпјҲSati)/е®ҡпјҲSamДҒdhiпјүгҒӘгҒ©гҖҒеҲқжңҹд»Ҹж•ҷгҒ§жҲҗз«ӢгҒ—гҒҹеҹәжң¬жҰӮеҝөгҒҢпјҲгғ‘гғ©гғҖгӮӨгғ гҒ®еӨү移гҒ®гҒӘгҒӢгҒ§пјүгҒ„гҒӢгҒ«гҒқгҒ®жҰӮеҝөеҶ…е®№гӮ’еӨүгҒҲгҖҒеӨүеҢ–гғ»еӨүиіӘгҒ—гҒҰгҒ„гҒЈгҒҹгҒ®гҒӢгӮ’иҰӢгҒҰгҒ„гҒҸгҖӮ
еҲқжңҹд»Ҹж•ҷгӮ„еӨ§д№—д»Ҹж•ҷгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰиҖғгҒҲгӮӢгҒ«гҒҜгҖҒгҖҢжҷӮй–“гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒ®иӘҚиӯҳгҖҚвҖ• жҷӮй–“гӮ’гҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгӮӮгҒ®гҒЁгҒ—гҒҰжҚүгҒҲгӮӢгҒӢгҖҒгҒқгҒ—гҒҰгҖҢиЁҖи‘үгҒ«й–ўгҒҷгӮӢиӘҚиӯҳгҖҚвҖ• иЁҖиӘһгҒ®еғҚгҒҚгӮ’гҖҒгҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘгӮӮгҒ®гҒЁгҒ—гҒҰжҚүгҒҲгӮӢгҒӢвҖ• гҒҢеӨ§гҒҚгҒӘйҚөгҒЁгҒӘгӮӢгҖӮ
гҒҫгҒҡеҲқгӮҒгҒ«иӘҚгӮҒгҒҰгҒҠгҒҸгҒ№гҒҚгҒҜгҖҒжҷӮй–“гҒ«й–ўгҒҷгӮӢе•ҸгҒ„гҒ«дәәй–“гҒҢгҒ©гӮҢгҒ гҒ‘зӯ”гҒҲгӮүгӮҢгӮӢгҒӢгҒҜгҖҒгҒқгҒҶгҒ—гҒҹе•ҸгҒ„гӮ’зҷәгҒҷгӮӢеҷЁе®ҳгҒ®жҖ§иіӘгҒ«еҲ¶зҙ„гҒ•гӮҢгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ гҖӮ
й ӯи“ӢеҶ…йғЁгҒ«и©°гҒҫгҒЈгҒҹи„ізҙ°иғһдёҖеҚғе„„еҖӢгҒ®жҹ”зө„з№”гҒҜжҲ‘гҖ…гҒ®зҹҘгӮӢе®Үе®ҷгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢжңҖгӮӮжҙ—з·ҙгҒ•гӮҢгҒҹиЈ…зҪ®гҒ§гҒҜгҒӮгӮҢгҒ©гҖҒжҷӮй–“гҒ®жҖ§иіӘгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰзҗҶи§ЈгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҖҢиЁӯиЁҲгҖҚгҒ•гӮҢгҒҹгӮҸгҒ‘гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҖӮгғҺгғјгғҲPCгҒҢиҮӘгӮүгҒ®гӮҪгғ•гғҲгӮҰгӮ§гӮўгӮ’жӣёгҒҸгӮҲгҒҶгҒ«иЁӯиЁҲгҒ•гӮҢгҒҹгӮҸгҒ‘гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҒ«гҖӮ
жҷӮй–“гҒ«й–ўгҒҷгӮӢе•ҸйЎҢгҒ«жҺўгӮҠгӮ’е…ҘгӮҢгӮӢгҒӘгҒӢгҒ§жҖқгҒ„зҹҘгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮӢгҒҢгҖҒжҷӮй–“гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒ®жҲ‘гҖ…гҒ®зӣҙиҰігӮ„зҗҶи«–гҒҜжҷӮй–“гҒ®жҖ§иіӘгӮ’гҒӮгӮүгӮҸгҒ«гҒ—гҒӨгҒӨгҖҒгҒқгӮҢгҒЁеҗҢгҒҳгҒҸгӮүгҒ„гҖҒжҲ‘гҖ…иҮӘиә«гҒ®и„ігҒ®ж§ӢйҖ еҺҹзҗҶгӮ„йҷҗз•ҢгӮӮгҒӮгӮүгӮҸгҒ«гҒҷгӮӢгҒ®гҒ гҖӮ
гҖҺи„ігҒЁжҷӮй–“гҖҸгғҮгӮЈгғјгғігғ»гғ–гӮӘгғҺгғһгғјгғҺи‘—
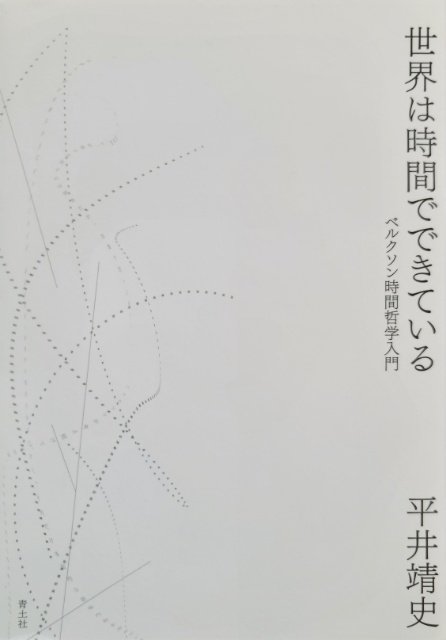
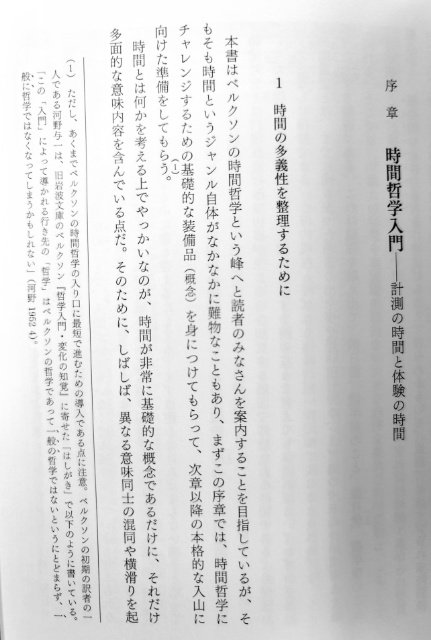
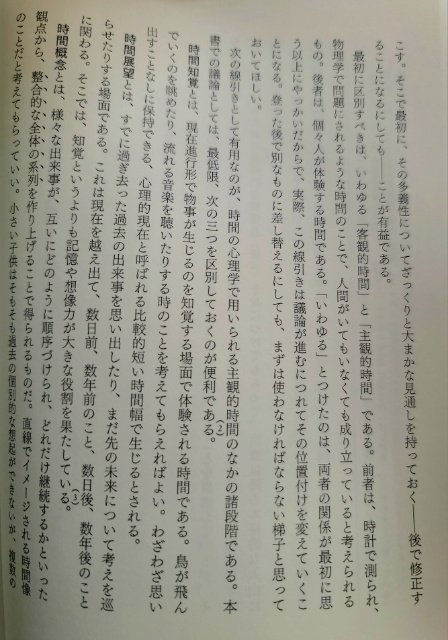
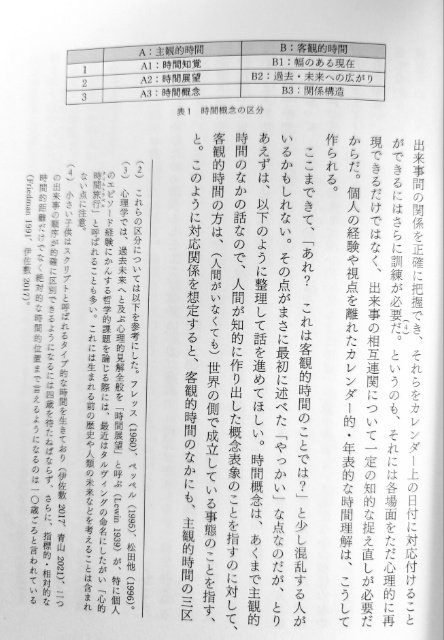
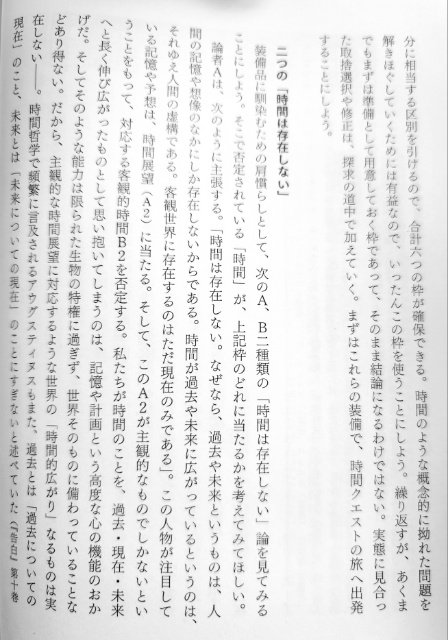
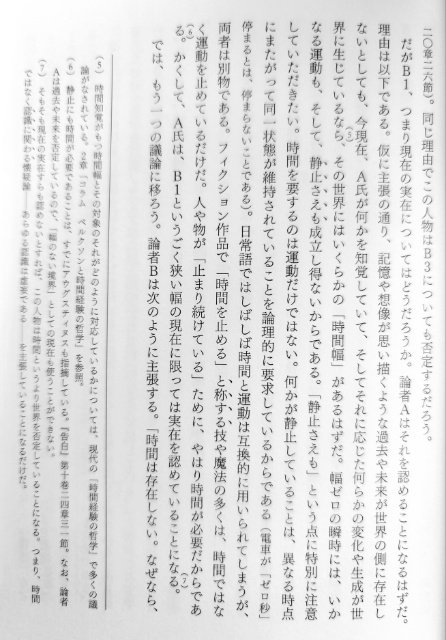
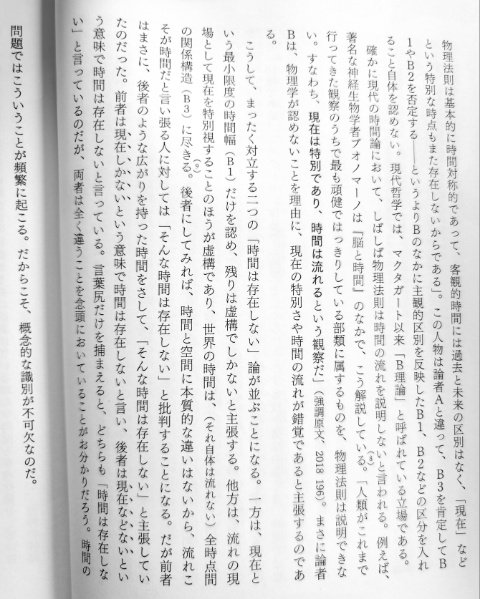
жҷӮй–“гҒҜгӮҸгҒҹгҒ—гӮ’дҪңгӮҠдёҠгҒ’гҒҰгҒ„гӮӢе®ҹдҪ“гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
жҷӮй–“гҒҜгӮҸгҒҹгҒ—гӮ’жҠјгҒ—жөҒгҒҷе·қгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгӮҸгҒҹгҒ—гҒҜгҒқгҒ®е·қгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
гҒқгӮҢгҒҜгӮҸгҒҹгҒ—гӮ’еј•гҒҚиЈӮгҒҸиҷҺгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгӮҸгҒҹгҒ—гҒҜгҒқгҒ®иҷҺгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
гҒқгӮҢгҒҜгӮҸгҒҹгҒ—гӮ’з„јгҒҚе°ҪгҒҸгҒҷзҒ«гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгӮҸгҒҹгҒ—гҒҜгҒқгҒ®зҒ«гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
дё–з•ҢгҒҜдёҚе№ёгҒ«гҒ—гҒҰзҸҫе®ҹгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгӮҸгҒҹгҒ—гҒҜдёҚе№ёгҒ«гҒ—гҒҰгғңгғ«гғҳгӮ№гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
гҖҺжҷӮй–“гҒ«й–ўгҒҷгӮӢж–°гҒҹгҒӘеҸҚй§ҒгҖҸ Jгғ»Lгғ»гғңгғ«гҒёгӮ№
жі•гҒЁжҰӮеҝөпјҲдәӢе®ҹгҒЁгӮӨгғЎгғјгӮёпјү
з§ҒгҒҹгҒЎгҒҢзҸҫе®ҹгҒ«зөҢйЁ“гғ»иҰіеҜҹгҒҷгӮӢдҪ•гҒ§гҒӮгӮҢгҖҒгҒқгӮҢгӮ’гҖҒгҒқгҒ®еҜҫиұЎгӮ’жҢҮгҒ—зӨәгҒҷгҖҢиЁҖи‘үгғ»жҰӮеҝөгғ»гӮӨгғЎгғјгӮёпјҲеҝғиұЎпјүгҖҚгӮ’еүҘгҒҺиҗҪгҒЁгҒ—гҒҹзҠ¶ж…ӢгҒ§гҖҒгҒқгҒ®иЁҖи‘үгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰжҢҮгҒ—зӨәгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖҢеҪ“гҒ®гӮӮгҒ®гҖҚгҒ«ж„ҸиӯҳгҒ®з„ҰзӮ№гӮ’еҪ“гҒҰгҖҒгҒқгӮҢгӮ’ж„ҹгҒҳгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҒ гӮҚгҒҶгҒӢгҖӮ
е°ҸеӯҰж Ўпј“е№ҙз”ҹгҒ®й ғгҒ гҒЈгҒҹгҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
зҗҶ科гҒ®жҺҲжҘӯгҒ§еӨңз©әгҒ®жҳҹеә§гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰзҝ’гҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гӮӘгғӘгӮӘгғіеә§гҖҒеҢ—ж–—дёғжҳҹвҖҰ гҒқгӮҢгҒҢгҖҒеӨңгҒ®з©әгҒ®гҖҒгҒ©гҒ“гҒ«гҖҒгҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«иҰӢгҒҲгӮӢгҒ®гҒӢгҖҒеӣіи§Је…ҘгӮҠгҒ§иӘ¬жҳҺгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒқгҒ®еҫҢгҖҒеӨңз©әгӮ’зңәгӮҒгӮӢгҒЁгҖҒгҒ„гҒӨгҒ§гӮӮгҖҒгҒҷгҒҗгҒ«гӮӘгғӘгӮӘгғіеә§гӮ’иҰӢгҒӨгҒ‘гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
жҲҗдәәеҫҢгҖҒ科еӯҰе•“и’ҷжӣёгӮ’иӘӯгӮҖгҒ®гҒҢеҘҪгҒҚгҒ«гҒӘгӮҠгҖҒе®Үе®ҷи«–гӮ„еӨ©ж–Ү科еӯҰгҒ®жң¬гҒ«иҰӘгҒ—гӮҖгҒӘгҒӢгҒ§гҖҒиүІгҖ…гҒӘгҒ“гҒЁгӮ’зҹҘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
1000е№ҙгҒЁгҒӢгҒ®жҷӮй–“гҒ®еҚҳдҪҚгҒ§гҒҝгӮӢгҒЁгҖҒжҳҹгҒ®дҪҚзҪ®гҒҜеӣәе®ҡгҒ•гӮҢгҒҰгҒҠгӮүгҒҡгҖҒжөҒеӢ•зҡ„гҒ«еӢ•гҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁпјҲгҒӨгҒҫгӮҠгҖҒгҒ„гҒҫгҖҒгҒ“гҒ®гӮ«гӮҝгғҒгҒ§гҖҒгҒ“гҒ®жҳҹеә§гӮ’иҰӢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒҜгҖҒгҒ“гҒ®жҷӮд»ЈгҒ®жҲ‘гҖ…гҒ гҒ‘гҒ§гҖҒжңӘжқҘгҒ®дәәйЎһгҒҜйҒ•гҒҶгӮӮгҒ®гӮ’иҰӢгӮӢгҒ“гҒЁпјү
жҳҹеә§гҒҜгҖҒгҒқгӮҢгҒһгӮҢгҒ®ж°‘ж—ҸгҒ®жҢҒгҒӨж–ҮеҢ–гғ»зҘһи©ұгҒӘгҒ©гҒ«еҹәгҒҘгҒҸйҖЈжғігҒ§гҒ—гҒӢгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҖҒгӮ®гғӘгӮ·гғЈгғ»иҘҝжҙӢж–ҮеҢ–д»ҘеӨ–гҒ®гҒЁгҒ“гӮҚгҒ§гҒҜгҖҒжҳҹгӮ’е…ЁгҒҸйҒ•гҒҶйҖЈгҒӘгӮҠгҒ§пјҲз•°гҒӘгӮӢз”ҹгҒҚзү©гҒӘгҒ©гҒ«гҒӘгҒһгӮүгҒҲгҒҰпјүиҰӢгҒҰгҒ„гӮӢпјҲиӘҚиӯҳгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢпјүгҒ“гҒЁ
жҳҹеә§гӮ’ж§ӢжҲҗгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢжҳҹгҒҜгҖҒе®ҹгҒҜгҖҒең°зҗғд»ҘеӨ–гҒ®ж–№еҗ‘гҒӢгӮүиҰӢгҒҹгӮүгҖҒдҪ•е…үе№ҙгӮӮеүҚеҫҢгҒ«гҒҡгӮҢгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒжЁӘдёҰгҒігҒ«дёҰгӮ“гҒ§гҒҜгҒ„гҒӘгҒ„гҒ“гҒЁпјҲгҒӨгҒҫгӮҠгҖҒгҒ“гҒ®ең°зҗғгҒӢгӮүгҒ®иҰ–зӮ№гҒ§гҒ®гҒҝгҖҒж„Ҹе‘ігҒӮгӮӢйҖЈгҒӘгӮҠгӮ’гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгӮҲгҒҶгҒ«иҰӢгҒҲгҒҰгҒ„гӮӢгҒ«йҒҺгҒҺгҒӘгҒ„гҒ“гҒЁпјүгҒӘгҒ©гҖҒеӨҡгҒҸгҒ®гҒ“гҒЁгӮ’жҘҪгҒ—гҒҝгҒӨгҒӨеӯҰгҒігҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒқгӮҢгӮүгҒ®зөҗи«–гҒЁгҒ—гҒҰгҖҒгҖҢгӮӘгғӘгӮӘгғіеә§гҒЁгҒҜгҖҒзҸҫд»Јж—Ҙжң¬дәәгҒЁгҒ—гҒҰж•ҷиӮІгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҰгҒҚгҒҹз§ҒгҒЁдә‘гҒҶеҖӢдәәгҒ®й ӯгҒ®дёӯгҒ«гҒӮгӮӢгҒ гҒ‘гҒ®еҰ„жғігҒ§гҖҒеӨ–з•ҢгҒ«еӯҳеңЁгҒ—гҒҰгҒҜгҒ„гҒӘгҒ„гҖҚгҒЁдә‘гҒҶгҒ“гҒЁгӮ’зҗҶи§ЈгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгҒқгҒ®дёҠгҒ§еӨңз©әгӮ’зңәгӮҒгҒҰгҒҝгҒҰгӮӮгҖҒз§ҒгҒ«гҒҜгӮӘгғӘгӮӘгғіеә§гҒҢиҰӢгҒҲгҒҰгҒ—гҒҫгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ„гҒҫгҒ§гӮӮгҖҒдёғгҒӨгҒ®жҳҹгҒҢзҙ°гҒ„з·ҡгҒ§з№ӢгҒҢгӮҢгҖҒдәӢе®ҹгҖҒгҒІгҒЁгҒҫгҒЁгҒҫгӮҠгҒ®еӣіеҪўгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«иҰӢгҒҲгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҒ“гҒЁгҒ«еӨүгӮҸгӮҠгҒҜгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
д»ҘдёҠгҒ®и©ұгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒгҖҢжҳҹгҒ®гӮӯгғ©гғЎгӮӯпјқжі•гғ»дәӢе®ҹеӯҳеңЁгҒҷгӮӢгӮӮгҒ®гҖҚгҒ§гҖҒгҖҢгӮӘгғӘгӮӘгғіеә§пјқжҖқиҖғгғ»гӮӨгғЎгғјгӮёгғ»жҰӮеҝөгҖҚгҒӘгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгҒӢгӮҲгҒҶгҒ«гҖҢжҰӮеҝөгӮ’еӨ–гҒ—гҒҰдё–з•ҢгӮ’иҰігӮӢгҖҚгҒ“гҒЁгҒҜйӣЈгҒ—гҒҸгҖҒгҒ“гӮҢгҒЁеҗҢгҒҳгҒ“гҒЁгҒҢгҖҒз§ҒгҒҹгҒЎгҒҢиӘҚиӯҳгҒҷгӮӢе…ЁгҒҰвҖ• иҒҙиҰҡгғ»иҰ–иҰҡгҒӘгҒ©гҒ®еӨ–з•ҢзҹҘиҰҡгҖҒжҖқиҖғгғ»ж„ҹжғ…гғ»ж¬ІжұӮгҒӘгҒ©гҒ®ж„Ҹиӯҳз•ҢгҖҒиә«дҪ“ж„ҹиҰҡгғ»иә«дҪ“йҒӢеӢ•гӮ’дё»гҒЁгҒ—гҒҹгӮ«гғ©гғҖгҒ®дё–з•ҢвҖ• гҒ§зһ¬й–“зһ¬й–“иө·гҒ“гҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гғҖгғігғһпјҲеҚҳдёҖдҪ“пјүгҒЁгғ‘гғігғӢгғЈгғғгғҶгӮЈпјҲиӨҮеҗҲдҪ“пјү
иҮӘжҖ§ – Wikipedia
иҮӘжҖ§жё…жө„ – Wikipedia
гғ»дәҢи«ҰиӘ¬пјҲдё–дҝ—и«Ұ/еӢқзҫ©и«Ұпјү
дә”иҳҠгҒЁе…ӯй–Җ/зёҒиө·
еҲқжңҹд»Ҹж•ҷгҒ®еҝғиӯҳи«–пјҲж„ҸиӯҳгҒ®зҗҶи«–пјүгҒ®йӘЁзө„гҒҝгҒЁгҒӘгӮӢиӘҚиӯҳи«–зҡ„еҚҒеӯ—жһ¶гҖӮпјҲжЁӘгҒЁзёҰгҒ®еҲҶжһҗгҒ®зө„гҒҝеҗҲгӮҸгҒӣпјү
е®ҹи·өзҡ„гғ»иӘҚиӯҳи«–зҡ„гҒӘзёҒиө·иӘ¬
в—Ҹ е…ӯй–Җ
е…ҘеҠӣгғҒгғЈгғігғҚгғ«пјҲй ҳеҹҹпјүеҲҘгҒ§гҒ®еҲҶйЎһпјҲе…ұжҷӮзҡ„еҲҶжһҗпјү
е…ӯгҒӨгҒ®жғ…е ұе…ҘеҠӣгҒ®гғҒгғЈгғігғҚгғ«пјҲж„ҹиҰҡеҷЁе®ҳпјү
в—Ҹ дә”иҳҠпјҲгҒ”гҒҶгӮ“пјү
жҷӮзі»еҲ—гҒ§гҒ®иӘҚиӯҳгҒ®гғ—гғӯгӮ»гӮ№гҒ®еҲҶжһҗгҖҖпјҲйҖҡжҷӮзҡ„еҲҶжһҗпјү
иӘҚиӯҳи«–зҡ„зёҒиө·гҖҖи§ҰвҶ’еҸ—вҶ’жғівҶ’пјҲжҖқпјүвҶ’иЎҢвҶ’иӯҳ
зёҒиө·гҒЁгҒҜгҖҒд»–гҒЁгҒ®й–ўдҝӮгҒҢзёҒгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰз”ҹиө·гҒҷгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҖӮе…ЁгҒҰгҒ®зҸҫиұЎгҒҜгҖҒеҺҹеӣ гӮ„жқЎд»¶гҒҢзӣёдә’гҒ«й–ўдҝӮгҒ—гҒӮгҒЈгҒҰжҲҗз«ӢгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгҒЈгҒҰзӢ¬з«ӢиҮӘеӯҳгҒ®гӮӮгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒжқЎд»¶гӮ„еҺҹеӣ гҒҢгҒӘгҒҸгҒӘгӮҢгҒ°зөҗжһңгӮӮиҮӘгҒҡгҒӢгӮүгҒӘгҒҸгҒӘгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгӮ’жҢҮгҒҷгҖӮ
зёҒиө·гғ»зӣёдҫқжҖ§пјҲгҒқгҒҶгҒҲгҒ—гӮҮгҒҶпјү
и«–зҗҶзҡ„гғ»зӣёдә’дҫқеӯҳй–ўдҝӮпјҲдёӯи«–пјү
SatiгҒЁSamДҒdhiпјҲжҷӮй–“еҲҶи§ЈиғҪгҒЁз©әй–“еҲҶи§ЈиғҪпјү
SatiгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰ
SatiпјҲжҷӮй–“еҲҶи§ЈиғҪпјүгҖҖгӮ·гғЈгғғгӮҝгғјгӮ№гғ”гғјгғҲгҖҖеӢ•дҪ“иҰ–еҠӣгҖҖй«ҳйҖҹеәҰж’®еҪұ
еҺҹе§Ӣд»Ҹж•ҷзҡ„гҒӘиӘҚиӯҳгҖҒжҙһеҜҹзҹҘ
иӘӨи§ЈгҒҜгҖҒжҷӮй–“зҡ„гҒ«еҫ®зҙ°гҒӘгҖҒйқһеёёгҒ«йҖҹгҒ„гҖҒеҝғгҒ®иӘҚиӯҳгғ¬гғҷгғ«гҒ§иө·гҒ“гҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
иӘҚиӯҳгӮ’жҷӮй–“зҡ„гҒ«и©ізҙ°гҒ«еҲҶи§ЈгҒҷгӮӢгӮөгғҶгӮЈгҒҢеҝ…иҰҒгҒ«гҒӘгӮӢгҖӮ
е•ҸйЎҢгҒҜгҖҒгҖҢгҒ„гҒҫгҖҚгҒ®жңҖе°ҸеҚҳдҪҚгҒҢгҖҒгҒ©гҒ®зЁӢеәҰгҒ®гӮӮгҒ®гҒӢгҖҒгҒЁгҒ„гҒҶгҒЁгҒ“гӮҚгҒ«гҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гғ»жҳ з”»гҒ®гҒҹгҒЁгҒҲгҖҒпјҲеҶ…е®№гӮ’иҰӢгӮӢгҒӢгҖҒгӮігғһгӮ’иҰӢгӮӢгҒӢпјү
гғ»гғҶгғ¬гғ“гҒ®е–©гҒҲпјҲжҳ еғҸгӮ’иҰӢгӮӢгҒӢгҖҒгғүгғғгғҲгҒ®ж¶Ҳж»…гӮ’иҰӢгӮӢгҒӢпјү
гғ»еӯҳеңЁи«–зҡ„еҺҹеӯҗгҒЁиӘҚиӯҳи«–зҡ„еҺҹеӯҗпјҲжңҖе°ҸеҚҳдҪҚпјү
гғ»з”ҹзү©еӯҰзҡ„дёҖзһ¬
гҖҺеӢ•зү©гҒҜдё–з•ҢгӮ’гҒ©гҒҶиҰӢгӮӢгҒӢгҖҸ
p.пј‘пјҳпј’пҪһ
гӮөгғігғ—гғӘгғігӮ°жҷӮй–“гҖҖгӮ«гғЎгғ©гҒ®йңІеҮәжҷӮй–“
500еҲҶгҒ®1з§’гҒЁ15еҲҶгҒ®пј‘з§’гҖҖеҚҳдҪҚжҷӮй–“еҪ“гҒҹгӮҠгҒ®гӮігғһж•°
жҳ з”»гҖҖ1з§’гҒ«24гӮігғһ
пјЈпјҰпјҰпјҲиҮЁз•ҢиһҚеҗҲй »еәҰпјүпјқиҰ–иҰҡгҒ§гҒ®жҷӮй–“зҡ„еҲҶи§ЈиғҪпјҲи§ЈжҳҺеәҰпјү
гғҹгғ„гғҗгғҒгҒ®иҰ–иҰҡзҡ„дёҖгӮігғһгҒҜдәәй–“гҒ®5еҲҶгҒ®1зЁӢеәҰгҖӮ
дәәгҒ®зӣ®гҒ®жҷӮй–“еҲҶи§ЈиғҪгҒҜзҙ„50msпҪһ100msзЁӢеәҰгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҒ“гҒ®жҷӮй–“гӮҲгӮҠгӮӮзҹӯгҒ„е…үгҒ®зӮ№ж»…гҒҜйҖЈз¶ҡзӮ№зҒҜгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгӮҲгҒҶгҒ«зҹҘиҰҡгҒ•гӮҢгӮӢгҖӮ
дҫӢгҒҲгҒ°зҷҪзҶұйӣ»зҗғгҒ®е…үгҒҜе•Ҷз”Ёйӣ»жәҗе‘Ёжіўж•°гҒҢ60HzгҒ®ең°еҹҹгҒ®е ҙеҗҲгҒҜ1з§’й–“гҒ«120еӣһзӮ№ж»…гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒҢгҖҒжҷ®йҖҡгҒҜгғҒгғ©гғ„гӮӯгӮ’ж„ҹгҒҳгҒӘгҒ„гҖӮ
е…үгҒ®зӮ№ж»…гҒ гҒ‘гҒ§гҒӘгҒҸгҖҒеӢ•з”»гҒ§гҒӮгӮҢгҒ°жҳ з”»гҒ®гғ•гӮЈгғ«гғ жҳ еғҸгӮ„гғҶгғ¬гғ“жҳ еғҸгҒҢжң¬еҪ“гҒҜйқҷжӯўз”»гӮ’гӮігғһйҖҒгӮҠгҒ—гҒҹгӮӮгҒ®(гғҶгғ¬гғ“гҒ®е ҙеҗҲгҖҒ1з§’й–“гҒ«30гӮігғһйҖҒгӮҠгҒ®йқҷжӯўз”»гҒ®еҲҮгӮҠжӣҝгҒҲ)гҒ§гҒӮгҒЈгҒҰгӮӮйҖЈз¶ҡгҒ—гҒҹеӢ•з”»гҒЁгҒ—гҒҰиҰӢгӮүгӮҢгҒҹгӮҠгҖҒгӮўгғӢгғЎгғјгӮ·гғ§гғігӮӮеҗҢж§ҳгҒ«еӢ•з”»гҒЁгҒ—гҒҰиҰӢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®зҸҫиұЎгӮ’д»®зҸҫйҒӢеӢ•гҒЁгҒ„гҒҶгҖӮ
гҖҺж„ҸиӯҳгҒ®гҒӘгҒӢгҒ®жҷӮй–“гҖҸгҖҖгӮЁгғ«гғігӮ№гғҲгғ»гғҡгғғгғҡгғ«
гҖҺз”ҹзү©гҒӢгӮүиҰӢгҒҹдё–з•ҢгҖҸгҖҖгғҰгӮҜгӮ№гӮӯгғҘгғ«
SatiпјҲж°—гҒҘгҒҚпјүгҒҢеҲҮгӮҢгҒҰгҒӘгҒ„гҖҒз¶ҡгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒҜгҖҒгҒ©гҒҶгҒ„гҒҶзҠ¶ж…ӢгҒӢпјҹ
пј‘гҖҖжӢҚеӢ•гҒ®еҚҳдҪҚгҖӮдёҖз§’гҒ«дёҖеӣһпјҲгҒІгҒЁгҒӨпјүгҒ®ж°—гҒҘгҒҚгҖҖе…Ҙй–Җгғ¬гғҷгғ«гҒ®зӣ®жЁҷ
пј’гҖҖпј”еҲҶгҒ®дёҖз§’гҒ®еҲ»гҒҝгҖӮгҖҖпјҲгӮ«гғӢгӮ«гӮөгғһгғјгғҮгӮЈгҒ®е§ӢгҒҫгӮҠпјүгҖҖдёӯзҙҡгғ¬гғҷгғ«гҒ®зӣ®жЁҷ
пј“гҖҖ10еҲҶгҒ®1з§’пҪһ20еҲҶгҒ®1з§’гҒЁгҒ„гҒҶгғ’гғҲгҒ®иӘҚиӯҳгҒ®гӮ·гӮ№гғҶгғ гҒ®йҷҗз•ҢгҖҖгғҙгӮЈгғ‘гғғгӮөгғҠгғјгғ¬гғҷгғ«
SamДҒdhiгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰ
SamДҒdhiгҒЁдә‘гҒҶиЁҖи‘үгҒҜгҖҒгӮӨгғігғүгҒ®е®—ж•ҷзҡ„дјқзөұгҒ§гҒҜгҖҒгҖҢгӮөгғһгғјгғҮгӮЈгҒ®еўғең°гҖҚгҒЁгҒӢгҖҢгҖҮгҖҮгӮөгғһгғјгғҮгӮЈгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶйўЁгҒ«гҖҒж„ҸиӯҳгҒ®зҠ¶ж…ӢпјҲstateпјүгҒЁдә‘гҒҶж„Ҹе‘ігҒ§дҪҝгӮҸгӮҢгӮӢгҖӮ
гғҶгғјгғ©гғҜгғјгғҖд»Ҹж•ҷгҒ§гҒҜгҖҒгҖҢеҪјгҒ«гҒҜгҖҒгӮөгғһгғјгғҮгӮЈгҒҢжңүгӮӢ/з„ЎгҒ„гҖҚгҒЁгҒӢгҖҢйӣҶдёӯеҠӣпјҲйӣҶдёӯгҒҷгӮӢиғҪеҠӣпјүгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶйўЁгҒ«гҖҒдёҖгҒӨгҒ®еҝғгҒ®иғҪеҠӣгҒЁгҒӢж©ҹиғҪгҒЁгҒ—гҒҰдҪҝз”ЁгҒ•гӮҢгӮӢгҖӮ
гҒ“гҒ®йҒ•гҒ„гҒ«гҒҜжіЁж„ҸгҒҢеҝ…иҰҒгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
д»ҠгҖҒгҒ“гҒ“гҒ§гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒҜгҖҒгғҶгғјгғ©гғҜгғјгғҖзҡ„гҒӘж„Ҹе‘ігҒ§гҒ®SamДҒdhiгҖҒгӮәгғјгғ гҒЁгҒӢгғ•гӮ©гғјгӮ«гӮ№гҒЁгҒӢгҒҷгӮӢеҝғгҒ®иғҪеҠӣгғ»ж©ҹиғҪгҒ®гҒ“гҒЁгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
SamДҒdhiпјҲз©әй–“еҲҶи§ЈиғҪпјүгӮәгғјгғ гғ»гғ•гӮ©гғјгӮ«гӮ№гҖҖиҰ–еҠӣгҒ®иүҜгҒ•гҖҖжңӣйҒ гғ¬гғігӮә
в—Ҹ SamДҒdhiгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒ®и§ЈиӘ¬
ең°ж©ӢиӢұеӨ« зһ‘жғігӮЁгғғгӮ»гӮӨ
гӮөгғһгғјгғҮгӮЈгҒ«гҒҜгҖҒгҒқгӮҢгҒ«д»ҳйҡҸгҒҷгӮӢпјҲдјҙгҒҶпјүж„ҸиӯҳзөҢйЁ“гҒҢгҒӮгӮӢгҖӮ
гғ»е…үгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢж„ҹеҸ—жҖ§гҒҢеў—гҒҷпјҲгҒӘгҒңгҒӢгҖҒе…үгҒҢгҒЁгҒҰгӮӮз¶әйә—гҒ«иҰӢгҒҲгӮӢпјү
гғ»йҹігҒ«еҜҫгҒҷгӮӢж„ҹеҸ—жҖ§гҒ®еӨүеҢ–пјҲйқҷгҒӢгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҒ®гҒ«гҖҒгҒӘгҒңгҒҢдё–з•ҢгҒҢйқҷгҒҫгӮҠгҒӢгҒҲгҒЈгҒҹгӮҲгҒҶгҒ«ж„ҹгҒҳгӮӢгҖҒйҹігҒЁйҹігҒ®еҗҲй–“гҒ®жІҲй»ҷгҒ«ж„ҸиӯҳгҒ®з„ҰзӮ№гҒҢгҒӮгҒҶж„ҹгҒҳгҒ«гҒӘгӮӢпјү
гғ»жҷӮй–“гҒ®жөҒгӮҢгҒҢгӮҶгҒЈгҒҸгӮҠгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгӮҲгҒҶгҒӘж„ҹгҒҳгҒӢгӮүе§ӢгҒҫгӮҠгҖҒжңҖзөӮзҡ„гҒ«гҒҜжҷӮй–“гҒҢжӯўгҒҫгҒЈгҒҹгӮҲгҒҶгҒӘж„ҹгҒҳгғ»жҷӮй–“ж„ҹиҰҡгҒҢж¶ҲеӨұгҒҷгӮӢгҖӮ
гҒқгҒ—гҒҰгҖҒж°ёйҒ гҒ®дёҖзһ¬пјҲAn eternal momentгҖҒEternal NowпјүгҖҢиҹ»еӢ•гҒ„гҒҰеӨӘеҸӨгҒ®еҰӮгҒ—гҖҚгҒЁдә‘гҒҶж„ҹгҒҳгҒ«гҒӘгӮӢгҖӮ
гғ»зІҫзҘһзҡ„гҒӘеҝ«ж„ҹгӮ’дјҙгҒҶпјҲе–ңгғ»жҘҪпјү
SamДҒdhiпјҲе®ҡгғ»дёүжҳ§пјүпјқзӯүжҢҒпјҲжҷӮй–“и»ёгҒ§гҒ®гғўгғҮгғ«пјүгҖҒжӯЈеҸ—/дёҚеҸ—гҖҒйҸЎгҒ®е–©гҒҲпјҲз©әй–“зҡ„гғўгғҮгғ«пјү
гғ»еҢ…жӢ¬зҡ„гҒӘж„ҸиӯҳпјҲInclusiveпјүй–ӢгҒ„гҒҹж°—гҒҘгҒҚгҒЁжҺ’йҷӨзҡ„йӣҶдёӯпјҲExclusiveпјү
еүҚиҖ…гҒҜе…ЁдҪ“зҡ„гҒӘгҖҒеҒҸгӮүгҒӘгҒ„ж–№еҗ‘жҖ§гӮ’жҢҒгҒЎгҖҒеҫҢиҖ…гҒҜйҷҗе®ҡгҒ•гӮҢгҒҹгҖҒзӢӯгҒ„зҜ„еӣІгҒёгҒ®ж–№еҗ‘жҖ§гӮ’жҢҒгҒӨгҖӮе®ҹйҡӣгҒ®ж„ҸиӯҳгҒҜгҒ“гӮҢгӮүгҒҢйҒ©еҪ“гҒ«ж··еҗҲгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢзҠ¶ж…ӢгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
гғ»з„ЎеҝғгҖҒз©әгҒЈгҒҪгҒ®еҝғгҖҒж„ҸиӯҳгҒ®з©әзҷҪгӮ’иӘҚгӮҒгӮӢгҒӢиӘҚгӮҒгҒӘгҒ„гҒӢ
гғ»зӮ№гҒ®йҖЈз¶ҡгҒЁгҒ—гҒҰгҒ®з·ҡгҖҒгҒ„гҒҫпјқж°ёйҒ пјқз„ЎжҷӮй–“гҖҒж°ёйҒ гҒ®гҒ„гҒҫ
дё»е®ўеҲҶйӣўвҶ’дё»е®ўжңӘеҲҶвҶ’еҲҶйӣў
зөҢйЁ“гҒҷгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒҜдәӢе®ҹпҪңе…¶е„ҳпјҲгҒқгҒ®гҒҫгҒҫпјүгҒ«зҹҘгӮӢгҒ®ж„ҸгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
е…ЁгҒҸиҮӘе·ұгҒ®зҙ°е·ҘгӮ’жЈ„гҒҰгҒҰгҖҒдәӢе®ҹгҒ«еҫ“гҒҶгҒҰзҹҘгӮӢгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
зҙ”зІӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒҜгҖҒжҷ®йҖҡгҒ«зөҢйЁ“гҒЁгҒ„гҒЈгҒҰгҒ„гӮӢиҖ…гӮӮгҒқгҒ®е®ҹгҒҜдҪ•гӮүгҒӢгҒ®жҖқжғігӮ’дәӨгҒҲгҒҰгҒ„гӮӢгҒӢгӮүгҖҒжҜ«пјҲгҒ”гҒҶпјүгӮӮжҖқж…®еҲҶеҲҘгӮ’еҠ гҒҲгҒӘгҒ„гҖҒзңҹгҒ«зөҢйЁ“е…¶е„ҳгҒ®зҠ¶ж…ӢгӮ’гҒ„гҒҶгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒҹгҒЁгҒҲгҒ°гҖҒиүІгӮ’иҰӢгҖҒйҹігӮ’иҒһгҒҸеҲ№йӮЈпјҲгҒӣгҒӨгҒӘпјүгҖҒжңӘгҒ гҒ“гӮҢгҒҢеӨ–зү©гҒ®дҪңз”ЁгҒ§гҒӮгӮӢгҒЁгҒӢгҖҒжҲ‘гҒҢгҒ“гӮҢгӮ’ж„ҹгҒҳгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒӢгҒ„гҒҶгӮҲгҒҶгҒӘиҖғгҒ®гҒӘгҒ„гҒ®гҒҝгҒӘгӮүгҒҡгҖҒгҒ“гҒ®иүІгҖҒгҒ“гҒ®йҹігҒҜдҪ•гҒ§гҒӮгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶеҲӨж–ӯгҒҷгӮүеҠ гӮҸгӮүгҒӘгҒ„еүҚгӮ’гҒ„гҒҶгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
гҒқгӮҢгҒ§зҙ”зІӢзөҢйЁ“гҒҜзӣҙжҺҘзөҢйЁ“гҒЁеҗҢдёҖгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮиҮӘе·ұгҒ®ж„ҸиӯҳзҠ¶ж…ӢгӮ’зӣҙдёӢгҒ«зөҢйЁ“гҒ—гҒҹжҷӮгҖҒжңӘгҒ дё»гӮӮгҒӘгҒҸе®ўгӮӮгҒӘгҒ„гҖҒзҹҘиӯҳгҒЁгҒқгҒ®еҜҫиұЎгҒЁгҒҢе…ЁгҒҸеҗҲдёҖгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгҒҢзөҢйЁ“гҒ®жңҖйҶҮгҒӘгӮӢиҖ…гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
гҖҺе–„гҒ®з ”究гҖҸиҘҝз”° е№ҫеӨҡйғҺ
иҰӢгҒҹгӮҠиҒһгҒ„гҒҹгӮҠгҒҷгӮӢе…ЁгҒҰгҖҒеҲӨж–ӯгҒҢгҒҫгҒ иЎҢгӮҸгӮҢгӮӢеүҚгҒҜгҖҒгҒҫгҒ з§ҒгҒҜеӯҳеңЁгҒӣгҒҡгҖҒдё»дҪ“гӮӮе®ўдҪ“гӮӮз„ЎгҒҸгҒҹгҒ гҒқгӮҢгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒгҒқгӮҢгҒҢгҒқгӮҢгҒ«ж°—гҒҘгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒ„гҒҶзҠ¶ж…ӢгҒҢиө·гҒҚгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒеҲӨж–ӯгҒҢе…ҘгӮӢгҒЁгҖҒгҒқгӮҢгҒҜгӮҸгҒҹгҒ—гҒҢиҰӢгҒҹгӮҠиҒһгҒ„гҒҹгӮҠгҒ—гҒҹдҪ•гҒӢгҒЁгҒӘгӮҠеҲҶйӣўгҒҢиө·гҒҚгҖҒдё–з•ҢгҒҢзҸҫгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
иҰӢгӮӢгӮӮгҒ®гҒӘгҒҸгҒ—гҒҰиҰӢгҖҒиҒһгҒҸгӮӮгҒ®гҒӘгҒҸгҒ—гҒҰиҒһгҒҸгҖӮ
иӘҚиӯҳеҜҫиұЎгғ»иӘҚиӯҳдҪңз”Ёгғ»иӘҚиӯҳдё»дҪ“гҒ®дёүй …гҒ®еҙ©еЈҠгҖҒеҶҚз”ҹпјҲз”ҰгӮҠпјү
гӮҜгғӘгӮ·гғҘгғҠгғ гғ«гғҶгӮЈгҖҢеҲҶйӣўгҒӘгҒҚиҰіеҜҹгҖҚеҸӮз…§
гӮ«гғӢгӮ«гғ»гӮөгғһгғјгғҮгӮЈгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰ
Khaб№ҮikasamДҒdhiпјқзһ¬й–“е®ҡгғ»еҲ№йӮЈе®ҡпјқгғҙгӮЈгғ‘гғғгӮөгғҠгғјгғ»гӮөгғһгғјгғҮгӮЈ
гӮөгғһгғјгғҮгӮЈгҒ®еј·еҠӣгҒӘйӣҶдёӯгҒҢгӮөгғҶгӮЈпјҲж°—гҒҘгҒҚпјүгҒ®зІҫеәҰгҒЁйҖҹеәҰгӮ’зҹўгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«йӢӯгҒҸгҒ—гҖҒдёҖзһ¬дёҖзһ¬гҒ®дәӢиұЎгҒ«ж’ғгҒЎиҫјгҒҫгӮҢгҖҒгҒқгҒ®жң¬иіӘгӮ’жҡҙгҒҚеҮәгҒ—гҒҰгҒ„гҒҸ…гҖӮ
еҝғгҒ«е…ҘгҒЈгҒҰгҒҸгӮӢгҒҷгҒ№гҒҰгҒ®еҜҫиұЎгӮ’е…¬е№ігҒ«гҖҒзӯүгҒ—гҒ„и·қйӣўгӮ’гӮӮгҒЈгҒҰзңәгӮҒгҖҒз„Ўе·®еҲҘе№ізӯүгҒ®зІҫзҘһгҒ«иІ«гҒӢгӮҢгҒҹжҳҺзўәгҒӘз„Ўй–ўеҝғгҒ®зҠ¶ж…ӢгӮ’дҝқгҒӨгҖӮ
гҖҺгғ–гғғгғҖгҒ®зһ‘жғіжі•гҖҸең°ж©Ӣз§Җйӣ„
SatiгҒЁSamДҒdhiгҒ®гғҗгғ©гғігӮ№гҒ®иүҜгҒ„гҒӢгҒ‘еҗҲгӮҸгҒӣгғ»жҲҗй•·
гғ»жңӣйҒ гғ¬гғігӮәд»ҳгҒҚй«ҳйҖҹеәҰж’®еҪұгӮ«гғЎгғ©гҒЁгҒ„гҒҶе–©гҒҲ
гғ»иһҚеҗҲгғўгғҮгғ«гҒЁжҳ з”»гғўгғҮгғ«
гғ»иҮӘ然主зҫ©пјҲиһҚеҗҲжҖқжғіпјүгҒЁеҸҚиҮӘ然主зҫ©гҖҖгҖҢгҒІгҒЁгҒӨгҒ«гҒӘгӮӢгҖҚгҒЁгҖҢйӣўгӮҢгҒҰиҰігӮӢгҖҚ
гғ»иҰіз…§иҖ…ж„ҸиӯҳгҒЁгҖҒиҰіз…§иҖ…гҒ®дёҚеңЁпјҲгҖҢйӣўгӮҢгҒҰиҰігӮӢгҖҚгҒЁгҖҢгҒқгҒ®гӮӮгҒ®гҒ«гҒӘгӮҠеҲҮгӮӢгҖҚ
д»ҘдёӢгҒ®дёүгҒӨгҒ®иҰҒзҙ гҒ®зө„гҒҝеҗҲгӮҸгҒӣгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰжҲҗгӮҠз«ӢгҒӨгҖӮ
1гҖҒгҖҢеҝғдёҖеўғжҖ§гҖҚгҒЁгҒ„гҒҶиҰҒзҙ гҖӮSamДҒdhi
е№ігҒҹгҒҸиЁҖгҒҲгҒ°гҖҒдё»е®ўжңӘеҲҶгҖҒе®Ңе…ЁгҒӘеҜҫиұЎгҒЁгҒ®иһҚеҗҲгҖҒи„ұиҗҪгҖҒиҰӢгӮӢгӮӮгҒ®гҒӘгҒҸгҒ—гҒҰгҒ®иҰіеҜҹгҖҒиҰӢгӮүгӮҢгӮӢеҜҫиұЎгҒ гҒ‘гҒ®зӢ¬еңЁгҖҒгҒӘгҒ©гҒЁгҒ„гӮҸгӮҢгӮӢж„ҸиӯҳзҠ¶ж…ӢгҖӮ
гҒқгӮҢгҒҢиө·гҒ“гҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒӢгҒ©гҒҶгҒӢпјҹ
гҖҢе…Ёйқўзҡ„гҒӘиҰіеҜҹгҖҚгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒгҒқгҒ®зһ¬й–“гҒ®гҒқгҒ®еҜҫиұЎгҒ гҒ‘гҒҢе…Ёе®Үе®ҷгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҒқгҒ®з”ҹиө·гҒ®зһ¬й–“гҖҒе®Үе®ҷй–Ӣй—ўгҒ—гҖҒгҒқгҒ®ж¶Ҳж»…гҒ®зһ¬й–“гҖҒе®Үе®ҷж»…е°ҪгҒҷгҖҒгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹж„ҹгҒҳгҒ«гҒӘгӮӢгҖӮ
гҒқгӮҢгӮ’иҰӢгҒҰгҒ„гӮӢгҖҢиҮӘеҲҶгҖҚгҒЁдә‘гҒҶж„ҹиҰҡгӮӮгҖҒгҖҢзө¶еҜҫзҡ„иҰіз…§иҖ…гҖҒи¶…еҖӢзҡ„иҰіеҜҹиҖ…гҒҢгҒ„гӮӢгҖҚгҒЁдә‘гҒЈгҒҹж„ҹиҰҡгӮӮгҖҒгҒҫгҒЈгҒҹгҒҸгҒӘгҒ„гҖӮ
гҒқгҒ®гҒ“гҒЁгҒҢгҖҒдёҖгҒӨдёҖгҒӨгҒ®еҶ…еӨ–гҒ®зҹҘиҰҡеҜҫиұЎвҖ•дә”ж„ҹгҒӢгӮүгҒ®ж„ҹиҰҡзҹҘиҰҡеҲәжҝҖгҖҒжҖқиҖғгҖҒгӮӨгғЎвҖ•гӮёгҖҒж„ҹжғ…гҖҒж¬ІжұӮвҖ•гҒЁгҒ®гҒӮгҒ„гҒ гҒ§гҖҒгӮҖгӮүгҒӘгҒҸгҖҒз„Ўе·®еҲҘзҡ„гҒ«иө·гҒ“гҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒӢгҒ©гҒҶгҒӢпјҹ
2гҖҒиҰіеҜҹгҒ®гӮ№гғ”гғјгғүгғ»еӢ•дҪ“иҰ–еҠӣгҖӮSati
дёҖз§’гҒ«дёҖеҖӢгҒ®еҜҫиұЎгҒЁиһҚеҗҲгҒ—и„ұиҗҪгӮ’иө·гҒ“гҒ—гҒҰгҒ„гҒҰгӮӮгҖҒгӮ«гғӢгӮ«гғ»гӮөгғһгғјгғҮгӮЈгҒЁгҒҜиЁҖгҒҲгҒӘгҒ„гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮгҒӘгҒңгҒӘгӮүгҖҒдёҖз§’й–“гӮӮжҢҒз¶ҡгҒҷгӮӢзҹҘиҰҡеҜҫиұЎгҒҜпјҲжҲ‘гҖ…дәәй–“гҒ®зҹҘиҰҡгӮ·гӮ№гғҶгғ дёҠпјүеӯҳеңЁгҒ—гҒӘгҒ„гҒҜгҒҡгҒ гҒӢгӮүгҒ§гҒҷгҖӮ
гҖҢж„ҸиӯҳгҒ®гҒӘгҒӢгҒ®жҷӮй–“гҖҚEгғ»гғҡгғғгғҡгғ«гҖҖпјҲеІ©жіўжӣёеә—пјү
гғҰгӮҜгӮ№гӮӯгғҘгғ«гҒ®гҖҢз”ҹзү©гҒӢгӮүиҰӢгҒҹдё–з•ҢгҖҚгҒ®з¬¬дёүз« гҖҢзҹҘиҰҡжҷӮй–“гҖҚгӮ’еҸӮз…§
дәәй–“гҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгҒ“гӮҢд»ҘдёҠеҲҶеүІгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„вҖңзһ¬й–“вҖқгҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒҢгҒӮгӮӢгҖӮ
гҒқгӮҢгҒҜгҖҒгҒ гҒ„гҒҹгҒ„20еҲҶгҒ®1з§’гҒҗгӮүгҒ„гҒ®еҚҳдҪҚгҒ§гҒӮгӮӢгҖҒгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮ
пјҲж„ҹиҰҡеҷЁе®ҳгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰе°‘гҒ—йҒ•гҒҶгҒ®гҒ гҒқгҒҶгҒ§гҒҷгҒҢпјү
гҒ“гҒ®гҖҢ20еҲҶгҒ®1з§’гҖҚгҒЁгҒ„гҒҶеҚҳдҪҚгҒҜгҖҒгӮ«гғӢгӮ«гғ»гӮөгғһгғјгғҮгӮЈгҒ®жҷӮй–“зҡ„йҷҗз•ҢгҒҢгҖҒеӨҡеҲҶ20еҲҶгҒ®1з§’гҒҸгӮүгҒ„гҒ®жүҖгҒ«гҒӮгӮӢгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢгҖҒгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ«гӮӮз¬ҰеҗҲгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гӮ«гғӢгӮ«гғ»гӮөгғһгғјгғҮгӮЈгҒЁиЁҖгҒҲгӮӢгҒ«гҒҜгҖҒе°‘гҒӘгҒҸгҒЁгӮӮдёҖз§’й–“гҒ«дә”гҒӨгҒӢгӮүеҚҒгҖҒгҒӮгӮӢгҒ„гҒҜгҒқгӮҢд»ҘдёҠгҒ®ж•°гҒ®еҜҫиұЎгҒЁгҒ®иһҚеҗҲгғ»йӣўи„ұгӮ’з№°гӮҠиҝ”гҒ—гҒҰгҒ„гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҖҒгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮ
гҖҢдёҖз§’гҒ«дёҖеҖӢгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶе ҙеҗҲгҖҒгҒҠгҒқгӮүгҒҸгҒҜиҰіеҜҹзңјгҒҢгғ”гғігҒјгҒ‘гҒ§гҖҒеӨҡгҒҸгҒ®зү©гӮ’иҰӢйҖғгҒ—гҒҰгӮӢпјҲзөҢйЁ“гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒ«ж°—гҒҘгҒ„гҒҰгҒӘгҒ„гҖҒз„ЎиҮӘиҰҡзҡ„гҒ«зөҢйЁ“гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢпјҲгҒ—гҒӢгҒ—еҪ“然еҪұйҹҝгҒҜеҸ—гҒ‘гҒҰгҒ„гӮӢгҒҜгҒҡпјүпјүгҒӢгҖҒ
гҒӮгӮӢгҒ„гҒҜзҹҘиҰҡзөҢйЁ“гҒ®зӣҙеҫҢгҒ«иҖғгҒҲдәӢгӮ’гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢпјҲеҫ®еҰҷгҒӘд»•ж–№гҒ§гҒқгҒ®зөҢйЁ“гӮ’е‘ігӮҸгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒӢгҖҒгҖҢгӮ„гҒЈгҒҹгғјгҖҒгҒӨгҒ„гҒ«вҖңгҒқгӮҢвҖқгҒҢиө·гҒ“гҒЈгҒҹгғјгҖҚгҒӘгҒ©гҒЁиЁҳжҶ¶гҒЁз…§еҗҲгҒ—гҒӨгҒӨиҖғгҒҲгҒҰгҒ„гӮӢгҒӢгҖҒ
гҒ©гҒЎгӮүгҒ«гҒ—гҒҰгӮӮзҸҫе®ҹз”ҹиө·гҒ«зңјгӮ’зһ‘гҒЈгҒҰгҒ„гӮӢпјүгҒӢгҒ®гҒ©гҒЎгӮүгҒӢгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢгҒЁз–‘гӮҸгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ®е ҙйқўгҒ§гҒ“гҒқгҖҢгғ©гғҷгғӘгғігӮ°гҖҚгҒЁгҒ„гҒҶиЈңеҠ©зҡ„жҠҖжі•гҒ®жңүеҠ№жҖ§гҒҢе®ҹж„ҹгҒ•гӮҢгӮӢгҒҜгҒҡгҒ§гҒҷгҖӮ
3гҖҒжҢҒз¶ҡжҷӮй–“пјҲжҢҒз¶ҡеҠӣпјү
еҚҳзҙ”иЁҲз®—гҒ§гҖҒдёҖз§’й–“гҒ«10еҖӢгҒ®гғҡгғјгӮ№гҒ®гӮөгғҶгӮЈгҒҢгҖҒ10з§’з¶ҡгҒ‘гҒ°100еҖӢгҖҒ60з§’з¶ҡгҒ‘гҒ°600еҖӢгҒ®гҖҢиҮӘжҖ§=жі•гҖҚгҒ®иҰіеҜҹгҒҢиЎҢгӮҸгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҢгӮ«гғӢгӮ«гғ»гӮөгғһгғјгғҮгӮЈгҒҢиө·гҒ“гҒЈгҒҹгҖӮгҒ§гӮӮгҖҒгҒқгӮҢгҒҜ0гҖҒ2з§’гҒ—гҒӢз¶ҡгҒӢгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒ§гҒҜгҖҒгҒқгӮҢгҒҜгӮ«гғӢгӮ«гғ»гӮөгғһгғјгғҮгӮЈгҒЁгҒҜе‘јгҒ№гҒӘгҒ„гҒ®гҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгҒ“гҒ®з¬¬дёүгҒ®иҰҒзҙ гҒҜгҖҒ第дёҖгҖҒ第дәҢгҒ®иҰҒзҙ гҒ«жҜ”гҒ№гҒҹгӮүйҮҚиҰҒгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒ®гҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гҒҹгҒЁгҒҲгҖҒгҒқгӮҢгҒҢдёүз§’й–“гҒ®гӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгҒЈгҒҰгӮӮгҖҒе®Ңе…ЁгҒӘеҝғдёҖеўғжҖ§пјҲеҜҫиұЎгҒЁгҒ®иһҚеҗҲпјүгҒЁгҖҒз ”гҒҺжҫ„гҒҫгҒ•гӮҢгҒҹеӢ•дҪ“иҰ–еҠӣгғ»иҰіеҜҹзңјпјҲзһ¬й–“зһ¬й–“гҒ®йӣўи„ұпјүгӮ’гӮӮгҒЈгҒҰгҒ®гҖҢиҰігҖҚгҒ§гҒӮгӮҢгҒ°е……еҲҶиЎқж’ғзҡ„гҒ§гҒӮгӮҚгҒҶгҖҒгҒЁиҖғгҒҲгӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ®дёүгҒӨгҒ®жқЎд»¶гӮ’е®Ңз’§гҒ«жәҖгҒҹгҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гӮ’гҖҢзһ¬й–“е®ҡгҖҚгҒЁе‘јгҒ¶гҒЁгҒҷгӮӢгҒӘгӮүгҒ°гҖҒз§ҒгҒҜжңӘгҒ гҖҒгҒқгҒ®зөҢйЁ“гҒҜгҒ—гҒҰгҒҠгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гҒӘгӮ“гҒЁгҒӘгҒҸгҒҶгҒЈгҒҷгӮүгҒЁгҖҒгҖҢзўәгҒӢгҒ«гҒ“гҒ®и©ұгҖҒеҳҳгҒ§гҒҜгҒӘгҒ•гҒқгҒҶгҒ гҖҚгҒЁж„ҹгҒҳгҒҰгҒ„гӮӢзЁӢеәҰвҖ• гҒҫгҒӮгҖҒгҒӣгҒ„гҒңгҒ„гҖҢзһ¬й–“е®ҡгҒЈгҒҪгҒ„гҖҚзҠ¶ж…ӢгӮ’гғҒгғ§гғӯгҒЈгҒЁзөҢйЁ“гҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮӢгҖҒгҒЁгҒ„гҒҶзЁӢеәҰгҒ§гҒҷгҖӮ
е®ҡеҠӣгҒҢгҒ„гҒҫдёҖгҒӨгҒ§гҖҒгӮөгғҶгӮЈгҒ®й«ҳйҖҹеҢ–гҒҢйҖЈз¶ҡгҒ—гҒҰиө·гҒҚгҒӘгҒ„гҖҒгҒЁгҒ„гҒҶе®ҡеҠӣдёҚи¶ігҒ®е•ҸйЎҢгҒ§гҒҷгҖӮ
гҖҢгғҙгӮЈгғ‘гғғгӮөгғҠгғјгҒ«дёҖзӮ№йӣҶдёӯеҠӣпјҲSamДҒdhiпјүгҒҜеҝ…иҰҒгҒӘгҒ„гҖҒжӢЎж•ЈжҖ§гҒ®ж°—гҒҘгҒҚпјҲSatiпјүгҒҢгҒӮгӮҢгҒ°е……еҲҶгҒ гҖҚгҒЁгҒҜгҖҒгӮҲгҒҸдә‘гӮҸгӮҢгӮӢи©ұгҒ§гҒҷгҒҢгҖҒжң¬ж јзҡ„гҒ«гӮ„гӮҚгҒҶгҒЁгҒҷгӮӢгҒЁгҖҒгҒ©гҒ“гҒӢгҒ§е®ҡеҠӣдёҚи¶ігҒ®е•ҸйЎҢгҒ«и¶ігӮ’еј•гҒЈејөгӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒқгҒ—гҒҰгҖҒгҒ©гҒҶгҒ—гҒҰе®ҡеҠӣгҒҢгҒӘгҒ„гҒ®гҒӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгӮ’иҖғгҒҲгӮӢгҒӘгӮүгҖҒгӮӮгҒЈгҒЁж №гҒЈгҒ“гҒ«жҪңгӮҖгҖҒгӮҲгӮҠжң¬иіӘзҡ„гҒӘйҡңе®іиҰҒеӣ гҒ«жҖқгҒ„иҮігӮүгҒӘгҒҸгҒҰгҒҜгҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҒ®гҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гӮ№гғӘгғ©гғігӮ«гӮ·гӮ№гғҶгғ гҒҜжңҖзөӮзҡ„гҒ«гҖҒгӮҜгғӘгӮ·гғҘгғҠгғ гғ«гғҶгӮЈгҒ®и©ұгҒЁгҒ»гҒЁгӮ“гҒ©иҰӢеҲҶгҒ‘гҒҢгҒӨгҒӢгҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҒӘз„ЎдҪңзӮәгҖҒз„ЎйҒёжҠһгҖҒз„Ўйҷҗе®ҡгҒ®зө¶еҜҫеҸ—еӢ•зҡ„иҰіеҜҹпјҲгғ©гғҷгғӘгғігӮ°гӮӮдёӯеҝғеҜҫиұЎгӮӮгҒӘгҒ—гҖҒгӮөгғҶгӮЈгҒҷгӮүгҒ—гҒӘгҒ„пјүгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹжүҖгҒҫгҒ§иҮігӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒқгҒҶгҒӘгӮӢгҒЁгҖҒгғҙгӮЈгғ‘гғғгӮөгғҠгғјгҒЁдә‘гҒҶгӮӮгҒ®иҮӘдҪ“гҒ«еҜҫгҒҷгӮӢгӮӨгғЎгғјгӮёгҒҢеӨүгӮҸгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҹгҒ йҒ•гҒҶгҒ®гҒҜгҖҒгҒқгҒ®гҖҢз„ЎжҠҖжі•гҖҚгҒ«иҮігӮӢгҒҫгҒ§гҒ«гҖҒжҠҖжі•гӮ’е°ҪгҒҸгҒ—гҒҰгҒ®гҖҒж®өйҡҺзҡ„гҒӘгҖҒдҪ“зі»гҒ гҒЈгҒҹеҹәзӨҺиЁ“з·ҙгҒҢз”Ёж„ҸгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒ„гҒҶзӮ№гҒ§гҒҷгҖӮ
гҖҢжҠҖжі•гӮ’е°ҪгҒҸгҒ—гҒҹеҫҢгҖҒз„ЎжҠҖжі•гҒ«иҮігӮӢгҖҚгҖҢдәәдәӢгӮ’е°ҪгҒҸгҒ—гҒҰеӨ©е‘ҪгӮ’еҫ…гҒӨгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶж–№гҒҢзҸҫе®ҹзҡ„гҖҒе®ҹзҸҫеҸҜиғҪгҒӘгӮӮгҒ®гҒ«ж„ҹгҒҳгӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ®гҒёгӮ“гҒ®и©ұгҒҜгҖҒзөҗеұҖгҖҒж¶Ҳж»…жҷәгҒ гҖҒеЈҠж»…жҷәгҒ гҖҒгҒЁгҒ„гҒҶи©ұгӮ’е®ҹйҡӣгҒ«зөҢйЁ“гҒ—гҒҰгҒҝгҒӘгҒ„йҷҗгӮҠгҖҒдҪ•гҒЁгӮӮиЁҖгҒҲгҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгҖӮ
гҒҠгҒқгӮүгҒҸгҖҒеҺҹе§Ӣд»Ҹж•ҷгҒ®дҪҝз”Ёжі•гҒ§гҒ®гҖҢз„ЎеёёгҖҒз„ЎжҲ‘гҖҒиӢҰгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶиЁҖи‘үгҒҜгҖҒжҲ‘гҖ…гҒҢжҷ®йҖҡгҒ«зҗҶи§ЈгҒ—дҪҝгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгӮҲгҒҶгҒӘгӮӮгҒ®гҒЁгҒҜе…ЁгҒҸз•°гҒӘгҒЈгҒҹж„Ҹе‘ігҒӘгҒ®гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
гҒқгҒ®зӣҙжҺҘзөҢйЁ“гҒӘгҒ—гҒ«гҖҒгҖҢдёҖеҲҮзҡҶиӢҰи«–гҒҜгҒҠгҒӢгҒ—гҒ„гҖҒеҺӯдё–зҡ„гҒ§жӯӘгӮ“гҒ гғўгғҺгҒ®иҰӢж–№гҒ гҖҚгҒӘгҒ©гҒЁиЁҖгҒЈгҒҰгҒҝгҒҹгҒЁгҒ“гӮҚгҒ§д»•ж–№гҒҢгҒӘгҒ„гҖӮ
гҒӨгҒҫгӮӢгҒЁгҒ“гӮҚгҖҒгғҙгӮЈгғ‘гғғгӮөгғҠгғјгҒҜйЎ•еҫ®йҸЎдёӢгҒ®дё–з•ҢгҒ®и©ұгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҒқгҒ®йЎ•еҫ®йҸЎгӮ’иҰ—гҒ„гҒҹгҒ“гҒЁгҒ®гҒӘгҒ„дәәй–“гҒҢдҪ•гӮ’иЁҖгҒЈгҒҰгӮӮд»•ж–№гҒҢгҒӘгҒ„гҖҒгҒЁгҒҜж„ҹгҒҳгҒҫгҒҷгҖӮ
зңјгҒ®еүҚгҒ«гҒӮгӮӢзҙҷгӮ’иӮүзңјгҒ§иҰӢгӮҢгҒ°гҒӨгӮӢгҒӨгӮӢгҒ гҒ—гҖҒи§ҰгӮҢгҒ°гҒҷгҒ№гҒҷгҒ№гҒ гҒ—гҖӮ
гҒ§гӮӮгҖҒ100еҖҚзҺҮгҒ®йЎ•еҫ®йҸЎгҒ§иҰ—гҒ‘гҒ°гҖҒгҒ§гҒ“гҒјгҒ“гҒ§з©ҙгҒ гӮүгҒ‘гҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒӘгҒ„гҖӮ
гҒ©гҒЈгҒЎгҒҢгҖҢгҒӮгӮӢгҒҢгҒҫгҒҫгҖҚгҒ®зңҹе®ҹгҒ§гҖҒгҒ©гҒЈгҒЎгҒҢеҰ„жғігҒӢгҒЁгҒ„гҒҶе•ҸйЎҢгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
иӮүзңјгҒ§иҰӢгӮҢгҒ°гҖҒгҒӨгӮӢгҒӨгӮӢгҒ«иҰӢгҒҲгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒҠгҒӢгҒ—гҒ„гҒ—гҖҒйЎ•еҫ®йҸЎгҒ§иҰ—гҒ‘гҒ°гҖҒгҒ§гҒ“гҒјгҒ“гҒ®з©ҙгҒ гӮүгҒ‘гҒ«иҰӢгҒҲгӮӢгҒ®гҒҢеҪ“然гҖӮ
гҒқгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘйҒ•гҒ„гҒ§гҒӮгӮӢгӮҲгҒҶгҒӘж°—гҒҢгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгҒҫгҒӮгҖҒжҲ‘гҖ…гҒЁгҒ—гҒҰгҒҜгҖҒеҲӨж–ӯдҝқз•ҷгҒ—гҒҰгҖҒиЁҖгӮҸгӮҢгҒҹйҖҡгӮҠгҒ«гҖҒгҒ—гҒӢгӮӮжү№еҲӨзҡ„зІҫзҘһгӮ’еғҚгҒӢгҒӣгҖҒдёҚзўәе®ҹгҒ•гҖҒгӮҸгҒӢгӮүгҒӘгҒ•гҒ«з•ҷгҒҫгӮҠгҒӨгҒӨгҖҒдҝ®иЎҢгӮ’з¶ҡгҒ‘гҒҰиЎҢгҒҸгҒ—гҒӢгҒӘгҒ„гҖӮ
з„Ўеёёгғ»иӢҰгғ»з„ЎжҲ‘пјҲгҒ®дёүзӣёпјүгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰ
иҮӘжҖ§пјқжі•пјҲдёҠеә§д»Ҹж•ҷзҡ„зҗҶи§Јпјү
жі•гҒҜз„ЎиҮӘжҖ§гҒ§гҒӮгӮӢгҖҒжі•з©әпјҲеӨ§д№—д»Ҹж•ҷзҡ„и§ЈйҮҲпјү
в—Ҹ еҺҹеӯҗд»Ҹж•ҷгҒ®е•ҸйЎҢиЁӯе®ҡпјҲеҺҹ-ж–ҮзҜҖпјү
з„ЎеёёпјқиӢҰпјҲдёҚеҝ«пјүпјқдёҚиҮӘз”ұпјҲз„ЎжҲ‘пјүпјқдёҚжө„пјҲе«ҢжӮӘпјүвҶ’еҺӯйӣўгҖҒжҚЁвҶ’жӮҹгӮҠ
гҒқгҒ“гҒ«гҒҜгҖҒSatiгҒ®иЁ“з·ҙгҒ«гӮҲгӮӢгҖҒжҷӮй–“ж„ҸиӯҳгҒ®еј·зғҲгҒ•пјҲжҷӮй–“зҡ„зҙ°еҲҶеҢ–пјүгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮпјҲдә”иҳҠзҡҶиӢҰпјү
гҖҢзёҒиө·гӮ’иҰӢгӮӢиҖ…гҒҜжі•гӮ’иҰӢгӮӢгҖӮжі•гӮ’иҰӢгӮӢиҖ…гҒҜзёҒиө·гӮ’иҰӢгӮӢгҖҚ
гҖҺгғһгғғгӮёгғһгғ»гғӢгӮ«гғјгғӨгҖҸ第28зөҢгҖҢиұЎи·Ўе–©еӨ§зөҢгҖҚпјҲгҖҺдёӯйҳҝеҗ«гҖҸгҖҢиұЎи·Ўе–©зөҢгҖҚеӨ§жӯЈи”ө1гҖҒеӣӣе…ӯдёғa)
в—Ҹ еӨ§д№—д»Ҹж•ҷгҒ®е•ҸйЎҢиЁӯе®ҡпјҲеҺҹ-ж–ҮзҜҖпјүгҖҒжӮҹгӮҠиҰі
еёёпјқжҘҪпјҲеҝ«пјү=иҮӘз”ұпјҲгҒ®ж„ҹиҰҡпјүпјқжё…жө„пјҲжё…гӮүгҒӢгҒ•пјүвҶ’жі•жӮҰ вҶ’ијӘе»»зҡ„з”ҹеӯҳпјҲгҒ®иӮҜе®ҡпјү
гҒқгҒ“гҒ«гҒҜгҖҒSamДҒdhiгҒ®й«ҳгҒҫгӮҠгҒ«гӮҲгӮӢгҖҒз„ЎжҷӮй–“зҡ„ж„ҹиҰҡгҒЁз©әй–“зҡ„иһҚеҗҲгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮпјҲдә”иҳҠзҡҶз©әпјү
иӢҰгҒӘгӮӢдё–з•ҢвҶ’еҰӮе®ҹзҹҘиҰӢвҶ’иӢҰ/жҘҪгҒ®и¶…и¶ҠпјҲз„ЎиҮӘжҖ§гғ»з©әгҒ®жҙһеҜҹпјүвҶ’зҸҫеңЁж¶…ж§ғпјҲеҪ“еҮҰеҚігҒЎи“®иҸҜеӣҪпјү
гҖҢиЎҶеӣ зёҒз”ҹпјҲеӣ зёҒжүҖз”ҹпјүгҒ®жі•гҖҒжҲ‘еҚігҒЎжҳҜгӮҢз„ЎпјҲз©әпјүгҒӘгӮҠгҒЁиӘ¬гҒҸгҖӮдәҰгҒҹжҳҜгӮҢд»®еҗҚгҒЁзӮәгҒҷгҖӮдәҰжҳҜгӮҢдёӯйҒ“гҒ®зҫ©гҒӘгӮҠгҖӮгҖҚ
пјҲгҒ©гӮ“гҒӘзёҒиө·гҒ®жі•гҒ§гӮӮгҖҒгҒқгӮҢгӮ’жҲ‘гҖ…гҒҜз©әгҒЁиӘ¬гҒҸгҖӮгҒқгӮҢгҒҜд»®гҒ«иЁӯгҒ‘гӮүгӮҢгҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгҒЈгҒҰгҖҒгҒқгӮҢгҒҜгҒҷгҒӘгӮҸгҒЎдёӯйҒ“гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮпјү
гҖҺдёӯи«–гҖҸ第24з« 18и©©
дә”иҳҠзҡҶиӢҰгҒЁдә”иҳҠзҡҶз©әвҖ•гғҶгғјгғ©гғҙгӮЎгғјгғҖгҒЁеӨ§д№—д»Ҹж•ҷ
гҖҢз©әгҒЁиӢҰгҖҚ
гҒӘгҒңгҖҒдёҖиҲ¬зҡ„гҒӘзһ‘жғіе®—ж•ҷгҒ§гҒҜгҖҒгҒӮгӮӢгҒҢгҒҫгҒҫгҒ®зҸҫе®ҹгӮ’иҰіеҜҹгҒ—гҒҹгҒЁгҒҚгҖҒгҖҢдә”иҳҠзҡҶз©әгҖҚвҖ•зҸҫиұЎгҒҜз©әгҒ§гҒӮгӮӢгҖҒгҒҷгҒ№гҒҰгҒҜз§ҒгҒ§гҒӮгӮӢгҖҒгҒЁгҒӘгӮӢгҒ®гҒ«гҖҒзңҹжҖ§гҒ®гғҙгӮЈгғ‘гғғгӮөгғҠгғјзһ‘жғігҒ§гҒҜгҖҢдә”иҳҠзҡҶиӢҰгҖҚвҖ•гҒӮгӮӢгҒҢгҒҫгҒҫгҒ®зҸҫе®ҹгҒҜгҖҢиӢҰпјҲгғүгӮҘгғғгӮ«пјүгҖҚгҒ§гҒӮгӮӢгҒЁгҒӘгӮӢгҒ®гҒӢгҖӮ
гҒ“гӮҢгҒҜгҖҒеҚҳгҒӘгӮӢиЁҖи‘үгӮ„ж–ҮеҢ–гҖҒжҷӮд»ЈгҒ®йҒ•гҒ„гҒ§иӘ¬жҳҺгҒ§гҒҚгӮӢгғ¬гғҷгғ«гҒ®е•ҸйЎҢгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒдҝ®иЎҢжі•гҖҒеҲ°йҒ”ең°зӮ№е…ЁдҪ“гҒ«й–ўгӮҸгӮӢж·ұеҲ»гҒӘгӮәгғ¬гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒйҮҚиҰҒгҒӘе•ҸйЎҢгҒ§гҒҷгҖӮ
зҗҶи«–гҒӘгҒҚиҰіеҜҹгӮ’гҒ—гҒҹгҒЁгҒҚгҖҒгҒӘгҒңдёҖж–№гҒҜгҖҢз©әгҖҚгҒ§гҖҒгӮӮгҒҶдёҖж–№гҒҜгҖҢиӢҰгҖҚгҒӘгҒ®гҒӢпјҹ
гғ»иҰӢгӮӢзӣ®гҒ®иЁ“з·ҙгҒ«гҖҒзҗҶи«–гҒҢеүҚжҸҗгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒӢгӮүпјҲиҰіеҜҹгҒ®зҗҶи«–иІ иҚ·жҖ§пјү
гғ»еӢ•дҪ“иҰ–еҠӣгҒ®йҒ•гҒ„пјҲжҷӮй–“еҲҶи§ЈиғҪгҒ®йҒ•гҒ„пјү
гғ»з©әй–“зҡ„иһҚеҗҲгҒЁжҷӮй–“зҡ„еҲҶи§Ј
гҒ§гҒҜгҖҒзҗҶи«–гӮ’йӣўгӮҢгҒҹгҖҢгҒӮгӮӢгҒҢгҒҫгҒҫгҖҚгҒЁгҒҜпјҹгҖҖгҒ©гҒЎгӮүгҒҢгҖҢгҒӮгӮӢгҒҢгҒҫгҒҫгҖҚгҒ«иҝ‘гҒ„гҒ®гҒӢпјҹ
гғ»гғ¬гғігғҲгӮІгғігҒЁMRIгҒ®е–©гҒҲ
гғ»зҙ°иғһгӮ’жҹ“гӮҒгӮӢгҒЁгҒҚгҒ®жҹ“ж–ҷгҒ®йҒ•гҒ„
гғ»иҰіеҜҹгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®еҷЁе…·пјҲиЈ…зҪ®пјүгҒҢгҖҒиҰіеҜҹгҒ•гӮҢгӮӢеҶ…е®№гӮ’гҒҚгӮҒгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҖӮ
гғ»зҗҶи«–пјҲеҒҸгӮҠгҖҒжқЎд»¶гҒҘгҒ‘пјүгҒӘгҒ—гҒ«гҒҜгҖҒиҰ–еҠӣгӮ’дёҠгҒ’гӮүгӮҢгҒӘгҒ„
гҒӮгӮүгӮҶгӮӢжҖқиҖғгғ»зҗҶи«–гӮ’жҺ’йҷӨгҒ—гҒҰгҒ®иҰіеҜҹгӮ’зӣ®жҢҮгҒҷгҖҒзҰ…гғ»гғҙгӮЈгғ‘гғғгӮөгғҠгғјгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгӮӮгҖҒиҰіеҜҹгҒ®зҗҶи«–иІ иҚ·жҖ§гҒ®е•ҸйЎҢгҒҜгҒӘгҒҸгҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҖӮ
гҒӮгӮүгӮҶгӮӢжқЎд»¶гҒҘгҒ‘гӮ’гҒӘгҒҸгҒ—гҒҹзҗҶи«–гҒҜгҖҒе…·дҪ“жҖ§гӮ’еӨұгҒ„гҖҒжңҖзөӮзҡ„гҒ«гҖҒдҪ•гӮӮиЁҖгҒҲгҒӘгҒҸгҒӘгӮӢгҖӮ
гҒҷгӮӢгҒ©гҒ„иҰіеҜҹгҒ«гҒҜгҖҒйҷҗе®ҡгҒҢеҝ…иҰҒгҖӮ
гҒӮгӮүгӮҶгӮӢзҗҶи«–гӮ’и„ұгҒ‘еҮәгҒҹиҰіеҜҹгҒҜз„ЎзҗҶ
гҒ§гҒҜгҖҒдҪ•гҒҢжңҖе–„гҒӢпјҹ
иӨҮж•°гҒ®иҰіеҜҹж©ҹжў°гҒ«гӮҲгӮӢз”»еғҸгӮ’иҰӢгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒгӮҲгӮҠгғӘгӮўгғӘгғҶгӮЈгҒ®иҝ‘дјјеҖӨгҒ«иҝ‘гҒҘгҒ‘гӮӢгҖӮзӣёеҜҫеҢ–гҒҷгӮӢгҖӮгҒқгҒ®гҒҹгӮҒгҒ«гҒҜгҖҒгҒ„гҒҫиҮӘеҲҶгҒҢиҰӢгҒҰгҒ„гӮӢгӮӮгҒ®гҒҢгҖҒзҗҶи«–дҫқеӯҳзҡ„гҒӘгӮӮгҒ®гҒ гҒЁгҒ®дәҶи§ЈгҒҢеҝ…иҰҒгҖӮпјҲзӣёеҜҫеҢ–пјү
и¶…еҖӢзҡ„иҰіеҜҹиҖ…гҒ®зўәз«ӢгҒ®еҫҢгҖҒгҒқгҒ®гҖҢиҰіеҜҹиҖ…гҖҚгҒҢгҖҒдёҖж°—гҒ«дёҮзү©гҒ®еҒҙгҒ«гҒӘгҒ гӮҢиҫјгҒҝгҖҒеҙ©гӮҢиҫјгҒҝгҖҒгҖҢеҲҶйӣўгҒӘгҒҚгҖҒиҰӢгӮӢгҒ“гҒЁгҖҚгҒҢиө·гҒ“гӮӢвҖ•гҒқгҒ“гҒ§гҒҜгҖҒгҖҲиҰӢгӮӢгӮӮгҒ®гҖүгҒҜгҖҲиҰӢгӮүгӮҢгӮӢгӮӮгҒ®гҖүгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
гӮӮгҒ—гҖҒе®Ңз’§гҒӘгӮөгғҶгӮЈвҖ•е®Ңз’§гҒӘеҶ…/еӨ–зҸҫиұЎгҒ®еҜҫиұЎеҢ–гғ»иҰіеҜҹгғ»йӣўи„ұвҖ•гҒҢзўәз«ӢгҒ•гӮҢгҒҹгҒӘгӮүгҒ°гҖҢзӣ®ж’ғиҖ…гҒЁзӣ®ж’ғгҒ•гӮҢгӮӢгӮӮгҒ®гҖҚгҒЁгҒ®дәҢе…ғжҖ§гҒҜгҖҒе®Ңе…ЁгҒ«жү•жӢӯгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒҜгҒҡгҖӮ
гҒӘгҒңгҒӘгӮүгҖҒгҒқгҒ®дәҢе…ғжҖ§гҖҒгҒқгҒ®еҲҶйӣўж„ҹгӮ’дҪңгӮҠгҒ гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒҜгҖҒд»–гҒӘгӮүгҒ¬гҖҒеҜҫиұЎеҢ–пјҲиҮӘиҰҡпјүгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„еҶ…йқўгҒ®гҒҶгҒ”гӮҒгҒҚвҖ•жҖқиҖғгғ»ж„ҹжғ…гғ»еҲӨж–ӯгҒӘгҒ©гҒ®еҫ®зҙ°гҒӘгҒҶгҒ”гӮҒгҒҚгҒ§гҒӮгӮӢгҒ гӮҚгҒҶгҒӢгӮүгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒӨгҒҫгӮҠгҖҒvipassanaгғ»зҰ…гғ»гӮҜгғӘгӮ·гғҘгғҠгғ гғ«гғҶгӮЈгҒӘгҒ©гҒҢжұӮгӮҒгҒҰгҒ„гӮӢгҖҢиҰіеҜҹгҖҚгҒЁгҒҜгҖҒе®Ңе…ЁгҒӘеҜҫиұЎеҢ–гғ»иҮӘиҰҡпјҲгҒқгӮҢгҒҢз”ҹиө·гҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгҒ«вҖ•гҒҹгҒЁгҒҲгҖҒгҒқгӮҢгҒҢгҖҒгҒ©гӮ“гҒӘеҫ®зҙ°гҒӘжғіеҝөгҒ§гҒӮгӮҢвҖ•ж°—гҒҘгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁпјүвҖ•гӮөгғҶгӮЈвҖ•гҒЁгҖҒе…Ёйқўзҡ„гҒӘпјҲгҒқгҒ®иҰіеҜҹеҜҫиұЎгҒЁгҒ®пјүиһҚеҗҲгҖҒз„ЎеҲҶйӣўжҖ§вҖ•гӮөгғһгғјгғҮгӮЈвҖ•гҒЁгҒ®ж··гҒңеҗҲгӮҸгҒ•гҒЈгҒҹзү№ж®ҠгҒӘгҖҢиҰіеҜҹгҖҚгҒ§гҒӮгӮӢгҖҒгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒӘгҒ®гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
зҰ…гҒ§гҒҜгҒ“гҒ®зү№ж®ҠгҒӘиҰіеҜҹзҠ¶ж…ӢгӮ’гҖҒгҖҢгҒқгҒ®гӮӮгҒ®гҒ«гҒӘгӮҠеҲҮгӮӢгҒ“гҒЁгҖҚгҒӘгҒ©гҒЁиЎЁзҸҫгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
иҒһгҒ“гҒҲгҒҰгҒ„гӮӢйҹігҒ«гҒӘгӮҠгҒҚгӮҠгҖҒж„ҹгҒҳгҒҹж„ҹиҰҡгҒ«гҒӘгӮҠгҒҚгӮҠгҖҒиҮӘеҲҶгҒ®жҖқиҖғгҖҒж„ҹжғ…гҒ«гҒӘгӮҠгҒҚгӮҠгҖҒгҒӘгӮҠгҒҚгӮҠгҒ—гҒҰгҒ„гҒҸгҖӮгҒқгӮҢгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҖҒгҒӮгӮүгӮҶгӮӢе•ҸйЎҢгӮ’з ҙз •гҒ—гҒҰгҒ„гҒҸвҖ•гҒқгӮҢгҒҢзҰ…гҒ®иЎҢгҒҚж–№гҒ§гҒҷгҒӯгҖӮ
е®ҹйҡӣгҒ«гҒҜгҖҒеҫ®зҙ°гҒӘгғ¬гғҷгғ«гҒ§гҒ®гҖҢеҗҢдёҖеҢ–гҖҚгҒ®гҖҢи§ЈйҷӨгҖҚвҖ•гҒӨгҒҫгӮҠгҖҒгҒӮгӮүгӮҶгӮӢеҶ…зҡ„/еӨ–зҡ„зҸҫиұЎгҒ®иҮӘиҰҡгҒЁеҜҫиұЎеҢ–гҖҒйӣўи„ұпјҲжҚЁпјүвҖ•гҒҜгҒ§гҒҚгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢпјҹ пјҲгҒӨгҒҫгӮҠгҖҒе®Ңе…ЁгҒӘиҰіеҜҹгҖҒе…Ёзҡ„гҒӘиҰіеҜҹгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҖӮиҰӢиҗҪгҒЁгҒ—гҒҢгҒӮгӮӢгҖӮпјү
гҒ§гҒҚгҒҰгҒӘгҒ„гҒҢгӮҶгҒҲгҒ«гҖҒгҖҢзӣ®ж’ғиҖ…гҒЁзӣ®ж’ғгҒ•гӮҢгӮӢгӮӮгҒ®гҒЁгҒ„гҒҶеҫ®еҰҷгҒӘдәҢе…ғи«–гҒҢеғҚгҒ„гҒҰгҖҚгҒ—гҒҫгҒҶгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢгҖҒгҒЁдә‘гҒҶгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҢзҸҫиұЎгҒ«еҜҫгҒ—гҒҰгҖҒдёҖеҲҮжҖқиҖғгҒ«гӮҲгӮӢз·ЁйӣҶдҪңжҘӯгӮ’гӮ„гӮҒгҖҚгҒҹгҒЁгҒҚгҖҒгҒқгҒ“гҒ«иҰӢгҒҲгӮӢгҒ®гҒҜгҖҒдёҖеҲҮиЎҢгҒ®гҖҢиӢҰ(гғүгӮҘгғғгӮ«пјүгҖҚжҖ§гҒ§гҒӮгӮӢгҖҒгҒЁгғҶгғјгғ©гғҙгӮЎгғјгғҖгҒҜжҳҺзҷҪгҒ«иЁҖжҳҺгҒ—гҖҒгҖҢиӢҰгҒ§гӮӮжҘҪгҒ§гӮӮгҒӘгҒ„гҖҒиӢҰжҘҪгӮ’и¶…гҒҲгҒҹгҖҒгҒӮгӮӢгҒҢгҒҫгҒҫгҒ гҖҚгҒЁгҖҒеӨ§д№—д»Ҹж•ҷгҒҜзўәзҙ„гҒҷгӮӢвҖ•гҒ“гҒ®жҳҺгӮүгҒӢгҒӘдёҚж•ҙеҗҲгӮ’гҖҒгҖҢвҖҘвҖҘзөҗеұҖжӮҹгӮҠгҒ®еўғең°гӮ’иЁҖиӘһеҢ–гҒҷгӮӢйҡӣгҒ«йҒ•гҒ„гҒҢз”ҹгҒҳгҒҰгҒ„гӮӢгҒ гҒ‘гҒӘгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢгҖҚгҒЁиЁҖгҒЈгҒҰжёҲгҒҫгҒҷгҒ“гҒЁгҒҜгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢгҖҒгҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒҢзҸҫеңЁгҒ®жҷӮзӮ№гҒ§гҒ®з§ҒгҒ®иҰӢи§ЈгҒ§гҒҷгҖӮ
еҲҶгҒӢгӮүгҒӘгҒ„гҒ®гҒҜгҖҒдёҖеҲҮгҒ®еӯҳеңЁгҒ®жң¬иіӘгӮ’иӢҰ(гғүгӮҘгғғгӮ«пјүгҒЁгҒ—гҖҒз…©жӮ©гӮ’еҺігҒ—гҒҸеҗҰе®ҡгҒҷгӮӢз«Ӣе ҙгҒ§гҒҷгҖӮгҒқгҒ—гҒҰгҖҒеӨ§д№—д»Ҹж•ҷгҒҢе·§еҰҷгҒ«з…©жӮ©гӮ’иӮҜе®ҡгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒҷгӮӢжү№еҲӨгҒ§гҒҷгҖӮ
гӮөгғҶгӮЈгҒЁгҒҜгҖҒиӢҰгҒЁгҒӢеҝ«гҒЁгҒӢгҒЁгҒ„гҒҶеҲӨж–ӯд»ҘеүҚгҒ«гҒӮгӮҠгҒ®гҒҫгҒҫгҒ«ж°—д»ҳгҒҚгӮ’е…ҘгӮҢгҒҰиЎҢгҒҸгҒ“гҒЁгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒ®гҒӢгҖҒгҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒҢз§ҒгҒ®зҙ жңҙгҒӘз–‘е•ҸгҒ§гҒҷгҖӮгҒқгҒ—гҒҰгҖҒз…©жӮ©гҒ®гҒӮгӮҠгҒ®гҒҫгҒҫгҒ«ж°—д»ҳгҒҚеҸ—е®№гҒҷгӮӢгҒЁгҒҚгҖҒз…©жӮ©гҒёгҒ®еӣҡгӮҸгӮҢгҒӢгӮүи§Јж”ҫгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҸгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢгҖӮеӨ§д№—д»Ҹж•ҷгҒ®дёӯгҒ«гҒҜгҖҒгҒқгҒҶгҒ„гҒҶиҖғгҒҲж–№гҒҢеңЁгӮӢгҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮгҒқгӮҢгҒҜгҖҒз…©жӮ©гҒ®иӮҜе®ҡгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸж°—д»ҳгҒҚгҒЁеҸ—е®№гҒ«гӮҲгӮӢгҖҒз…©жӮ©гҒӢгӮүгҒ®и§Јж”ҫгҒӘгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢгҒЁжҖқгҒҶгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖӮ
гғҶгғјгғ©гғҙгӮЎгғјгғҖд»Ҹж•ҷгҒҢгҖҒз…©жӮ©гӮ’еҗҰе®ҡгҒЁиӮҜе®ҡгҒЁгҒ„гҒҶгғ¬гғҷгғ«гҒ§иӘһгӮӢгҒЁгҒ“гӮҚгҒҢгӮҲгҒҸгӮҸгҒӢгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮз”ҹиө·гҒҷгӮӢгҒӮгӮӢгҒҢгҒҫгҒҫгҒ«ж°—д»ҳгҒҚгӮ’е…ҘгӮҢгӮӢгӮөгғҶгӮЈгҒ®иҖғгҒҲж–№гҒЁгҖҒз§ҒгҒ®дёӯгҒ§гҒҶгҒҫгҒҸж•ҙеҗҲгҒ—гҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
гғҙгӮЈгғ‘гғғгӮөгғҠгғјзһ‘жғігҒ®дҝ®иЎҢжі•гҒ«гҒҜйқһеёёгҒ«еј·гҒ„е…ұйіҙгӮ’ж„ҹгҒҳгӮӢгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҒқгҒ®иғҢжҷҜгӮ’гҒӘгҒҷгғҶгғјгғ©гғҙгӮЎгғјгғҖд»Ҹж•ҷгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒеј•гҒЈгҒӢгҒӢгӮҠгҒҢгҒӮгҒЈгҒҰгҒҷгӮ“гҒӘгӮҠеҸ—гҒ‘е…ҘгӮҢгӮүгӮҢгҒӘгҒ„гҖӮ
дёҖз•ӘгҒ®еј•гҒЈгҒӢгҒӢгӮҠгҒҜгҖҒгӮ„гҒҜгӮҠзҸҫиұЎгҒ®дёҖеҲҮгӮ’иӢҰпјҲгғүгӮҘгғғгӮ«пјүгҒЁгҒ—гҒҰе®Ңе…ЁгҒ«еҗҰе®ҡгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ гҖӮ
гғҙгӮЈгғ‘гғғгӮөгғҠгғјзһ‘жғігҒҜгҖҒз”ҹж»…еӨүеҢ–гҒҷгӮӢзҸҫиұЎгҒ®еңЁгӮӢгҒҢгҒҫгҒҫгҒ«ж°—д»ҳгҒ„гҒҰзўәиӘҚгҒҷгӮӢгӮөгғҶгӮЈгҒ®дҝ®иЎҢгҒ«еҠұгӮҖгҖӮгӮөгғҶгӮЈгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰзҸҫиұЎгӮ’гҒӮгӮӢгҒҢгҒҫгҒҫгҒ«еҸ—гҒ‘е…ҘгӮҢгӮӢиЁ“з·ҙгӮ’з¶ҡгҒ‘гӮӢгҒЁгҖҒгӮ„гҒҢгҒҰеҝғгҒҢдҪңгӮҠеҮәгҒҷгӮӮгҒ®гҒЁзңҹгҒ«е®ҹеңЁгҒҷгӮӢгӮӮгҒ®гҒЁгҒ®йҒ•гҒ„гҒҢгҒҜгҒЈгҒҚгӮҠгҒЁеҲҶгҒӢгӮҠгҖҒзҸҫиұЎгҒ®зңҹгҒ®е§ҝгҒҢжҙһеҜҹгҒ•гӮҢгӮӢзһ¬й–“гҒҢжқҘгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҖӮ
гҒҫгҒҹгҖҒеҝғгҒҢжҸҸгҒҚеҮәгҒҷеҰ„жғігғ»е№»еҪұгғ»зҸҫе®ҹгҒ®жӯӘжӣІгҒ®гҒҹгҒҗгҒ„гҒҢгҒҜгҒЈгҒҚгӮҠиҰӢгҒҲгӮӢгҒЁгҖҒеҗҢжҷӮгҒ«иҮӘжҲ‘пјҲгӮЁгӮҙпјүгҒҢгҖҒе…ғжқҘгҒҜеӯҳеңЁгҒ—гҒӘгҒ„е№»еҪұгҒ§гҒӮгӮҠйҢҜиҰҡгҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеҲҶгҒӢгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҖӮ
д»ҘдёҠгҒҜзҙҚеҫ—гҒ§гҒҚгӮӢгҖӮеӨ§д№—д»Ҹж•ҷгӮӮеҹәжң¬зҡ„гҒ«гҒҜеҗҢгҒҳгҒ“гҒЁгӮ’иЁҖгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁжҖқгҒҶгҖӮеҮЎеӨ«гҒҜиЁҖи‘үгҒЁжҖқиҖғгӮ’д»ӢгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҢеҜҫз«ӢгҒЁеҢәеҲҘгҒ®зӣёгҖҚгҒ®дёӢгҒ®гҒ“гҒ®дё–з•ҢгӮ’иҰӢгӮӢгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҒқгӮҢгҒҜдё–з•ҢгҒ®зңҹе®ҹгҒ®зӣёгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҖӮиңғж°—жҘјгҒ®гҒ”гҒЁгҒҚе№»гҒ®дё–з•ҢгӮ’зңҹе®ҹгҒЁиҰӢй–“йҒ•гҒҲгҒҰгҒ„гӮӢгҒ«йҒҺгҒҺгҒӘгҒ„гҖӮиЁҖи‘үгҒ«гӮҲгӮӢеҢәеҲҘгғ»еҜҫз«Ӣгғ»еҲҶеҲҘгӮ’и¶…гҒҲгҒҹдё–з•ҢгҒ®гҒӮгӮҠж–№гҒҢз©әжҖ§гҒЁе‘јгҒ°гӮҢгӮӢгҖӮ
гӮҸгҒӢгӮүгҒӘгҒ„гҒ®гҒҜгҖҒгғҶгғјгғ©гғҙгӮЎгғјгғҖд»Ҹж•ҷгҒ§гҒҜгҖҒе№»еҪұгӮ’жҢҜгӮҠжү•гҒЈгҒҹгҒЁгҒҚгҒ«жҙһеҜҹгҒ•гӮҢгӮӢдё–з•ҢгҒҢгҖҒиӢҰгҒЁжҚүгҒҲгӮүгӮҢгҖҒеӨ§д№—д»Ҹж•ҷгҒ§гҒҜгҒқгӮҢгҒҢгҖҒз©әгҒЁжҚүгҒҲгӮүгӮҢгӮӢгҒЁгҒ“гҒЁгҒ гҖӮгғҙгӮЈгғ‘гғғгӮөгғҠгғјзһ‘жғігӮӮгӮЁгӮҙгӮ„иЁҖи‘үгҒ«гӮҲгӮӢжӯӘжӣІд»ҘеүҚгҒ®гҒӮгӮҠгҒ®гҒҫгҒҫгҒ®дё–з•ҢгӮ’иҰӢгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶзӮ№гҒҜгҖҒеӨ§д№—д»Ҹж•ҷгҒЁеҗҢгҒҳгҒ§гҒӮгӮӢгҒҜгҒҡгҒӘгҒ®гҒ«гҖҒгҒӘгҒңгҒқгӮҢгҒҜгҖҒз©әгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸеҝ«гӮ„е№ёзҰҸгҒЁеҜҫз«ӢгҒҷгӮӢиӢҰгҒӘгҒ®гҒӢгҖӮзҸҫиұЎгӮ’иӢҰгҒЁиҰҸе®ҡгҒ—гҒҹгҒЁгҒҚгҖҒгҒқгӮҢгҒҜгӮӮгҒҶгҖҢеҜҫз«ӢгҒЁеҢәеҲҘгҒ®зӣёгҖҚгҒ§гҒ®иҰӢж–№гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒ®гҒӢгҖӮ
гғҶгғјгғ©гғҙгӮЎгғјгғҖгҒ§иЁҖгҒҶгҖҢиӢҰгҖҚгҒ«гҒҜгҖҒ
гғ»иӢҰвҖҗиӢҰ
гғ»еЈҠвҖҗиӢҰпјҲеӨүжҳ“иӢҰпјү
гғ»иЎҢвҖҗиӢҰ
гҒ®дёүгҒӨгҒ®гӮӮгҒ®гҒҢгҒӮгӮӢгҖҒгҒЁдә‘гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮпјҲгҒ“гӮҢгӮүгҒҜгҖҒеҚҳгҒӘгӮӢеҪўејҸзҡ„гҒӘж•ҷзҗҶгғ»еҲҶйЎһгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒҜгҒҡгҒ§гҒҷгҖӮпјү
гҒқгҒ—гҒҰгҖҢдә”иҳҠзҡҶиӢҰгҖҚгҒ®ж №жӢ гҒҜгҖҒжңҖзөӮзҡ„гҒ«гҒҜгҖҒгҒ“гҒ®гҖҒеӯҳеңЁгҒ®гҖҢиЎҢвҖҗиӢҰгҖҚжҖ§гҒ«гҒӮгӮӢгҒ®гҒ гҒЁжҖқгӮҸгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮжҺІзӨәжқҝгҒ§гҒ®иӯ°и«–гҒҜгҖҒгҒ“гҒ®дёүгҒӨгҒ®гҖҢиӢҰгҖҚгҒҢе…ҘгӮҠд№ұгӮҢгҖҒе°‘гҖ…ж··д№ұгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгӮҲгҒҶгҒ«иҰӢеҸ—гҒ‘гӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮNoboruгҒ•гӮ“гҒ®еј•гҒЈжҺӣгҒӢгҒЈгҒҰгҒҠгӮүгӮҢгӮӢе•ҸйЎҢгҒҜгҖҒгҖҢиЎҢвҖҗиӢҰгҖҚгҒ®гғ¬гғҷгғ«гҒ§гҒ®е•ҸйЎҢгҒ§гҒӮгӮӢгҒҜгҒҡгҒ§гҒҷгҖӮ
гҖҢз”ҹж»…гҖҚгҖҢеЈҠж»…гҖҚгӮ’зӣ®гҒ®еҪ“гӮҠгҒ«гҒ—гҒҰгҒ«гҖҒжҖ–гӮҢгҖҒгҒҠгҒ®гҒ®гҒҚгҖҒжҲҰж…„гҒҷгҖҒгҒЁгҒ„гҒҶгҖҢиЎҢвҖҗиӢҰгҖҚгҒ®дҪ“йЁ“гҒҜгҖҒvipassanaгҒ®дҝ®иЎҢиЎҢзЁӢгҒ®гҒӘгҒӢгҒ§гҒҜгҖҒпјҲгҒҹгҒ„гҒҰгҒ„пјүй җжөҒйҒ“гҒ«гҒӘгӮӢпјҲгҒӨгҒҫгӮҠгҖҒжӮҹгӮӢпјүзӣҙеүҚгҒ«еҲқгӮҒгҒҰиө·гҒ“гӮӢгҒ“гҒЁгҒ®гӮҲгҒҶгҒ§гҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ“гҒ§иЁҖгӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖҢиӢҰгҖҚгҒҢгҖҒеёёиӯҳзҡ„гҒӘж„Ҹе‘ігҒ§гҒ®гҖҢгҒӮгҒӮгҖҒиӢҰгҒ—гҒ„пҪһгҖҒиӢҰз—ӣгҒ пҪһгҖҚгҒЁж„ҹгҒҳгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҒӮгӮӢгҒЁгҒҜжҖқгҒҲгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гҒӨгҒҫгӮҠгҖҒпјҲд»ҠгҒ®жҷӮзӮ№гҒ§гҒ®пјүз§ҒгҒҹгҒЎгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгҖҢиЎҢвҖҗиӢҰгҖҚгҒЁгҒҜгҖҒгҖҢи©ұгҒЁгҒ—гҒҰгҒҜеҲҶгҒӢгӮӢгҒ‘гҒ©гҖҒеҸ—гҒ‘е…ҘгӮҢгӮүгӮҢгҒӘгҒ„гҖҚгӮӮгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒгҖҢи©ұгҒЁгҒ—гҒҰгҒҷгӮүзҗҶи§ЈгҒ§гҒҚгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҖҒгҒҫгҒЈгҒҹгҒҸиҰӢеҪ“гҒ®гҒӨгҒӢгҒӘгҒ„гҖҚгӮҝгӮӨгғ—гҒ®иӢҰгҒ§гҒӮгӮӢгҒҜгҒҡгҒ§гҒҷгҖӮ
еүҚгҒ«гҖҒгҒ©гҒ“гҒӢгҒ§гҖҒиӘ°гҒӢгҒҢгҖҢиӢҰгҒ®зҗҶи§ЈгҒ“гҒқгҒҢгҖҒд»Ҹж•ҷпјҲеҺҹе§Ӣд»Ҹж•ҷгҖҒгғ–гғғгғҖгҒ®иӘ¬гҒ„гҒҹж•ҷгҒҲпјүгҒ®е…ЁгҒҰгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮиӢҰгӮ’зҗҶи§ЈгҒ§гҒҚгҒҹгҒӘгӮүгҖҒи§Ји„ұгҒҷгӮӢгҖҚгҒЁиЁҖгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гӮ’иҒһгҒ„гҒҹгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢгҖҒгҒҫгҒ•гҒ«гҖҒгҒқгҒ®йҖҡгӮҠгҒӘгҒ®гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
гҖҢиӢҰгҖҚгҒ®зҗҶи§ЈгҒ“гҒқгҒҢйҮҚиҰҒгҒӘгҒ®гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
гҖҢжҖқиҖғеҒңжӯўгҒ—гҒҰгҖҒзҸҫиұЎдё–з•ҢгӮ’гҒӮгӮӢгҒҢгҒҫгҒҫгҒ«иҰіеҜҹгҒ—гҒҹгҒЁгҒҚпјҲеҰӮе®ҹзҹҘиҰӢпјүгҖҒгҖҢдёҖеҲҮиЎҢвҖҗиӢҰгҖҚгӮ’ж„ҹгҒҡгҖҒгҖҢдёҖеҲҮиЎҢвҖҗиӢҰгҖҚгӮ’ж„ҹгҒҳгӮӢгҒҢж•…гҒ«гҖҒгҖҢеҺӯйӣўгҖҚгҒҢз”ҹгҒҡпјҲгҒ“гҒ®гҖҢеҺӯйӣўгҖҚгҒЁдә‘гҒҶиЁҖи‘үгҖҒиЁҖи‘үгҒ©гҒҶгӮҠгҒ«иӘӯгӮҖгҒӘгӮүгҖҒеҺӯгҒ„йӣўгӮҢгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгӮҲгҒӯгҖӮжұәгҒ—гҒҰгҖҒгҖҢж·ЎгҖ…гҒЁгҖҚгҒЁгҒӢгҖҒгҖҢгҒӮгӮӢгҒҢгҒҫгҒҫгҒ«гҖҚгҒЁгҒӢгҖҢеҸ—е®№гҒҷгӮӢгҖҚгҒЁгҒӢгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸпјүгҖҒгҖҢеҺӯйӣўгҖҚгҒҢз”ҹгҒҳгҒҹгҒҢж•…гҒ«и§Ји„ұгҒҷгӮӢгҖҚгҒЁдә‘гҒҶгҒ®гҒҜеҺҹе§ӢзөҢе…ёгҒ«з№°гӮҠиҝ”гҒ—зҸҫгӮҸгӮҢгӮӢиЎЁзҸҫгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҒ“гӮҢиҮӘдҪ“гӮ’гҖҒгҖҢгҒ“гӮҢгҒҜгғ–гғғгғҖгҒ®иЁҖгҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„пјҒгҖҖгғ–гғғгғҖгҒ®жӯ»еҫҢгҖҒе°Ҹд№—д»Ҹж•ҷеҫ’гҒҢжҚҸйҖ гҒ—гҒҹи©ұгҒ гҖҚгҒӘгҒ©гҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒҜгҖҒгҒӮгҒҫгӮҠгҒ«з„ЎзҗҶгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ®гҖҒгҖҢеҰӮе®ҹзҹҘиҰӢвҶ’гҖҢдёҖеҲҮиЎҢвҖҗиӢҰгҖҚгҒ®жҙһеҜҹвҶ’еҺӯйӣўвҶ’и§Ји„ұгҖҚгӮ’еҗҰе®ҡгҒҷгӮӢгҒӘгӮүгҒ°гҖҒгғ–гғғгғҖгӮӮгҖҒеҺҹе§Ӣд»Ҹж•ҷгӮӮеҗҰе®ҡгҒ—гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
гҒқгӮҢгҒ«еҜҫгҒ—гҖҒгҖҢиӢҰгҒӘгӮӢдё–з•ҢвҶ’еҰӮе®ҹзҹҘиҰӢвҶ’иӢҰ/жҘҪгҒ®и¶…и¶ҠпјҲз„ЎиҮӘжҖ§гғ»з©әгҒ®жҙһеҜҹпјүвҶ’зҸҫеңЁж¶…ж§ғпјҲеҪ“еҮҰеҚігҒЎи“®иҸҜеӣҪпјүгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒҢгҖҒеӨ§д№—д»Ҹж•ҷдёҖиҲ¬гҒ®жӮҹгӮҠиҰігҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒӢгҖӮ
гҖҢдҪ“йЁ“иҖ…гҖҚгҒЁгҖҢдҪ“йЁ“гҖҚгҒЁгҒ®дәҢе…ғжҖ§гҒҢеҙ©гӮҢеҺ»гӮҠгҖҒеҲҶйӣўгҒӘгҒҚгҖҠиҰӢгӮӢгҒ“гҒЁгҖӢгҒҢиө·гҒ“гӮӢгҒЁгҒҚвҖ•
гҒқгҒ®гҒЁгҒҚгҖҒгҒқгҒ®гҖҢдҪ“йЁ“гҖҚгӮ’гҖҒгҖҢдҪ“йЁ“иҖ…гҖҚгҒҢгҒӘгҒҸгҒӘгҒЈгҒҰгҖҢдҪ“йЁ“гҖҚгҒ®гҒҝгҒҢж®ӢгҒЈгҒҹпјҲгҖҢдҪ“йЁ“гҖҚгҒ®гҒҝгҒ«вҖңгҒӘгҒЈгҒҹвҖқпјүгҖҒгҒЁиЎЁзҸҫгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮгҖҒеҲҶйӣўгҒ—гҒҹеҜҫиұЎгҒЁгҒ—гҒҰгҒ®гҖҢдҪ“йЁ“пјҲеҶ…е®№пјүгҖҚгҒҢгҒӘгҒҸгҒӘгҒЈгҒҰгҖҒгҖҢдҪ“йЁ“иҖ…вҖ•зңҹе®ҹгҒ®иҮӘе·ұгғ»жң¬жқҘгҒ®йқўзӣ®вҖ•гҖҚгҒ®гҒҝгҒҢж®ӢгҒЈгҒҹпјҲгҒҢгҖҒйңІгӮҸгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖҒйЎ•зҸҫгҒ—гҒҹпјүгҖҒгҒЁиЎЁзҸҫгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮгҖҒгҒӮгӮӢгҒ„гҒҜгҖҒгҖҢдҪ“йЁ“иҖ…гҖҚгӮӮгҖҢдҪ“йЁ“гҖҚгӮӮгҖҒдҪ•гӮӮгҒӢгӮӮгҒҢгҒӘгҒҸгҒӘгҒЈгҒҹпјҲйҷҗз•Ңз·ҡгҖҒеўғз•Ңз·ҡгҒ®гҒӘгҒ„emptiness)гҖҒгҒЁиЎЁзҸҫгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮеҸҜиғҪгҒ гҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
иҮӘе·ұгҒҢгҒӘгҒҸгҒӘгҒЈгҒҰгҖҒз„ЎжҲ‘гҒ«гҒӘгҒЈгҒҹвҖ•з„ЎжҲ‘гҒ«гҒӘгҒЈгҒҰиҰӢгӮҢгҒ°гҖҒе…ЁгҒҰгҒҢиҮӘе·ұгҒ гҒЈгҒҹгҖҒгҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒҜзҰ…е®—гҒ®жұәгҒҫгӮҠж–ҮеҸҘвҖ•гҒҹгҒЁгҒҲгҒ°гҖҒгҒ“гӮ“гҒӘж„ҹгҒҳгҒ§гҒҷгҖӮ
гҖҢзҰ…гҒ®зңҹй«„гҒҜиҮӘе·ұгӮ’еҝҳгҒҡгӮӢгҒ«гҒӮгӮӢгҖӮзңҹдҝ®еҠҹжҲҗгӮҠгҖҒиә«еҝғиҮӘ然гҒ«и„ұиҗҪгҒ—гҒҰгҖҒзңҹз®ҮиҮӘе·ұгӮ’еҝҳгҒҡгӮӢжҷӮгҖҒеӨ©ең°зҡҶиҮӘе·ұгҒӘгӮүгҒ–гӮӢгҒӘгҒҚгӮ’иҮӘиҰҡгҒ—гҒҰгҖҒжүӢгҒ®иҲһгҒ„гҖҒи¶ігҒ®иёҸгӮҖгӮ’зҹҘгӮүгҒҡгҒҳгӮғгҖӮ
гҒ•гӮҢгҒ©гӮӮз„Ўе§ӢеҚҙжқҘзІҳзқҖзёӣзқҖгҒ®иҮӘе·ұгӮ’еҝҳгҒҡгӮӢгҒ®е®№жҳ“гҒӘгӮүгҒ–гӮӢгҒ“гҒЁгӮ’гҖҒеҝҳгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҒ§гҒҚгҒ¬гҖӮгҖҚ
иЎЁи©®пјҲиӮҜе®ҡзҡ„иЎЁзҸҫгҖҒз”ҹгҒӢгҒҷпјүгҒЁгҖҒйҒ®и©®пјҲеҗҰе®ҡзҡ„иЎЁзҸҫгҖҒж®әгҒҷпјүвҖ•гҒқгҒ®гҒ©гҒЎгӮүгҒҢдҪҝгӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒӢгҒҜгҖҒпјҲзҰ…гҒ®е ҙеҗҲпјүж–Үи„ҲгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰеҲӨж–ӯгҒҷгӮӢгҒ—гҒӢгҒӘгҒ„гҖӮ


