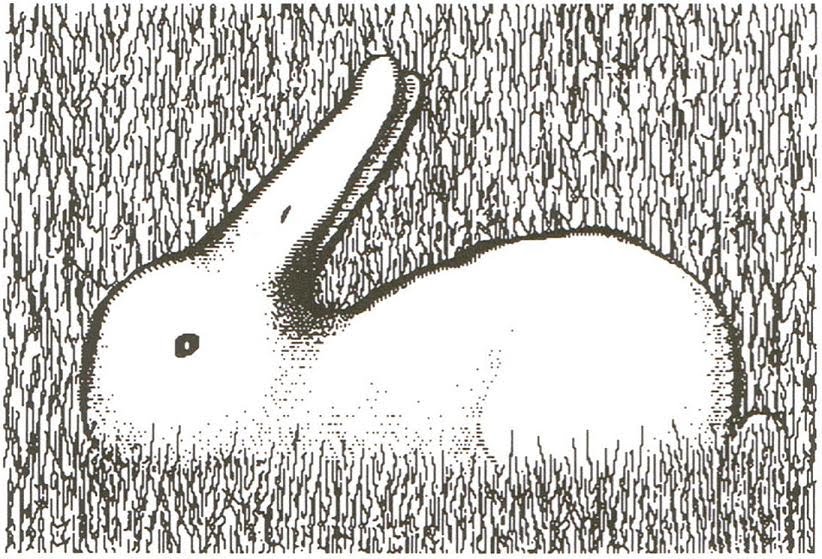гӮҜгғӘгӮ·гғҘгғҠгғ гғ«гғҶгӮЈгҒ®ж•ҷгҒҲгҒҜзҫҺгҒ—гҒ„гҖӮ
гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгҒқгӮҢгҒҜзңҹз©әдёӯгҒ®зңҹзҗҶгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
гҒқгҒ“гҒ«гҒҜиӘ°гӮӮдҪҸгӮҖгҒ“гҒЁгҒҜгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҖӮ
гҒЎгӮҮгҒҶгҒ©жңҲгҒ«дҪҸгӮҖгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҒ«гҖӮ
пјҲеҮәе…ёдёҚжҳҺгҒ®иӘ°гҒӢгҒ®иЁҖи‘үпјү
гҒҜгҒҳгҒҫгӮҠгҒ®гӮҜгғӘгӮ·гғҘгғҠгғ гғ«гғҶгӮЈ
з§ҒгҒ®дҝ®иЎҢгҒ®еҮәзҷәзӮ№гҒ«гҒҜгӮҜгғӘгӮ·гғҘгғҠгғ гғ«гғҶгӮЈгҒҢеұ…гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒқгӮҢгҒҜдәҢеҚҒжӯігҒ«гҒӘгӮӢе°‘гҒ—еүҚгҒ®гҒ“гҒЁгҖҒ
гҒ„гҒҫиҖғгҒҲгҒҰгӮӮдёҚжҖқиӯ°гҒӘгӮҝгӮӨгғҹгғігӮ°гҒ§гҒ®еҮәдјҡгҒ„гҒ§гҒ—гҒҹгҖӮвҶ’ еӨ•ж—ҘгҒ®дҪ“йЁ“
еҲқиӘӯгҒ—гҖҒпјҲгҒқгҒ®еӨҡгҒҸгҒҜзҗҶи§ЈгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҒҫгҒҫпјүиЎқж’ғгӮ’еҸ—гҒ‘гҖҒгҒқгҒ“гҒӢгӮүж•°е№ҙй–“гҖҒеӯӨзӢ¬гҒ«з…©жӮ¶гҒҷгӮӢжҷӮжңҹгҒҢз¶ҡгҒҚгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҒқгҒ®еҫҢгҖҒиҮӘеҠӣгҒ§гҒҜгҒ©гҒҶгҒ—гӮҲгҒҶгӮӮгҒӘгҒҸгҖҒдҪ•гӮүгҒӢгҒ®еҠ©гҒ‘гӮ’жұӮгӮҒгҒҰдјқзөұд»Ҹж•ҷгҒ®дё–з•ҢгҒёжөҒгӮҢгӮӢгҖҒгҒЁгҒ„гҒҶзөҢз·ҜгӮ’гҒҹгҒ©гӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮ
пјҠ иҮӘиә«гҒ®дҝ®иЎҢжҷӮд»ЈгҖҒдҪ•е№ҙгҒӢгҒӢгҒ‘гҒҰдҪңгҒЈгҒҹгҖҒгҒ“гҒ®гҖҢгӮҜгғӘгӮ·гғҘгғҠгғ гғ«гғҶгӮЈиӘӯи§ЈгҖҚгҒ«зӣ®гӮ’йҖҡгҒ—гҒҰгӮӮгӮүгҒҲгӮҢгҒ°гҖҒз§ҒгҒҢгҖҒгҒқгӮӮгҒқгӮӮгҖҒгҒ©гӮ“гҒӘе•ҸйЎҢж„ҸиӯҳгӮ’жҢҒгҒЈгҒҰе®ҹи·өдҝ®иЎҢгӮ’гӮ№гӮҝгғјгғҲгҒ—гҒҹгҒ®гҒӢгҖҒзҗҶи§ЈгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒ гҒ‘гӮӢгӮӮгҒ®гҒЁжҖқгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ“гҒ“гҒӢгӮүи§ЈиӘ¬гҒ—гҒҰгҒ„гҒҸе®ҹи·өзҗҶи«–гҒЁжҠҖжі•гҒЁгҒҜгҖҒгҒқгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘиғҢжҷҜгӮ’жҢҒгҒЈгҒҹдәәй–“гҒҢгҖҒи©ҰиЎҢйҢҜиӘӨгҖҒзҙҶдҪҷжӣІжҠҳгӮ’зөҢгҒҹжң«гҒ«гҒҹгҒ©гӮҠзқҖгҒ„гҒҹж–№жі•и«–гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҒқгҒ®зҙ°йғЁгҒҜгҖҒдјқзөұд»Ҹж•ҷеҗ„жҙҫгҒ®жҠҖжі•гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰж§ӢжҲҗгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гӮӮгҒ—гҖҒгҒқгҒ®дәәгҒ®гҖҒж°—гҒҘгҒҚгҒ®зҙ”еәҰгғ»еј·еәҰгҒҢж—ўгҒ«е……еҲҶгҒӘгғ¬гғҷгғ«гҒ«гҒӮгӮӢгҒӘгӮүгҒ°гҖҒгҒ“гҒЎгӮүгҒ®з ”дҝ®гҒ§иЎҢгҒҶгӮҲгҒҶгҒӘгҖҢж°—гҒҘгҒҚгҒ®еҹәзӨҺиЁ“з·ҙгғ»гғҒгғҘгғјгғӢгғігӮ°пјҲиӘҝеҫӢпјүгҖҚгҒ®еҝ…иҰҒжҖ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒгӮҜгғӘгӮ·гғҘгғҠгғ гғ«гғҶгӮЈгҒ®иЁҖгҒҶйҖҡгӮҠгҖҒдёҖеҲҮгҒ®жҠҖжі•гӮӮеҠӘеҠӣгӮӮж–№еҗ‘гҒҘгҒ‘гӮӮз„ЎгҒ—гҒ®гҖҢгҒӮгӮӢгҒҢгҒҫгҒҫгҖҚгҒ®иҰіеҜҹгӮ’йҖҡгҒ—гҒҰгҒ®иҮӘе·ұзҗҶи§ЈгҒЁеӨүе®№гҖҒгҒқгҒ—гҒҰжңҖзөӮзҡ„гҒӘи§Јж”ҫгҒҢиө·гҒ“гӮӢгҒ®гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
гҒқгҒ®дҪңжҘӯгӮ’йҖІгӮҒгҒҰгҒ„гҒҸдёҠгҒ§еҝ…иҰҒгҒӘе…·дҪ“зҡ„жіЁж„ҸгҒҜгҖҒж°—гҒҘгҒҚгҒ®е®ҹи·өгғһгғӢгғҘгӮўгғ«пјҲж”»з•Ҙжң¬пјүгҒҹгӮӢеҪјгҒ®и‘—дҪңгҒ®гҒӘгҒӢгҒ§и©ізҙ°гҒ«иӘһгӮүгӮҢгҒҰгҒҠгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒз§Ғеҗ«гӮҒеӨҡгҒҸгҒ®дҝ®иЎҢиҖ…гҒҜгҖҒжӮІгҒ—гҒ„гҒӢгҒӘгҖҒзө¶еҜҫзҡ„гҒ«ж°—гҒҘгҒҚгҒ®зҙ”еәҰгғ»еј·еәҰгҒҢи¶ігӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
д»ҠгҒӮгӮӢгҒҫгҒҫгҒ§гҒҜгҖҒгҒӮгҒҫгӮҠгҒ«ж°—гҒҘгҒҚгҒ®гғ¬гғҷгғ«гҒҢејұгҒҸгҖҒйҲҚгҒҸгҖҒж•…гҒ«гғһгғӢгғҘгӮўгғ«гҒҢгғһгғӢгғҘгӮўгғ«гҒЁгҒ—гҒҰж©ҹиғҪгҒ—гҒҰгҒҸгӮҢгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒқгҒ“гҒ«иүІгҖ…гҒӘжҠҖжі•гӮ’з”ЁгҒ„гҒҰгҒ®пјҲеүҚж®өйҡҺгҒ®пјүгҖҢж°—гҒҘгҒҚгҒ®еҹәзӨҺиЁ“з·ҙгҖҚгҒ®ж„Ҹзҫ©гӮ„еҝ…иҰҒжҖ§гҒҢеӯҳеңЁгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
жңҖзөӮзҡ„гҒ«гҖҒгҒқгӮҢгӮүгҒ®жҠҖжі•гҒҢиә«гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰпјҲж°—гҒҘгҒҚгғ»жҙһеҜҹгғўгғјгғүгҒҢгҖҒж„Ҹиӯҳгғ»и„ігҒ«ж§ӢйҖ еҢ–гҒ•гӮҢгҒҰпјүгҖҒзү№гҒ«гҖҢжҠҖжі•гғ»гғҶгӮҜгғӢгғғгӮҜгҖҚгҒЁгҒ—гҒҰгӮ„гҒЈгҒҰгҒ„гӮӢиҮӘиҰҡгҒҢгҒӘгҒ„гҒҫгҒҫгҖҒгҒқгӮҢгҒҢе……еҲҶгҒ«ж©ҹиғҪгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢзҠ¶ж…ӢгҒҢж—ҘеёёеҢ–гҒ•гӮҢж„ҸиӯҳгҒ®еёёж…ӢгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒЈгҒҹгҒӘгӮүгҒ°гҖҒгҒқгҒ®гҒЁгҒҚгҒ«гҒҜгҖҒгҒқгӮҢгӮүгҒ®жҠҖжі•гҒҜгҒҷгҒ№гҒҰеҝҳгӮҢгҒҰпјҲжҚЁгҒҰгҒҰпјүгҒ—гҒҫгҒҲгҒ°иүҜгҒ„гҒ—гҖҒгҒҫгҒҹгҖҒгҒқгҒҶгҒ—гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гӮҜгғӘгӮ·гғҘгғҠгғ гғ«гғҶгӮЈгҒ®иЁҖгҒҶгҖҢйҒёжҠһгҒӘгҒҚгҖҒйҷҗз•ҢгҒӘгҒҚгҖҒзҗҶжғіпјҲгҒӮгӮӢгҒ№гҒҚпјүгҒӘгҒҚгҖҒеҲ»гҖ…гҒ®ж°—гҒҘгҒҚгҖҚгҒ®зҠ¶ж…ӢгҒ«гҒҜе…ҘгӮҢгҒӘгҒ„гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
иЈңеҠ©зҡ„жҠҖжі•гҒ«гҒҜгҖҒдҪҝгҒҶгҒ№гҒҚжҷӮжңҹгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒгҒҫгҒҹгҖҒйӣўгӮҢгҖҒжҚЁгҒҰгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒ„жҷӮжңҹгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ—гҒӢгҒ—е®ҹйҡӣгҒ«гҒҜгҖҒгҖҢйӣўгӮҢгӮӢгҖҚеҝ…иҰҒгӮӮгҖҢжҚЁгҒҰгӮӢгҖҚеҝ…иҰҒгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гҒқгӮҢгӮүгҒ®жҠҖжі•гҒҢе®ҢжҲҗгҒ—гҒҹгҒЁгҒҚгҖҒгҒқгӮҢгӮүгҒҜйқҷгҒӢгҒ«жң¬жқҘгҒ®гӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖҢж°—гҒҘгҒҚ-ж„ҸиӯҳгҖҚгҒ®гҒӘгҒӢгҒ«жә¶гҒ‘иҫјгҒҝгҖҒе§ҝгӮ’ж¶ҲгҒ—гҖҒгҒқгҒ—гҒҰйҖҸжҳҺгҒӘеҪўгҒ§е®Ңе…ЁгҒ«ж©ҹиғҪгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒқгӮҢгҒҢиҰӢгӮүгӮҢгӮӢпјҲиӘҚиӯҳгҒ•гӮҢгӮӢпјүеҜҫиұЎгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒиҰӢгӮӢеҷЁе®ҳгҒЁгҒӘгӮҠиҮӘиә«гҒ®иҰ–з•ҢгҒӢгӮүж¶ҲгҒҲгҒҹгҒЁгҒҚгҖҒгҒҜгҒҳгӮҒгҒҰе®ҢжҲҗгҒ—гҒҹпјҲиә«гҒ«гҒӨгҒ„гҒҹпјүгҒЁиЁҖгҒҲгӮӢгҒӢгӮүгҒ§гҒҷгҖӮ
иЈңеҠ©зҡ„жҠҖжі•гҒ®еӯҳеңЁж„Ҹзҫ©
гҒқгӮҢгҒҜеҲқгӮҒгҒҰиҮӘи»ўи»ҠпјҲдәҢијӘи»ҠпјүгҒ«д№—гӮӢгҒ®гӮ’иҰҡгҒҲгӮӢгҒЁгҒҚгҒ«дјјгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҖҢзңҹгҒ«иҮӘи»ўи»ҠпјҲдәҢијӘи»ҠпјүгҒ«д№—гӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮҠгҒҹгҒ„гҒ®гҒӘгӮүгҖҒеҲқгӮҒгҒӢгӮүеҠ©гҒ‘гҒ®жқ–гҒЁгҒ—гҒҰгҒ®иЈңеҠ©ијӘпјҲгӮігғӯпјүгӮ’дҪҝгҒҶгҒ№гҒҚгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҖҚгҒЁиҖғгҒҲгҒҰгҖҒе§ӢгӮҒгҒӢгӮүгӮігғӯпјҲиЈңеҠ©ијӘ)з„ЎгҒ—гҒ§з·ҙзҝ’гҒҷгӮӢгҒӢгҖҒгҖҢиҮӘеңЁгҒ«д№—гӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮӢгҒҫгҒ§гҖҒгӮігғӯпјҲиЈңеҠ©ијӘпјүгҒ®еҠ©гҒ‘гӮ’еҖҹгӮҠгӮӢгҒ®гӮӮжңүгӮҠгҖҚгҒЁиҖғгҒҲгӮӢгҒӢгҒ®йҒ•гҒ„гҒ§гҒҷгҖӮ
гӮігғӯпјҲиЈңеҠ©ијӘпјүгҒ®еҠ©гҒ‘гӮ’еҖҹгӮҠгҒӘгҒ„гҒ§гӮӮгҖҒз№°гӮҠиҝ”гҒ—и»ўгҒ¶зөҢйЁ“гӮ’йҮҚгҒӯгҒҰгҖҒд№—гӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮӢдәәгӮӮеұ…гӮӢгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгӮӮгҒ—гҖҒи»ўгҒіз¶ҡгҒ‘гӮӢгҒ“гҒЁгҒ«е«Ңж°—гҒҢгҒ•гҒ—гҖҢиҮӘеҲҶгҒ«гҒҜиҮӘи»ўи»ҠгҒ«д№—гӮӢжүҚиғҪгҒҢгҒӘгҒ„гҒ®гҒӢгӮӮвҖҰгҖҚгҒЁи«ҰгӮҒгҒҰгҒ—гҒҫгҒ„гҖҒгҒқгҒ®гҒҫгҒҫдёҖз”ҹиҮӘи»ўи»ҠгҒ«д№—гӮүгҒӘгҒ„пјҲд№—гӮҢгҒӘгҒ„пјүдәәгҒҢеұ…гӮӢгҒӘгӮүгҖҒгҒқгӮҢгҒҜдёҚе№ёгҒӘгҒ“гҒЁгҒ§гҒҷгҖӮ
иЈңеҠ©ијӘд»ҳгҒҚгҒ§гҒӮгӮҚгҒҶгҒЁе®ҹйҡӣгҒ«иҮӘи»ўи»ҠгӮ’йҒӢи»ўгҒ—гҒҰгҒҝгҖҒгҖҢиҮӘи»ўи»ҠгҒ«д№—гӮӢгҖҚгҒЁдә‘гҒҶиЎҢзӮәгҒ®е…·дҪ“зҡ„гҒӘйҒӢеӢ•гӮӨгғЎгғјгӮёгӮ’и„іиЈҸгҒ«зўәз«ӢгҒ•гҒӣгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҖҒж–°гҒҹгҒӘжҠҖиЎ“гҒ®зҝ’еҫ—гҒ®йҡӣгҒ«гҒҜжңүеҠ№гҒ§гҒӮгӮӢгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
гҒҹгҒ гҖҒж—ўгҒ«гӮігғӯз„ЎгҒ—гҒ§д№—гӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ«гӮӮй–ўгӮҸгӮүгҒҡгҖҒгҒқгӮҢгҒ«ж°—гҒҘгҒӢгҒҡгҖҒгҒ„гҒӨгҒҫгҒ§гӮӮгӮігғӯгҒӨгҒҚгҒ§д№—гӮҠгҒҫгӮҸгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢдәәгҖҒгҒӮгӮӢгҒ„гҒҜгҖҢиҮӘи»ўи»ҠгҒЁгҒҜгҖҒжң¬жқҘгӮігғӯгҒӨгҒҚгҒ§д№—гӮӢгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖҚгҒЁгҒ®дҝЎеҝөпјҲж•ҷзҫ©пјүгӮ’зҜүгҒ„гҒҰгҒ—гҒҫгҒЈгҒҰгӮӢдәәгҒҢгҒ„гӮӢгҒЁгҒ—гҒҹгӮүгҖҒгҒқгӮҢгҒҜж»‘зЁҪгҒӘгҒ гҒ‘гҒ§гҖӮ
гҒқгӮҢгҒЁеҗҢж§ҳгҒӘи©ұгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢгҒЁиҖғгҒҲгҒҫгҒҷгҖӮ
пјҠ гҖҢгғӘгғҸгғ“гғӘеүҚжңҹгҒ®иЈ…зқҖе…·гҖҚгҒЁдә‘гҒҶе–©гҒҲгҒ§гӮӮгҒЈгҒҰгҖҒеҗҢгҒҳиӘ¬жҳҺгӮ’гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮеҸҜиғҪгҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
иҰіеҜҹгғ»зҗҶи§Јгғ»еӨүе®№
е®ҹи·өгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒиҰіеҜҹпјҲж°—гҒҘгҒҚпјүвҶ’ зҗҶи§ЈпјҲжҙһеҜҹпјүвҶ’ еӨүе®№пјҲе•ҸйЎҢгҒӢгӮүгҒ®й–Ӣж”ҫпјүгҒЁгҒ„гҒҶгғ—гғӯгӮ»гӮ№гҒҢгҖҒгҒқгӮҢгҒһгӮҢгҒ®еұҖйқўгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰпјҲж·ұгҒҫгӮҠгҒӨгҒӨпјүеҸҚеҫ©зҡ„гҒ«з№°гӮҠиҝ”гҒ•гӮҢгӮӢгҖӮ
иһәж—ӢйҡҺж®өгӮ’жҳҮгҒЈгҒҰгҒ„гҒҸпјҲгҒӮгӮӢгҒ„гҒҜйҷҚгӮҠгҒҰгӮҶгҒҸпјүгҒӢгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гҖӮ вҶ’ жјёйҖІзҡ„гӮўгғ—гғӯгғјгғҒ
гҒқгӮҢгҒҜгҖҒиҮӘиә«гҒ®еҝғзҗҶзҡ„/иӮүдҪ“зҡ„е•ҸйЎҢгҒёгҒ®ж°—гҒҘгҒҚпјҲиҰіеҜҹпјүвҶ’ жҙһеҜҹпјҲзҗҶи§ЈпјүвҶ’ еӨүе®№пјҲе•ҸйЎҢгҒ®иҮӘе·ұеӨүе®№гғ» иҮӘе·ұеӨүиІҢгғ» иҮӘе·ұж¶Ҳж•Јгғ» иҮӘе·ұж¶ҲеӨұгҖҒе•ҸйЎҢгҒҢе•ҸйЎҢгҒ§гҒӘгҒҸгҒӘгӮӢгҒ“гҒЁгҖҒе•ҸйЎҢгҒ§гҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгҒ«ж°—гҒҘгҒҸгҒ“гҒЁпјүгҒЁдә‘гҒҶгғ—гғӯгӮ»гӮ№вҖ• ж°—гҒҘгҒҚпјҲиҰіеҜҹпјүгҒӢгӮүжҙһеҜҹпјҲиӘҚиӯҳгҒ®и»ўжҸӣ)гҒёгҒЁиҮігӮӢгғ—гғӯгӮ»гӮ№гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒҫгҒҹгҖҒгҒ“гӮҢгҒҜгҖҒпјҲдёүгҒӨгҒ«еҲҶгҒ‘гӮӢгҒ“гҒЁгӮӮгҒ§гҒҚгӮӢгҒҢпјүе®ҹйҡӣгҒ«гҒҜгҖҒдёҖгҒӨгҒ®гӮӮгҒ®гғ»гҒ“гҒЁгҒ§гӮӮгҒӮгӮӢвҖ• йҖЈз¶ҡгҒҷгӮӢдёҖйҖЈгҒ®гғ—гғӯгӮ»гӮ№гӮ’дёүжһҡгҒ®йқҷжӯўз”»еғҸгҒЁгҒ—гҒҰеҲҮгӮҠеҸ–гӮҠгҖҒдёҰгҒ№гҒҹгӮӮгҒ®гҖӮ
иҰіеҜҹгҒҜгҖҒгҖҢгҒқгҒ®гғўгғҺпјҲеҜҫиұЎпјүгӮ’гҖҒгҒ“гӮҢгҒҫгҒ§гҒЁйҒ•гҒҶд»•ж–№гҒ§иҰігӮӢгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶж„Ҹе‘ігҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒзҗҶи§ЈпјҲжҙһеҜҹпјүпјқпјҲзү©дәӢгҒҢйҒ•гҒҶеҪўгҒ§з«ӢгҒЎзҸҫгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгғ»иӘҚиӯҳгҒ®и»ўжҸӣпјүгӮ’ж—ўгҒ«еӯ•гӮ“гҒ§гҒ„гӮӢгҖӮ
зҗҶи§ЈпјҲжҙһеҜҹпјүпјқгҒӮгӮӢзү©дәӢгҒҢгҖҒгҒқгӮҢгҒҫгҒ§гҒЁйҒ•гҒҶгғўгғҺгҒЁгҒ—гҒҰиӘҚиӯҳгҒ•гӮҢгӮӢгҒ“гҒЁпјқеҚігҖҒеӨүе®№гҒ§гӮӮгҒӮгӮӢгҖӮ
гӮҲгҒЈгҒҰгҖҒгҖҢиҰіеҜҹгҖҚеҚігҖҢзҗҶи§ЈпјҲжҙһеҜҹгҒ®жҲҗз«ӢпјүгҖҚгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҒқгӮҢгҒҜгҖҒгҒқгҒ®гҒҫгҒҫгҖҢеӨүе®№гҖҚгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
гҒ“гҒ®гҖҢиҰіеҜҹгғ»зҗҶи§Јгғ»еӨүе®№гҖҚгҒ®гғ—гғӯгӮ»гӮ№е…ЁдҪ“гӮ’гҖҢж°—гҒҘгҒҚгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶдёҖиЁҖгҒ§иЎЁгҒҷгҒ“гҒЁгӮӮгҒ§гҒҚгӮӢгҖӮ
гҒ“гҒ®гҖҢж°—гҒҘгҒҚгҖҚгҒЁдә‘гҒҶиЁҖи‘үгҒҜгҖҒи©ұиҖ…гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰпјҲгҒӮгӮӢгҒ„гҒҜи©ұгҒ®ж–Үи„ҲгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰпјүгҖҒ
1.В иҰіеҜҹпјқж°—гҒҘгҒҚгҖҒгҒЁдә‘гҒҶж„Ҹе‘ігҒ§дҪҝгӮҸгӮҢгӮӢе ҙеҗҲгҖҒ
2.В иҰіеҜҹвҶ’зҗҶи§ЈпјҲжҙһеҜҹпјүпјқж°—гҒҘгҒҚгҖҒгҒЁдә‘гҒҶж„Ҹе‘ігҒ§дҪҝгӮҸгӮҢгӮӢе ҙеҗҲгҖҒ
3.В иҰіеҜҹвҶ’зҗҶи§ЈпјҲжҙһеҜҹпјүвҶ’еӨүе®№пјқж°—гҒҘгҒҚгҖҒгҒЁдә‘гҒҶж„Ҹе‘ігҒ§дҪҝгӮҸгӮҢгӮӢе ҙеҗҲгҖҒ
гҒЁиүІгҖ…гҒӘеҗ«гҒҝгӮ’жҢҒгҒЈгҒҰдҪҝгӮҸгӮҢгӮӢгҖӮ
жӣҙгҒ«гҖҒгҖҢж°—гҒҘгҒҚпјқиҰіз…§иҖ…ж„Ҹиӯҳпјқзҙ”зІӢж„ҸиӯҳпјқгғҸгӮӨгӮўгғјгӮ»гғ«гғ•пјҲгҒЁиЁҖгӮҸгӮҢгӮӢгӮӮгҒ®пјүпјқж„ҸиӯҳгҖҚгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҒҷгҒ№гҒҰгҒҜгҖҢж°—гҒҘгҒҚгҖҚгҒ§гҒӮгӮҠгҖҢж„ҸиӯҳгҒқгҒ®гӮӮгҒ®гҖҚгҒ§гҒӮгӮҠгҖҢгҒ•гҒЁгӮҠгҖҚгҒ§гҒӮгӮӢгҖҒгҒЁдә‘гҒҶгӮҲгҒҶгҒӘдҪҝгҒ„ж–№гӮ’гҒ•гӮҢгӮӢе ҙеҗҲгӮӮгҒӮгӮӢгҖӮ
гҒҫгҒҹгҖҒгҒ“гҒ®гҖҢж°—гҒҘгҒҚпјқжҙһеҜҹгғўгғјгғүгҒ§еғҚгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢи„ігҒ®зҠ¶ж…ӢгҖҚгӮ’гҖҒгҖҢж—ҘеёёгғўгғјгғүгҒ§еғҚгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢи„іпјқиҮӘжҲ‘пјқз§ҒгҖҚгҒҢгҖҒиҮӘеҲҶгҒЁгҒҜеҲҘгҒ®дёҖгҒӨгҒ®дәәж јдҪ“гҒЁгҒ—гҒҰпјҲеӨ–еңЁзҡ„гҒ«пјүиӘҚиӯҳгҒ—гҒҹгҒЁгҒҚгҖҒгғҸгӮӨгӮўгғјгӮ»гғ«гғ•гҖҒгғҒгғЈгғҚгғӘгғігӮ°гҒ®е®Үе®ҷдәәгҖҒеҶ…гҒӘгӮӢгӮ°гғ«пјҲеҶ…гҒӘгӮӢеё«пјүгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒгҖҢд»–иҖ…гҖҚзҡ„гҖҒгҖҢи¶…и¶Ҡзҡ„еӯҳеңЁгҖҚзҡ„гҒ«зөҢйЁ“гҒ•гӮҢгӮӢгҖӮ
гӮҰгӮөгӮ®гҒЁгӮўгғ’гғ«вҖ• иӘҚиӯҳгҒ®и»ўжҸӣ
гҒ“гҒ®гҖҢгӮҰгӮөгӮ®/гӮўгғ’гғ«еӣіеҪўгҖҚгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒдәҢгҒӨгҒ®гҖҢиҰӢгҒҲгҖҚгҒ®еҸҚи»ўгҒҜгҖҒдёҖзһ¬гҒ§иө·гҒ“гӮӢгҒЁгӮӮиЁҖгҒҲгӮӢгҒ—гҖҒж•°з§’гҒ®пјҲиҰӢгҒӨгӮҒгҒҰгҒ„гӮӢпјүжҷӮй–“гӮ’иҰҒгҒҷгӮӢгҒЁгӮӮиЁҖгҒҲгӮӢгҖӮ
дәҢгҒӨгҒ®иҰӢгҒҲгҒҢеҗҢжҷӮгҒ«жҲҗз«ӢгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜжұәгҒ—гҒҰгҒӘгҒҸгҖҒеҝ…гҒҡпјҲж•°з§’гҒ”гҒЁгҒ«пјүеҸҚи»ўгҒҷгӮӢгҖӮ
ж„ҸиӯҳгҒ®еҠӣгҒ§гҖҒгҒқгӮҢгӮ’жӯўгӮҒгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜдёҚеҸҜиғҪгҒ§гҒӮгӮӢгҒ—гҖҒгҒҫгҒҹгҖҒгҒқгӮҢгӮ’гҖҢгӮҰгӮөгӮ®гҒ§гӮӮгӮўгғ’гғ«гҒ§гӮӮгҒӘгҒ„гҖҚж„Ҹе‘ідёҚжҳҺгҒ®иҰ–иҰҡжғ…е ұгҒЁгҒ—гҒҰиҰӢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜйқһеёёгҒ«йӣЈгҒ—гҒ„гҖӮ
зһ‘жғігҒ®е®ҹи·өжҠҖжі•
гҒ“гӮҢгҒӢгӮүиӘ¬жҳҺгҒҷгӮӢж°—гҒҘгҒҚгҒ®иЁ“з·ҙгҒ®дҪ“зі»гҒҜгҖҒйқһеёёгҒ«зІҫеҜҶгҒӘгӮӮгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
гҒқгҒ“гҒ«гҒҜ無駄гҒӘпјҲз©әи«–зҡ„гғ»иҰіеҝөзҡ„гҒӘпјүиҰҒзҙ гҒҢе°‘гҒӘгҒ„еҲҶгҖҒеҺіеҜҶгҒ«жӯЈзўәгҒ«йҒ©з”ЁпјҲе®ҹи·өпјүгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢе•ҸйЎҢгҒЁгҒӘгӮҠгҖҒе°‘гҒ—гҒ§гӮӮжҠҖжі•гҒ®зҗҶи§ЈгҒ«гӮәгғ¬гҒҢгҒӮгӮҠгҖҒйҒ•гҒҶгҒ“гҒЁгӮ’гӮ„гҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҒЁгҖҒдҪ“йЁ“гҒ®ж–№еҗ‘гҒ«гӮәгғ¬гҒҢз”ҹгҒҳгҒҰгҒ—гҒҫгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
жӯЈгҒ—гҒ„ж–№еҗ‘гҒЁгҒҜгҖҒиҮӘе·ұзҗҶи§Јгғ»иҮӘе·ұиӘҚиӯҳгҒҢж·ұгҒҫгӮӢж–№еҗ‘жҖ§гҒӘгҒ®гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгӮ„гӮ„гӮӮгҒҷгӮҢгҒ°гҖҒгҒқгҒҶгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒйҷ¶й…”гҒЁгӮӮиЁҖгҒҲгӮӢзү№ж®ҠгҒӘж„ҸиӯҳзҠ¶ж…Ӣгғ»зһ‘жғізөҢйЁ“гҖҒж°—жҢҒгҒЎгӮҲгҒ•гӮ’еҸҚеҫ©гҒ—гҒҰе‘ігӮҸгҒҶгҒ“гҒЁгҒҢзӣ®зҡ„еҢ–гҒ—гҒҰгҒ„гҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҒ“гҒЁгҒҢеӨҡгҒҸгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
вҶ’ гҖҢдҝ®иЎҢгҒ®еӢ•ж©ҹгҒЁгҖҒгҒқгҒ®зҙ”еҢ–гҖҚ
гҒҜгҒҳгӮҒгҒҜгҖҒгӮ„гҒҜгӮҠдёҖйҖұй–“д»ҘдёҠгҒ®жҷӮй–“гӮ’гҒӢгҒ‘гҒҰгҒ®гҖҒгҖҢгӮ„гӮҠж–№гҒ®иӘ¬жҳҺгӮ’иҒһгҒҸвҶ’ йӣҶдёӯзҡ„гҒ«гӮ„гҒЈгҒҰгҒҝгӮӢвҶ’ пјҲйқўжҺҘгҒ«гҒҰпјүгғ¬гғқгғјгғҲгҒЁз–‘е•ҸзӮ№гӮ’еҮәгҒҷвҶ’ жҠҖжі•гҒ®еҫ®иӘҝж•ҙпјҲй–“йҒ•гҒЈгҒҰгҒ„гӮӢзӮ№гҒ®дҝ®жӯЈпјүвҶ’ пјҲеҶҚгҒіпјүе®ҹи·өвҶ’ гғ¬гғқгғјгғҲвҶ’ еҫ®иӘҝж•ҙвҖҰгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶз№°гӮҠиҝ”гҒ—гҒҢеҝ…иҰҒгҒЁгҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
дё–гҒ®дёӯгҒ«гҒҜеӨҡгҒҸгҒ®зһ‘жғігҒ®жөҒжҙҫпјҲдјқзөұпјүгҒЁжҠҖжі•пјҲгғҶгӮҜгғӢгғғгӮҜпјүгҒҢеӯҳеңЁгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒ“гӮҢгҒӢгӮүиӘ¬жҳҺгҒ—гҒҰгҒ„гҒҸзҗҶи«–/жҠҖжі•гҒЁгҒҜгҖҒзҰ…пјҲеӨ§д№—д»Ҹж•ҷпјүгҒЁгғҙгӮЈгғ‘гғғгӮөгғҠгғјпјҲдёҠеә§д»Ҹж•ҷпјүгӮ’зҙ жқҗгҒ«иҰҒзҙ жҠҪеҮәгӮ’еҠ гҒҲгҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
зҰ…гӮ„гғҙгӮЈгғ‘гғғгӮөгғҠгғјгҒ®гҒӘгҒӢгҒ«гҒҷгӮүгҖҒж•°еӨҡгҒҸгҒ®жөҒжҙҫгҒҢгҒӮгӮҠжҠҖжі•гҒҢгҒӮгӮҠгҖҒгҒқгӮҢгҒһгӮҢгҒҢгҖҒй•·жүҖ/зҹӯжүҖпјҲе„ӘгӮҢгҒҹйғЁеҲҶгҒЁгҖҒгҒ„гҒҫдёҖгҒӨгҒӘйғЁеҲҶпјүгӮ’жҢҒгҒЈгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒқгӮҢгӮүгӮ’иҖғгҒҲгҒҹгҒҶгҒҲгҒ§гҖҒгҒ“гҒЎгӮүгҒ®зһ‘жғігӮігғјгӮ№гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒжҠҖжі•гҒ®гғҷгғјгӮ№пјҲйӘЁзө„гҒҝпјүгӮ’гҖҢгғһгғҸгғјгӮ·гғЎгӮҪгғғгғүгҖҚгҒ«гҒҠгҒҚгҒҫгҒҷгҖӮ
гғһгғҸгғјгӮ·гғЎгӮҪгғғгғүгҒЁгҒҜгҖҒгҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘжҠҖжі•гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒӢпјҹ
гҒқгҒ“гҒ«гҒҜгҖҒгҖҢдёҖгҒӨгҒ®ж №жң¬еҺҹзҗҶгҖҚгҒЁгҖҢдәҢгҒӨгҒ®иЈңеҠ©зҡ„жҠҖжі•пјҲеҺҹеүҮпјүгҖҚгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гғһгғҸгғјгӮ·гғЎгӮҪгғғгғүгҒ®дёүжң¬жҹұ
1.гҖҖгҒӨгҒӯгҒ«пјҲгҒ„гҒӨгҒ§гӮӮгҖҒзңјгҒҢиҰҡгӮҒгҒҰгҒ„гӮӢгҖҒгҒ©гҒ®зһ¬й–“гӮӮпјүгҒҷгҒ№гҒҰгҒ«пјҲгҒӮгӮүгӮҶгӮӢзҸҫиұЎгҖҒгҒӮгӮүгӮҶгӮӢеҜҫиұЎгҒ«пјүж°—гҒҘгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҖҖгҖҗж №жң¬еҺҹзҗҶгҖ‘
2.гҖҖгғ©гғҷгғӘгғігӮ°гҒ®ж„ҸиӯҳгҒёгҒ®е®ҡзқҖпјҲж§ӢйҖ еҢ–пјүгҖҖгҖҗеҺҹеүҮпј‘гҖ‘
3.гҖҖдёӯеҝғеҜҫиұЎгҒ®иЁӯе®ҡгҒЁгҖҒе ҙйқўпјҲзҠ¶жіҒпјүгҒ«еҝңгҒҳгҒҹйҒ©з”ЁгҖҖгҖҗеҺҹеүҮпј’гҖ‘
гҒҫгҒҡгҖҒжңҖеҲқгҒ®гҖҢгҒӨгҒӯгҒ«гҖҒгҒҷгҒ№гҒҰгҒ«гҖҒж°—гҒҘгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁпјҲзө¶гҒҲй–“гҒӘгҒ„ж°—гҒҘгҒҚпјүгҖҚгҒЁдә‘гҒҶж №жң¬еҺҹзҗҶгҒӢгӮүиҰӢгҒҰгҒ„гҒҚгҒҫгҒ—гӮҮгҒҶгҖӮ
гҖҢгҒӨгҒӯгҒ«гҖҚгҒЁгҒҜпјҹ
гҒқгӮҢгҒҜгҖҒиө·гҒҚгҒҰгҒ„гӮӢй–“дёӯвҖ• жңқгҖҒзӣ®гӮ’иҰҡгҒҫгҒ—гҒҹзһ¬й–“гҒӢгӮүгҖҒеӨңгҖҒзң гӮҠгҒ«иҗҪгҒЎгӮӢгҖҒгҒқгҒ®зһ¬й–“гҒҫгҒ§вҖ• еҲҮгӮҢзӣ®гҒӘгҒҸгҖҒеқҮиіӘгҒ«гҖҒз„Ўе·®еҲҘгҒ«вҖ• гҒЁгҒ„гҒҶгҒ“гҒЁгӮ’ж„Ҹе‘ігҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
гҒқгҒ“гҒ«зһ‘жғігҒ®жҷӮй–“гҒЁгҖҒгҒқгҒҶгҒ§гҒӘгҒ„жҷӮй–“гҒЁгҒ®еҢәеҲҘгҒҜеӯҳеңЁгҒ—гҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гҖҢгҒҷгҒ№гҒҰгҒ«гҖҚгҒЁгҒҜпјҹ
дёүгҒӨгҒ®дё–з•ҢпјҲй ҳеҹҹпјүе…ЁдҪ“гҒ«гҖҒгғ гғ©гҒӘгҒҸгҖӮ
пј‘.гҖҖиә«дҪ“пјҲеҶ…йғЁпјүж„ҹиҰҡвҖ• пјҲдҪ“иЎЁйқўгҒ®жҺҘи§Ұж„ҹгҖҒең§иҝ«ж„ҹгҖҒжӢҚеӢ•/и„ҲеӢ•ж„ҹгҖҒж·ұйғЁгҒ®зӯӢж„ҹиҰҡгҖҒз—ӣгҒҝгҒӘгҒ©гҖҒдҪ“иЎЁйқўгҒ®ијӘйғӯгҒӢгӮүгҒӘгҒӢпјүгҒ®дё–з•ҢпјҲй ҳеҹҹпјү
пј’.гҖҖеӨ–з•ҢпјҲзҹҘиҰҡпјүвҖ• дё»гҒ«гҖҒиҰӢгӮӢгғ»иҒһгҒҸгҒ®дё–з•ҢпјҲй ҳеҹҹпјү
пј“.гҖҖж„ҸиӯҳпјҲеҝғпјүвҖ• жҖқиҖғпјҲеҶ…иӘһпјүгғ»гғЎгғігӮҝгғ«гӮӨгғЎгғјгӮёгғ»ж„ҹжғ…гғ»ж¬ІжұӮгҒ®дё–з•ҢпјҲй ҳеҹҹпјү
пјҠ е‘іпјҲе‘іиҰҡпјүгҖҒеҢӮгҒ„пјҲе—…иҰҡпјүгҒҜгҖҒ1гҒЁ2гҒ®дёӯй–“й ҳеҹҹпјҲдёӯгҒЁеӨ–гҒ®зӢӯй–“пјүгҒ«гҒӮгӮӢгҖӮ
з§ҒгҒҹгҒЎгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгҖҢз”ҹгҒҚгҒҰгӮӢпјҲзөҢйЁ“гҒ—гҒҰгӮӢпјүгҒ“гҒЁгҒ®дёӯиә«гғ»еҶ…е®№гҖҚгҒЁгҒҜдҪ•гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶпјҹ
з§ҒгҒҹгҒЎгҒҢгҖҒж—ҘгҖ…гҖҒзһ¬й–“зһ¬й–“гҖҒз”ҹгҒҚгҒҰж„ҹгҒҳгҒҰгҒ„гӮӢзҸҫе®ҹпјҲдё–з•ҢпјүгҒ®дёӯиә«гғ»е®ҹиіӘгҒЁгҒҜпјҹ
гҒқгӮҢгҒҜгҖҒиә«дҪ“ж„ҹиҰҡпјҲзҡ®иҶҡж„ҹиҰҡгғ»еҶ…йғЁж„ҹиҰҡгҖҒжҡ–гҒӢгҒ•гҖҒеҶ·гҒҹгҒ•пјүгҖҒеӨ–з•ҢзҹҘиҰҡпјҲиҰӢгҒҲгӮӢгӮӮгҒ®гҖҒиҒһгҒҲгӮӢйҹігҖҒе‘ігҖҒеҢӮгҒ„пјүгҖҒгҒқгҒ—гҒҰгҖҒж„ҸиӯҳгҒ®дё–з•ҢпјҲжҖқиҖғгҖҒж„ҹжғ…гҖҒгӮӨгғЎгғјгӮёгҖҒж¬ІжұӮпјүвҖ•
гҒқгҒ®дёүгҒӨгҒҢзҢӣзғҲгҒӘгӮ№гғ”гғјгғүгҒ§гҖҒз«ӢгҒЎзҸҫгӮҢгҖҒе…ҘгӮҠд№ұгӮҢгҖҒгҒқгӮҢгҒҢеҗҲжҲҗгҒ•гӮҢгҖҒгғ‘гғғгғҒгғҜгғјгӮҜгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹиӨҮеҗҲдҪ“вҖҰ гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҒӢгҖӮ
гҒҹгҒЁгҒҲгҒ°гҖҒиә«дҪ“ж„ҹиҰҡгҒ®гҒҶгҒЎгҖҢи§ҰиҰҡгҖҚгҒ«йҷҗгҒЈгҒҰгӮӮгҖҒ
гғ»ең§иҰҡ
гғ»жё©иҰҡ
гғ»еҶ·иҰҡ
гғ»з—ӣиҰҡ
гғ»жҢҜеӢ•ж„ҹиҰҡ
гҒӘгҒ©гҒҢгҒӮгӮҠгҖҒ
й–ўзҜҖгҒ®и§’еәҰгӮ„иә«дҪ“гҒ®дҪҚзҪ®гӮ’ж„ҹгҒҳеҸ–гӮӢгҖҢзӯӢж„ҹиҰҡгҖҚгҖҒеҶ…иҖігҒ«гӮҲгӮӢгҖҒеүҚеәӯпјҲе№іиЎЎж„ҹиҰҡпјүгӮӮгҒӮгӮӢгҖӮ
иҰ–иҰҡгҒҜ
гғ»йҒӢеӢ•иҰҡ
гғ»иүІиҰҡ
гғ»е…үиҰҡпјҲжҳҺеәҰгҒ®ж„ҹиҰҡпјү
гҒӘгҒ©гҒ®еҗҲжҲҗгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
ж¬ЎгҒ«гҖҒгғ©гғҷгғӘгғігӮ°гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖӮ
гғ»гҒ“гӮҢгҒҜгҖҒеҺҹзҗҶгҒ®гҖҢгҒӨгҒӯгҒ«гҖҚгӮ’е®ҹзҸҫгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®иЈңеҠ©зҡ„жҠҖжі•гҒЁгҒ—гҒҰгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гғ»дё»гҒ«гҖҒsatiгҒ®й–ӢзҷәгӮ’зӣ®жҢҮгҒ—гҒҰиЎҢгӮҸгӮҢгӮӢгҖӮ
жңҖеҫҢгҒ«гҖҒдёӯеҝғеҜҫиұЎгҒ®иЁӯе®ҡгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖӮ
гғ»иӢұиӘһгҒ®гҖҢгғЎгӮӨгғігғ»гӮӘгғ–гӮёгӮ§гӮҜгғҲгҖҚгҖҢгғ—гғ©гӮӨгғһгғӘгғјгғ»гӮӘгғ–гӮёгӮ§гӮҜгғҲгҖҚгҒ®иЁігҖӮ
гғ»гҒ“гҒЎгӮүгҒҜгҖҒеҺҹзҗҶгҒ®гҖҢгҒҷгҒ№гҒҰгҒ«гҖҚгӮ’е®ҹзҸҫгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®иЈңеҠ©зҡ„жҠҖжі•гҒЁгҒ—гҒҰеӯҳеңЁгҒҷгӮӢгҖӮ
гғ»дё»гҒ«гҖҒsamadhiгҒ®ж®өйҡҺзҡ„гҒӘй–Ӣзҷәгғ»еў—еј·гҒ®гҒҹгӮҒдҪңгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ
гғ»гғ©гғігӮҝгғігҒЁгғҳгғғгғүгғ©гғігғ—гҖҖж„ҸиӯҳгҒ®жҢҮеҗ‘жҖ§
гғ»дәҢж®өж§ӢгҒҲгҒ®з…§жҳҺпјҲдёӯеҝғиҰ–йҮҺгҒЁе‘ЁиҫәиҰ–йҮҺпјү
гғ»гғҶгғ¬гғ“еұҖгҒ®и„ҡд»ҳгҒҚгӮ«гғЎгғ©гҒ®гӮәгғјгғ пјҲе…ҘгӮҠгҒЁеј•гҒҚпјү
е®ҹи·өжҠҖжі•гғӘгӮ№гғҲ
з”ҹгҒҚгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁпјҲжҷ®ж®өгҒ®з”ҹжҙ»пјүгҒЁеҲҘгҒ®е ҙжүҖгҖҒеҲҘгҒ®жҷӮй–“гҒ«гҖҒгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒгҖҢз”ҹгҒҚгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒқгҒ®гӮӮгҒ®гҖҚгҒ®гҒӘгҒӢгҒ§зһ‘жғігӮ’дҪңгӮӢгҖӮж—ҘеёёгҒ®гҖҢз”ҹгҒҚгҒҰгӮӢгҒ“гҒЁгҒқгҒ®гӮӮгҒ®гҖҚгӮ’зһ‘жғігҒЁгҒҷгӮӢгҖӮ
гҒ„гӮҸгӮҶгӮӢгҖҢйқҷгҒӢгҒ«еә§гҒЈгҒҰгҒҠгҒ“гҒӘгҒҶзһ‘жғігҖҚгҒЁгҒҜз•°гҒӘгҒЈгҒҹзҷәжғігҒҢгғҷгғјгӮ№гҒ«гҒӮгӮӢгҖӮ
гҖҢдҪ•гҒҢзһ‘жғігҒӢпјҹгҖҚгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒгҖҢдҪ•гӮ’зһ‘жғігҒЁзӮәгҒҷгҒ®гҒӢпјҹгҖҚгҖҢз”ҹжҙ»гҒ®дёӯгҒ®гҖҒгҒ“гҒ®иЎҢзӮәгӮ’гҖҒгҒ©гҒҶгҒҷгӮҢгҒ°зһ‘жғіеҢ–гҒ§гҒҚгӮӢгҒӢпјҹгҖҚгҒЁдә‘гҒҶзҷәжғігҒ«еҹәгҒҘгҒ„гҒҹзһ‘жғіжі•гҖӮ
гғ—гғӯгӮ»гӮ№жҢҮеҗ‘гҒЁзӣ®зҡ„жҢҮеҗ‘
е…·дҪ“зҡ„жҠҖжі•гҒ®иӘ¬жҳҺгҒ«е…ҘгӮӢеүҚгҒ«гҖҒе…ЁдҪ“гҒ«й–ўгӮҸгӮӢйҮҚиҰҒгҒӘжіЁж„ҸзӮ№пјҲиҖғгҒҲж–№пјүгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖӮ
гӮҸгҒӢгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮӢгҖҢеӢ•дёӯе·ҘеӨ«гҖҚгҒЁгҒ„гҒҶиҖғгҒҲж–№гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖӮ
гғ»гғ•гғ©гӮӨгғігӮ°
гғ»гғЎгғігӮҝгғ«гғӘгғҸгғјгӮөгғ«
гғ»ж®өеҸ–гӮҠиғҪеҠӣ
гғ»гғһгғ«гғҒгӮҝгӮ№гӮҜгҒЁгӮ·гғігӮ°гғ«гӮҝгӮ№гӮҜ
гғ»иЎҢдҪҸеқҗиҮҘгҒ®еӣӣеЁҒе„ҖгҒҜгҖҒеӢ•гҒҸ/еӢ•гҒӢгҒӘгҒ„пјҲгӮӨгғігғҶгғігӮ·гғ§гғігғ»иә«дҪ“еҲ¶еҫЎгҒ®ж„ҸжҖқгҒ®жңүгӮӢгҒӘгҒ—пјүгҒ®дәҢгҒӨгҒ®е ҙйқўгҒ—гҒӢгҒӘгҒ„гҖҒгҒЁиҖғгҒҲгӮӢгҖӮ
гғ»иә«еҸ—еҝғжі•гҒ®еӣӣйҡҸеҝөвҶ’гҖҖиә«дҪ“гҒӢгӮүеҝғгҒёгҒ®дёүдё–з•Ңи«–гҒ§иӘ¬жҳҺгҒҷгӮӢгҖӮ
гҒӨгҒҺгҒ«гҒҫгҒҹгҖҒжҜ”дёҳгҒҹгҒЎгӮҲгҖҒ
жҜ”дёҳгҒҜгҖҒйҖІгӮҖгҒ«гӮӮйҖҖгҒҸгҒ«гӮӮгҖҒжӯЈзҹҘгӮ’гӮӮгҒЈгҒҰиЎҢеӢ•гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
зңҹгҒЈзӣҙгҒҗиҰӢгӮӢгҒ«гӮӮгҒӮгҒЎгҒ“гҒЎиҰӢгӮӢгҒ«гӮӮгҖҒжӯЈзҹҘгӮ’гӮӮгҒЈгҒҰиЎҢеӢ•гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
жӣІгҒ’гӮӢгҒ«гӮӮдјёгҒ°гҒҷгҒ«гӮӮгҖҒжӯЈзҹҘгӮ’гӮӮгҒЈгҒҰиЎҢеӢ•гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
еӨ§иЎЈгҒЁйүўиЎЈгӮ’жҢҒгҒӨгҒ«гӮӮгҖҒжӯЈзҹҘгӮ’гӮӮгҒЈгҒҰиЎҢеӢ•гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
йЈҹгҒ№гӮӢгҒ«гӮӮйЈІгӮҖгҒ«гӮӮеҷӣгӮҖгҒ«гӮӮе‘ігӮҸгҒҶгҒ«гӮӮгҖҒжӯЈзҹҘгӮ’гӮӮгҒЈгҒҰиЎҢеӢ•гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
еӨ§дҫҝе°ҸдҫҝгӮ’гҒҷгӮӢгҒ«гӮӮгҖҒжӯЈзҹҘгӮ’гӮӮгҒЈгҒҰиЎҢеӢ•гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮ
иЎҢгҒҸгҒ«гӮӮз«ӢгҒӨгҒ«гӮӮгҖҒеқҗгӮӢгҒ«гӮӮзң гӮӢгҒ«гӮӮзӣ®иҰҡгӮҒгӮӢгҒ«гӮӮгҖҒиӘһгӮӢгҒ«гӮӮй»ҷгҒҷгӮӢгҒ«гӮӮгҖҒжӯЈзҹҘгӮ’гӮӮгҒЈгҒҰиЎҢеӢ•гҒ—гҒҫгҒҷгҖӮд»ҘдёҠгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гҖҒиә«гҒ®еҶ…гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰиә«гӮ’иҰігҒӨгҒҘгҒ‘гҒҰдҪҸгҒҝгҖҒ
гҒӮгӮӢгҒ„гҒҜгҖҒеӨ–гҒ®иә«гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰиә«гӮ’иҰігҒӨгҒҘгҒ‘гҒҰдҪҸгҒҝгҖҒ
гҒӮгӮӢгҒ„гҒҜгҖҒеҶ…гҒЁеӨ–гҒ®иә«гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰиә«гӮ’иҰігҒӨгҒҘгҒ‘гҒҰдҪҸгҒҝгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒҫгҒҹгҖҒиә«гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰз”ҹиө·гҒ®жі•гӮ’иҰігҒӨгҒҘгҒ‘гҒҰдҪҸгҒҝгҖҒ
гҒӮгӮӢгҒ„гҒҜгҖҒиә«гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰж»…е°ҪгҒ®жі•гӮ’иҰігҒӨгҒҘгҒ‘гҒҰдҪҸгҒҝгҖҒ
гҒӮгӮӢгҒ„гҒҜгҖҒиә«гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰз”ҹиө·гҒЁж»…е°ҪгҒ®жі•гӮ’иҰігҒӨгҒҘгҒ‘гҒҰдҪҸгҒҝгҒҫгҒҷгҖӮгҒқгҒ—гҒҰгҖҒгҒӢгӮҢгҒ«гҖҢиә«гҒ®гҒҝгҒҢгҒӮгӮӢ гҖҚгҒЁгҒ®еҝөгҒҢзҸҫеүҚгҒ—гҒҫгҒҷгҒҢгҖҒгҒқгӮҢгҒ“гҒқгҒҜжҷәгҒ®гҒҹгӮҒеҝөгҒ®гҒҹгӮҒгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮ
гҒӢгӮҢгҒҜгҖҒдҫқеӯҳгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒӘгҒҸдҪҸгҒҝгҖҒдё–гҒ®гҒ„гҒӢгҒӘгӮӢгӮӮгҒ®гҒ«гӮӮеҹ·зқҖгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
гҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гҒҫгҒҹгҖҒжҜ”дёҳгҒҹгҒЎгӮҲгҖҒжҜ”дёҳгҒҜиә«гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰиә«гӮ’иҰігҒӨгҒҘгҒ‘гҒҰдҪҸгӮҖгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮй•·йғЁзөҢе…ё 第дәҢеҚҒдәҢзөҢгҖҢеӨ§еҝөеҮҰзөҢпјҲеҝғгҒ®е°ӮжіЁгҒ®зўәз«ӢпјүгҖҚ
жӢҚеӢ•пјҲи„ҲеӢ•пјүзһ‘жғігҖҖвҖ•еӢ•гҒӢгҒӘгҒ„зһ‘жғігҒ®еҹәжң¬еһӢгғј
еә§гӮӢгҖҒгҒӮгӮӢгҒ„гҒҜжЁӘгҒҹгӮҸгҒЈгҒҰгҖҒиә«дҪ“гӮ’еӣәе®ҡгғ»е®үе®ҡгҒ•гҒӣгҒҰ
пј‘гҖҖеҗҲжҺҢгҖҖиғёгҒ®еүҚгҒ§жүӢгӮ’еҗҲгӮҸгҒӣгҒҰпјҲжҢҮгҒ§и„ҲгӮ’еҸ–гӮҠгҒӘгҒҢгӮүгҖҒгӮ№гғҲгғјгғ–гҒ®жҡ–гҒӢгҒ•гҖҒгҒ—гҒігӮҢгӮ’дҪңгҒЈгҒҰпјү
пј’гҖҖжүӢгӮ’е°‘гҒ—й–ӢгҒ„гҒҰ
пј“гҖҖжүӢгӮ’иҶқгҒ«гҒҠгӮҚгҒ—гҒҰ
пј”гҖҖзүҮжүӢгҒҡгҒӨ
пј•гҖҖзүҮжүӢгӮ’гғ‘гғјгғ„гҒ«еҲҶгҒ‘гҒҰ
пј–гҖҖиә«дҪ“гҒ®д»–гҒ®е ҙжүҖгҒ§пјҲи¶ігҒ®иЈҸгҖҒи…°и…№йғЁгҒӘгҒ©пјү
гғ»гӮӘгғҺгғһгғҲгғҡгҒ®гғ©гғҷгғӘгғігӮ°еҢ–пјҲгӮёгғігӮёгғігҖҒгғүгӮҜгғүгӮҜгҒӘгҒ©пјү
е‘јеҗёзһ‘жғі
гғ» йј»пјҲж°—гҒҢдёҠгҒҢгӮҠгӮ„гҒҷгҒ„гҒ®жіЁж„ҸпјүгҖҖеҹәжң¬гҖҒгӮӘгӮ№гӮ№гғЎгҒҜгҒ—гҒӘгҒ„гҖӮ
гғ» и…°и…№йғЁпјҲиә«дҪ“гӮӨгғЎгғјгӮёгҒ®ж··е…ҘгҒ«ж°—гӮ’гҒӨгҒ‘гӮӢпјүгҖҖжЁӘиҮҘжҷӮгҒ«йҒ©гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢ
гғ» е…Ёиә«гҖҖпјҲеҒҸиә«гҖҒгҒӮгҒҫгҒӯгҒҸпјү
гғ» и¶іиЈҸгҖҖзңҹдәәгҒҜиёөгӮ’гӮӮгҒЈгҒҰе‘јеҗёгҒҷпјҲгӮӨгғЎгғјгӮёгӮ’дҪҝгҒЈгҒҰпјү
жӯ©иЎҢзһ‘жғігҖҖвҖ•еӢ•гҒҸзһ‘жғігҒ®еҹәжң¬еһӢгғј
жҺҘи§Ұж„ҹвҶ’ гҖҢи§ҰгӮҢгҒҹгҖҚ
еҶ…йғЁж„ҹиҰҡгғ»ең§иҝ«ж„ҹвҶ’ гҖҢж„ҹгҒҳгҒҹгҖҚгҒ®гғ©гғҷгғӘгғігӮ°
пј–гҒӨгҒ®гӮ№гғҶгғғгғ—пјҲгғңгғҮгӮЈгғҜгғјгӮҜзҡ„иЁ“з·ҙгҒёгҒЁз№ӢгҒ’гӮӢпјү
пј‘гҖҖи§ҰгӮҢгҒҹи¶іпјҲи»ёи¶іпјүгҒ§пј‘еҲҶеүІпјҲи§ҰгӮҢгҒҹпјүвҶ’ пј’еҲҶеүІгҖҖпјҲи§ҰгӮҢгҒҹгҖҒж„ҹгҒҳгҒҹпјү
пј’гҖҖгҒҷгӮҠи¶іпјҲгҒӢгҒӢгҒЁпјүпј’еҲҶеүІгҖҖпјҲи§ҰгӮҢгҒҹгҖҒж„ҹгҒҳгҒҹпјү
пј“гҖҖжө®гҒ„гҒҹпјҲеӢ•гҒҸеҒҙгҒ®з©әдёӯгҒ®и¶іпјүпј’еҲҶеүІпјҲи§ҰгӮҢгҒҹвҶ’ж„ҹгҒҳгҒҹпјү
пј”гҖҖеҗҲдҪ“пјҲе·ҰеҸідёЎи¶іеҗҢжҷӮпјү
пј•гҖҖе…Ёиә«пјҲиүІгҖ…гҒӘзө„гҒҝеҗҲгӮҸгҒӣпјүгғңгғҮгӮЈгғҜгғјгӮҜгӮ’зө„гҒҝгҒӮгӮҸгҒӣгҒҰпјҲгғүгғӯгғјгӮӨгғігҖҒй ӯйғЁгҒӘгҒ©пјү
пј–гҖҖиә«дҪ“еӨ–гҒёгҒ®ж°—гҒҘгҒҚпјҲиҰӢгҒҹгҖҒиҒһгҒ„гҒҹгҖҒжҖқиҖғгҖҒгӮӨгғЎгғјгӮёжңүгӮҠпјү
гғ»жӯ©иЎҢзһ‘жғігҒ®йҡӣгҒ®е§ҝеӢўгҒ®жіЁж„Ҹ
гғ»жӯ©иЎҢзһ‘жғігҒ®гҒҹгӮҒгҒ®жӯ©гҒҚж–№гҒ®иӘ¬жҳҺ
з—ӣгҒҝгҒ®иҰіеҜҹ
пј‘гҖҖз©әй–“зҡ„жҺӘе®ҡпјҲеўғз•Ңз·ҡгҖҒијӘйғӯпјү
пј’гҖҖжҷӮй–“и»ёгҒ§гҒ®иҝҪи·ЎпјҲз”ҹгғ»дҪҸгғ»ж»…пјү
пј“гҖҖжі•гҒЁжҰӮеҝөгҒ®иӯҳеҲҘгғ»еі»еҲҘ
йЈҹдәӢпјҲе–«иҢ¶пјүзһ‘жғі
гғ»гғӘгғҲгғӘгғјгғҲгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢе®ҹи·өдҝ®иЎҢгҒ®з·ҸеҗҲе•ҸйЎҢгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒйқһеёёгҒ«йҮҚиҰҒеәҰгҒҢй«ҳгҒ„гҖӮ
гғ»жҘөеҠӣгҖҒзӣ®гӮ’зһ‘гӮӢгҖӮ
гғ»гғҒгғЈгғігғҚгғ«гӮ’йҮҚгҒӯгҒӘгҒ„гҖӮгҖҢгҒӘгҒҢгӮүгҖҚгҒ«гҒӘгӮүгҒӘгҒ„гӮҲгҒҶж°—гӮ’гҒӨгҒ‘гӮӢгҖӮ
гғ»еӢ•дҪңгҒ®дёҖгҒӨдёҖгҒӨгҒ«гҖҒдёҖжҷӮеҒңжӯўпјҲгғқгғјгӮәпјүгӮ’е…ҘгӮҢгӮӢ
гғ»ж„ҹиҰҡгҒ®дҪҷйҹ»гӮ’иҒҙгҒҸпјҲйҗҳгҒ®йҹігҒ®е–©гҒҲпјү
гғ»еҮәгҒ гҒ—гҒ®зҙ°еҲҶеҢ–гҒ®гғ¬гғҷгғ«иЁӯе®ҡгҒҢгҒҷгҒ№гҒҰгӮ’жұәгӮҒгӮӢгҖӮ
ж—ҘеёёгҒ®еӢ•дҪңпјҲгғҲгӮӨгғ¬гҖҒгҒҠйўЁе‘ӮгҖҒжӯҜзЈЁгҒҚпјү
гғ»гҒҠйўЁе‘ӮгҒҢдёҖз•ӘйӣЈгҒ—гҒ„гҖӮ
гғ»жӯҜзЈЁгҒҚгҒ®гҒЁгҒҚгҖҒгҒӮгҒҲгҒҰеӨ§йӣ‘жҠҠгҒ«жҚүгҒҲгӮӢгҖӮ
гғ»з«ӢгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢи¶ігҒ®иЈҸгҒ®жҺҘи§Ұж„ҹгғ»ең§иҝ«ж„ҹгҒ§гҒЁгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгӮ„гӮҠж–№гӮӮгҒӮгӮӢгҖӮ
гғңгғҮгӮЈгғҜгғјгӮҜгҒЁгҒ®зө„гҒҝеҗҲгӮҸгҒӣпјҲиә«йҡҸиҰіеҢ–гҖҒзһ‘жғіеҢ–пјү
гғ»гғ•гӮ§гғ«гғҮгғігӮҜгғ©гӮӨгӮ№гғ»гғЎгӮҪгғғгғүгҖҒжјёйҖІзҡ„ејӣз·©жі•гҒЁгҒ®зө„гҒҝеҗҲгӮҸгҒӣ
гғ»жЁӘиҮҘгҒ®е§ҝеӢўпјҲд»°еҗ‘гҒ‘гғ»гҒҶгҒӨдјҸгҒӣгғ»иҶқгҒ гҒҰпјү
гғ»з«ӢдҪҚ
гғ»жӯ©иЎҢ
гғ»иҮӘйҮҚгғҲгғ¬гғјгғӢгғігӮ°гҒЁгҒ®зө„гҒҝеҗҲгӮҸгҒӣ
гғ»гғЁгғјгӮ¬гҖҒеӨӘжҘөжӢігҒ®еҘ—и·ҜгҒӘгҒ©гҒЁгҒ®зө„гҒҝеҗҲгӮҸгҒӣ
гғ»гӮҰгӮ©гғјгӮӯгғігӮ°гғ»гӮёгғ§гӮ®гғігӮ°гҒЁгҒ®зө„гҒҝеҗҲгӮҸгҒӣ
гғ»гӮҜгғӘгӮўгғӘгғігӮ°пјҲе‘јеҗёгҒ®ж“ҚдҪңгӮ’дҪҝгҒЈгҒҹжҠҖжі•пјү
гғҶгӮҝгғӢгғјпјҲйҒҺе‘јеҗёгҒ«гӮҲгӮӢз—әгӮҢпјүгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰ
гғӣгғӯгғҲгғӯгғ”гғғгӮҜгғ»гғ–гғ¬гӮ№гғҜгғјгӮҜгҒЁгҒ®жҜ”ијғ
еҝғгҒ®иҰіеҜҹпјҲеҝғйҡҸиҰіпјү
гғ»гҒҫгҒҡгҖҒгӮӨгғігғҶгғігӮ·гғ§гғігҒ®гғ©гғҷгғӘгғігӮ°пјҲиә«дҪ“гҒ«жҢҮд»ӨгӮ’еҮәгҒҷеҝғгҒ®еӢ•гҒҚпјүгҒӢгӮүгӮ№гӮҝгғјгғҲгҒҷгӮӢгҖӮгҖҖгҒқгҒ“гҒӢгӮүгҖҒгҖҢеҝғгҒ«жҢҮзӨәгӮ’еҮәгҒҷеҝғгҖҚгҒёгҒЁйҖІгӮҖгҖӮ
гғ»ж„ҹжғ…гҒҜгҖҒиә«дҪ“ж„ҹиҰҡгҒЁгҒ—гҒҰеҸ–гӮӢ
гғ» еҝ«гҒЁдёҚеҝ«гҖҒж¬ІжңӣгҒЁе«ҢжӮӘвҖ• гғ©гғҷгғӘгғігӮ°гҒ«гӮҲгӮӢд»•еҲҶгҒ‘гғ»ж„ҹгҒҳеҲҶгҒ‘гҖӮ
еҝ«пјҲиә«дҪ“зҡ„ж„ҹиҰҡпјүвҶ’ ж¬ІжңӣпјҲеҝғзҗҶзҡ„еҸҚеҝңпјү
дёҚеҝ«пјҲиә«дҪ“зҡ„ж„ҹиҰҡпјүвҶ’ е«ҢжӮӘпјҲеҝғзҗҶзҡ„еҸҚеҝңпјү
гғ»зҸҫеңЁйҖІиЎҢеһӢпјҲгғӘгӮўгғ«гӮҝгӮӨгғ пјүгҒ®еҶ…иҰівҖ• еҶ…иҰігҒЁгғҙгӮЈгғ‘гғғгӮөгғҠгғјпјҲеҝғйҡҸиҰіпјүгҒ®еҗҲжөҒгғ»еҗҲдҪ“