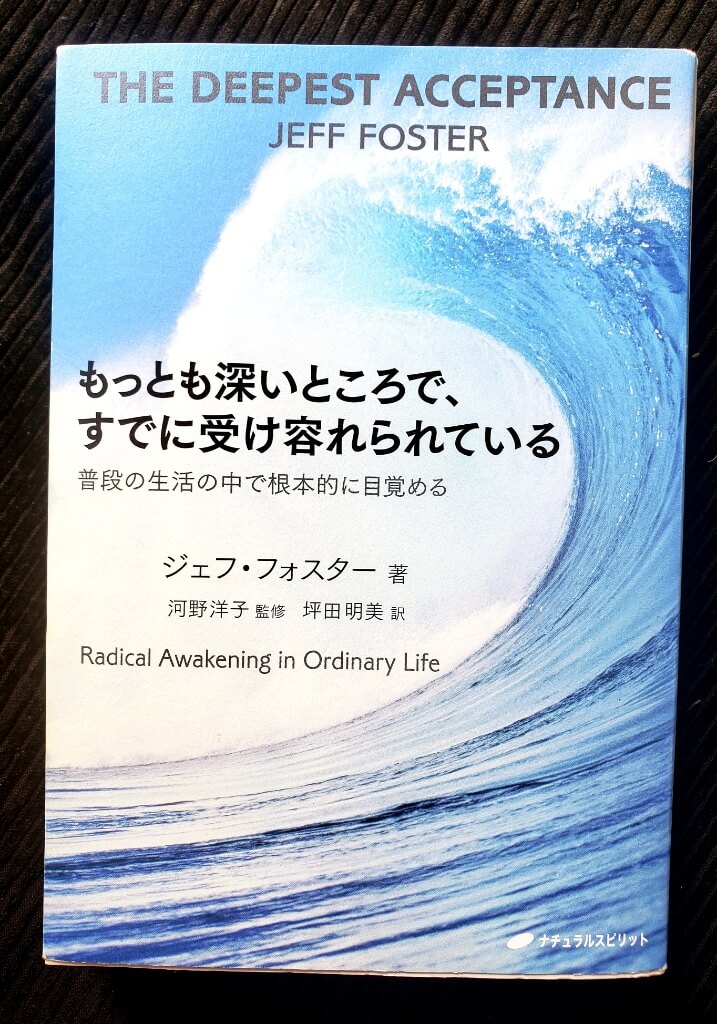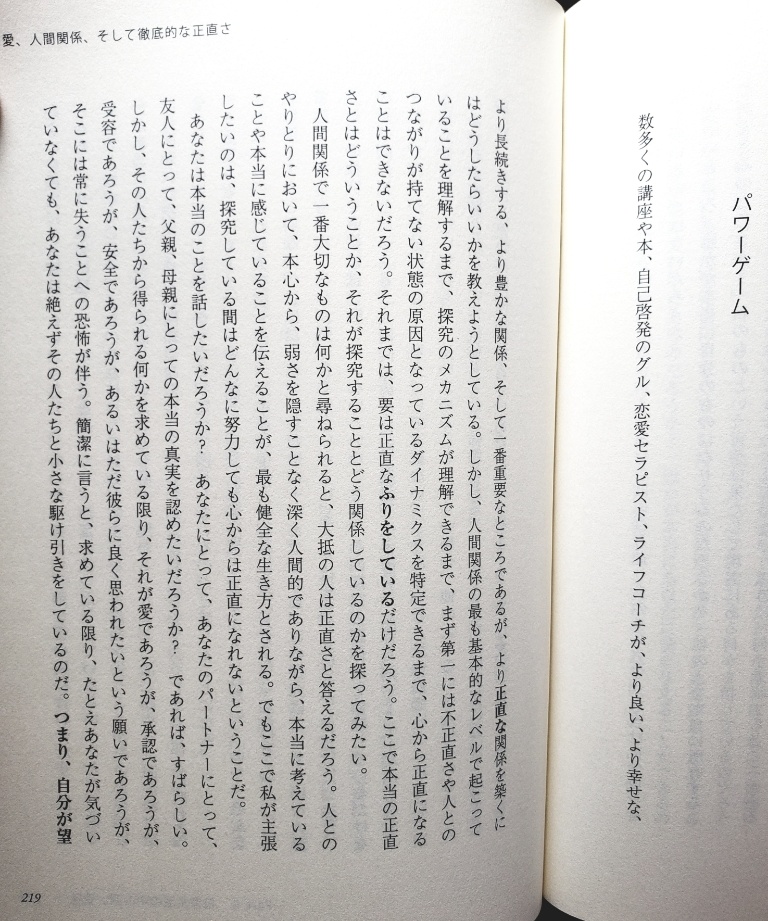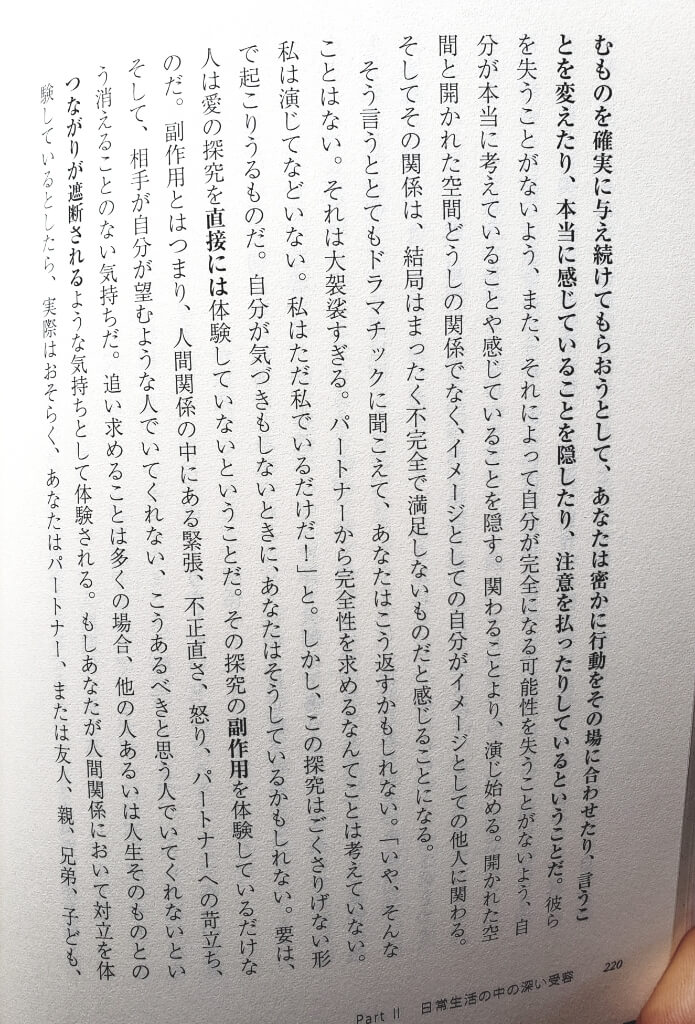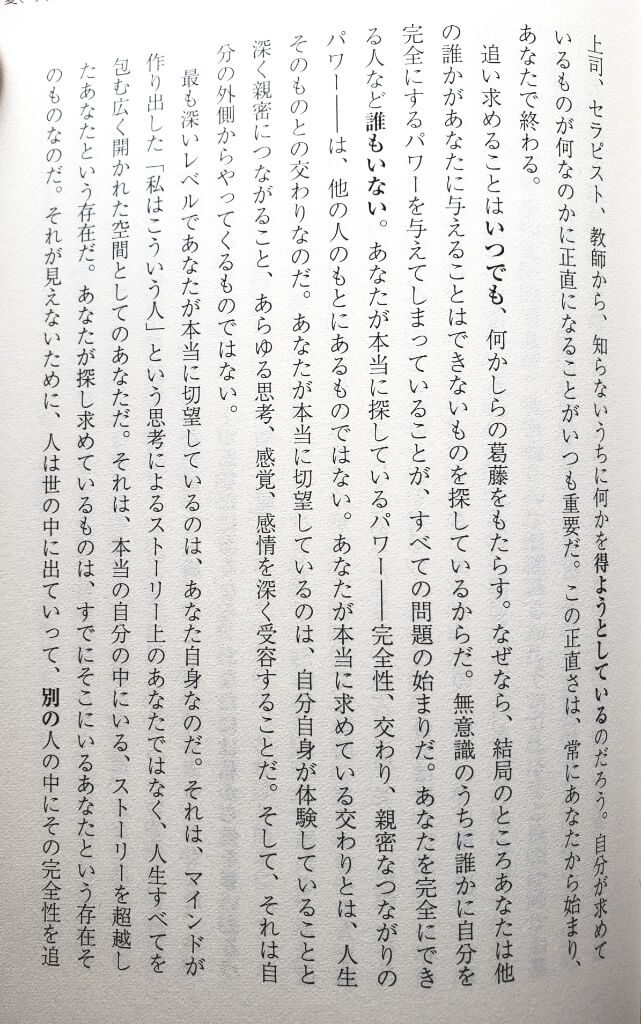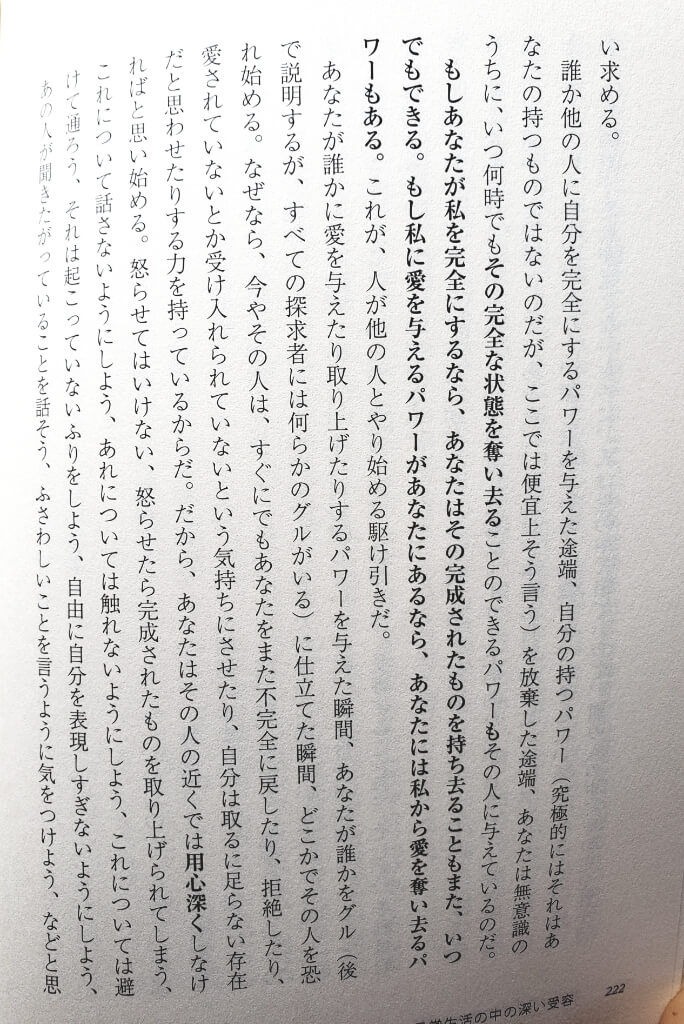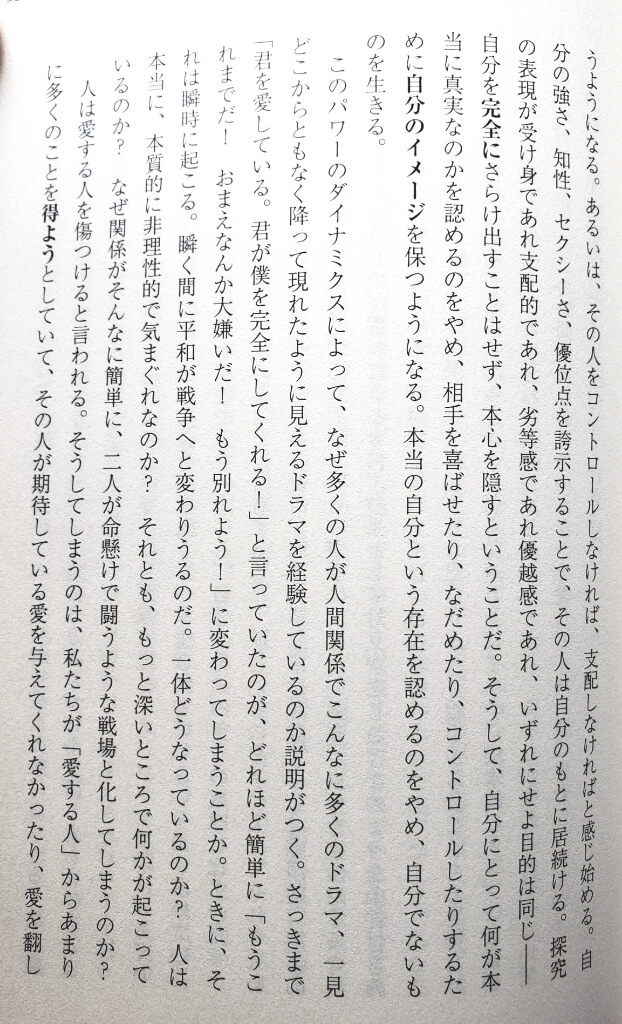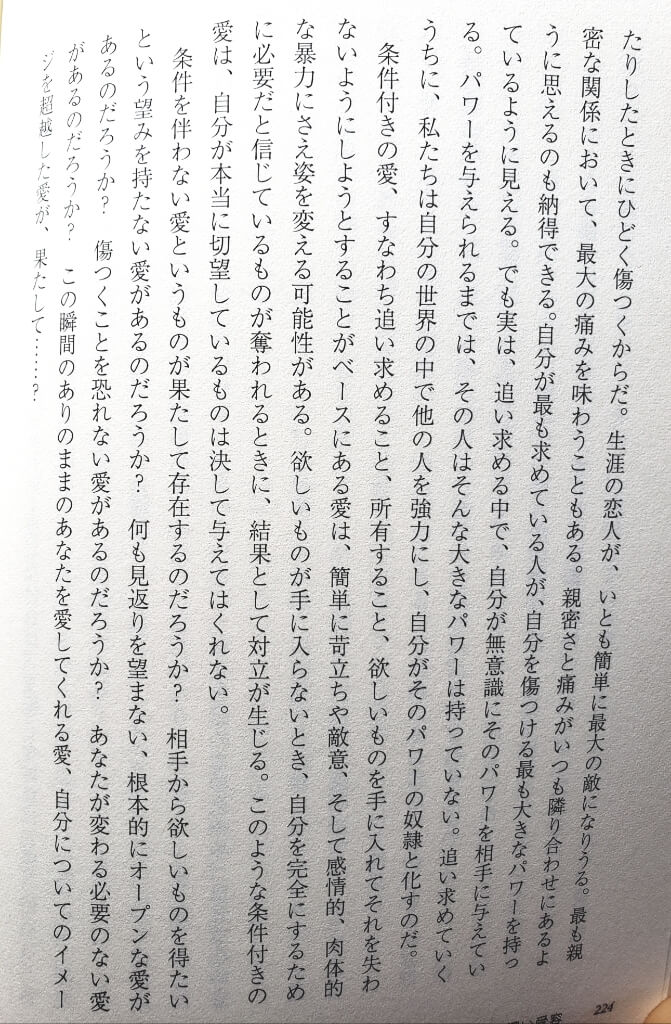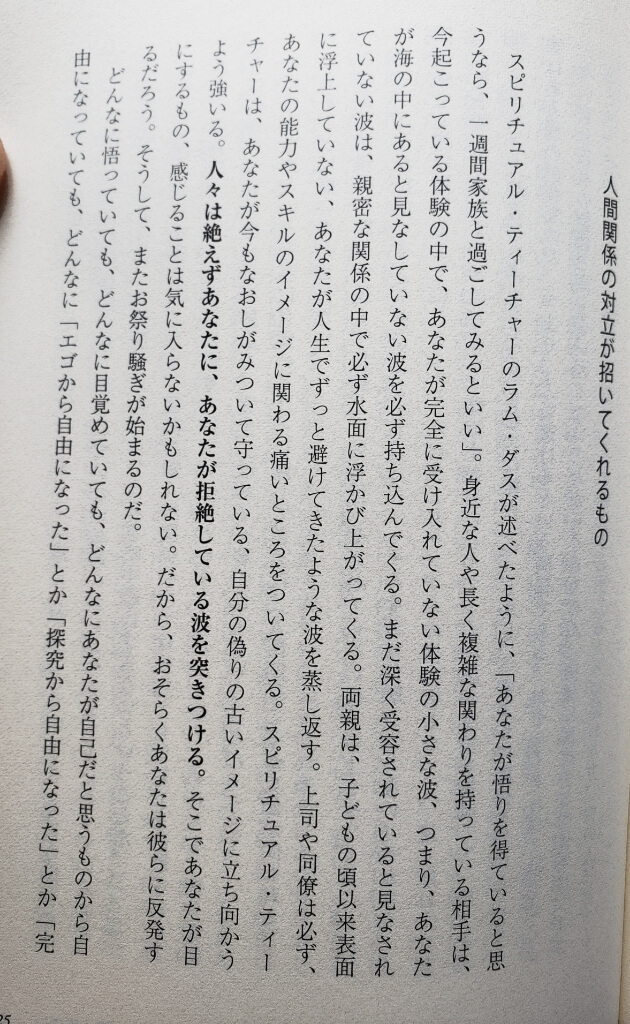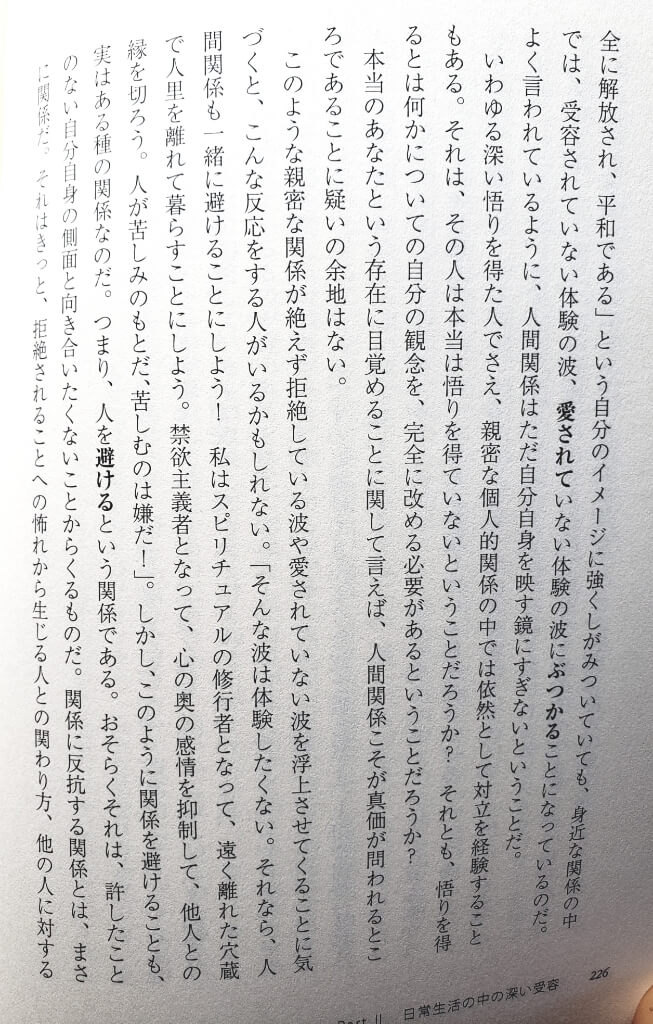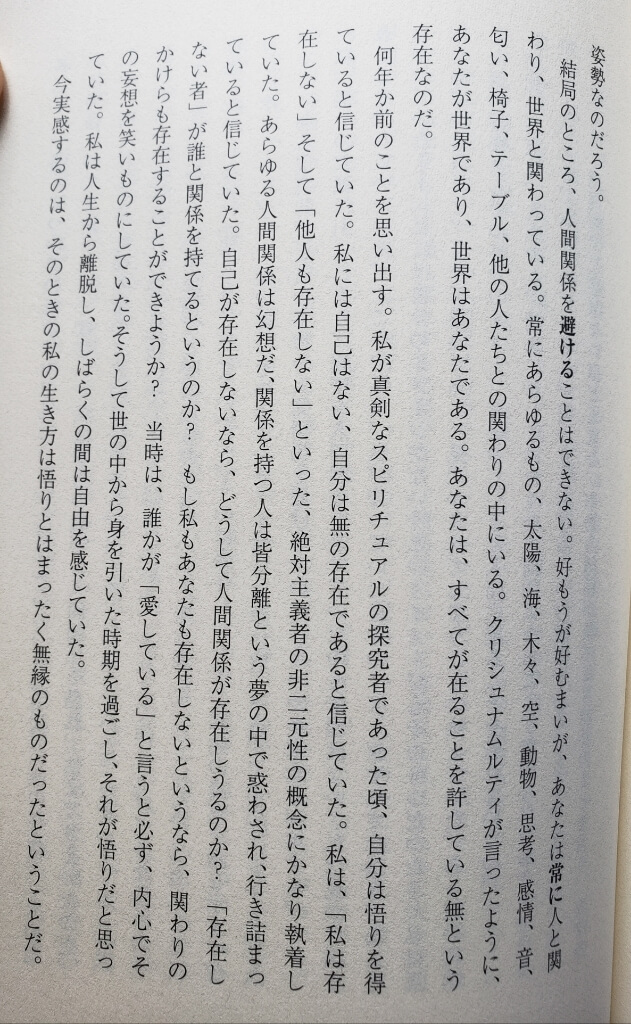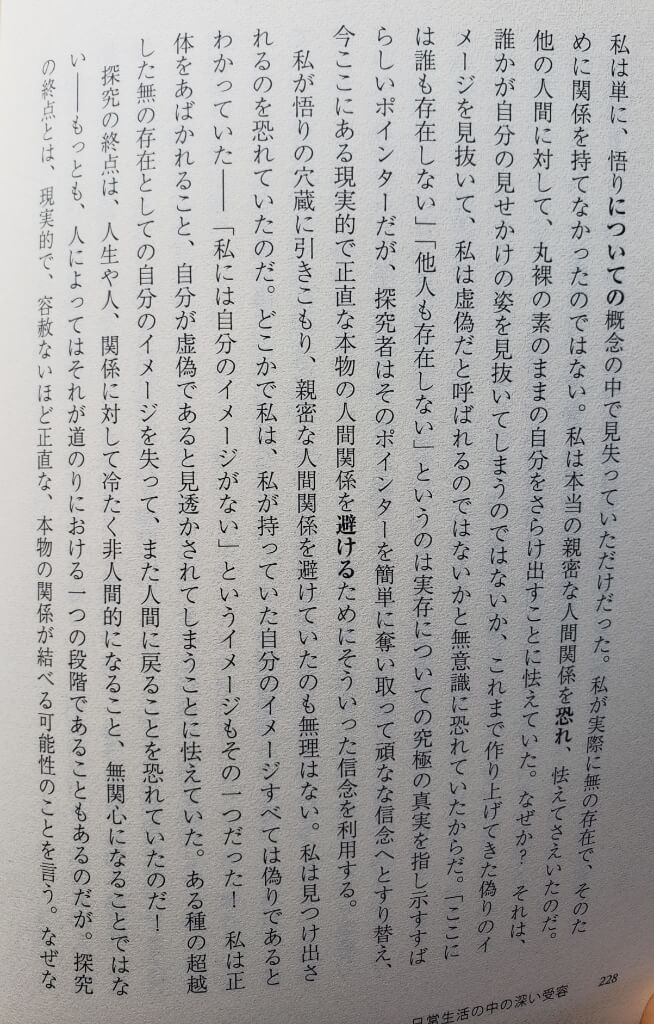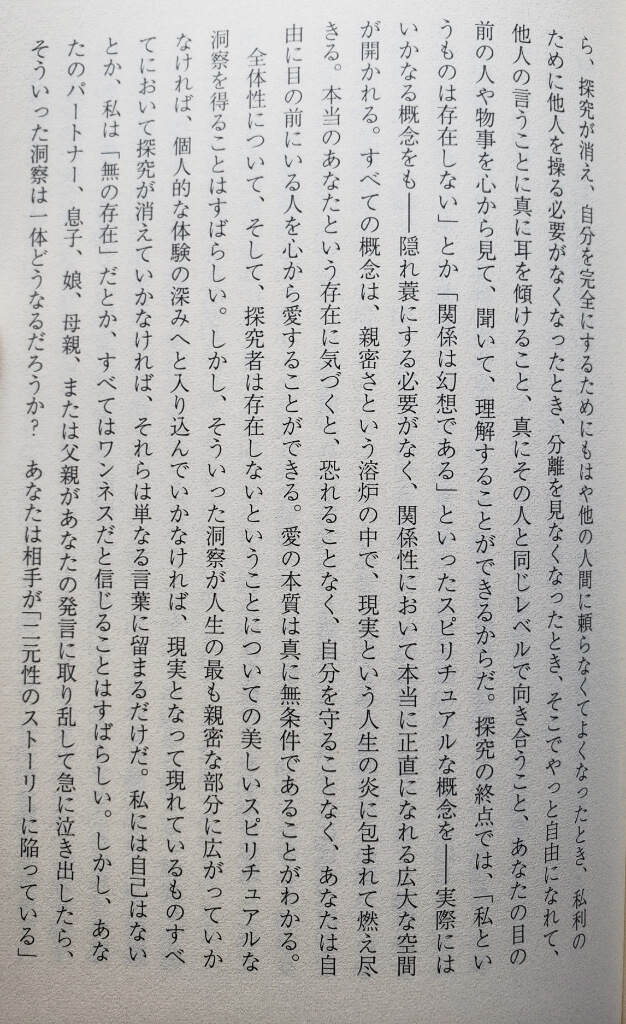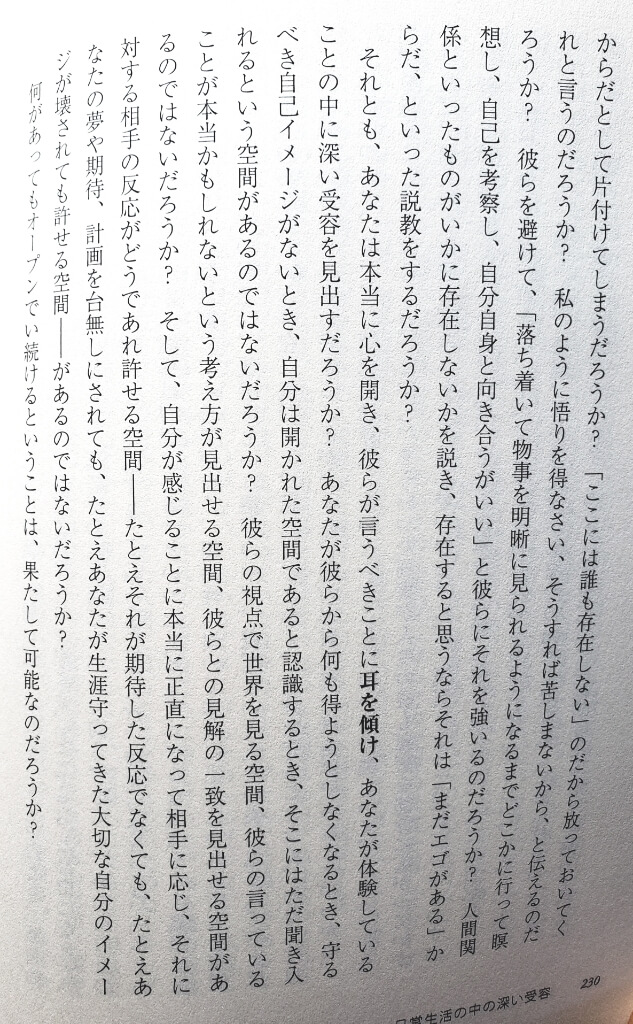カテゴリー: blog
沈黙の力量、黙っている力
バカ発見器に「発見されるバカ」にならないために
この記事を読み、このところ(特に、コロナ禍始まって以来)感じていたものが、とてもうまく言語化されているのに感心しました。
ÂøÉ„Å´ÊÄù„ÅÜ„ÇÇ„ÅÆ„Åå„ÅÇ„Çä„ŧ„ŧ„ÇÇȪô„Å£„Ŷ„ÅÑ„Çã„Åì„Å®„Å´„ÅØ„ÄÅ„Åù„Çå„Å™„Çä„ÅÆÂäõÈáè„Åå˶ńÇä‚Äï „Åù„Çå„ÅØÂãøË´ñ„ÄÅÁô∫Ë®ÄÔºàÁô∫‰ø°Ôºâ„Åô„Çã„Åπ„Åç„ÄÅ„Å®ÊÑü„Åò„Åü„Å®„Åç„ÄÅÊÑü„Åò„ÅüÂÜÖÂÆπ„Å´Èñ¢„Åó„ŶÁô∫‰ø°„Åô„Çã„Åì„Å®„ÇíÂê¶ÂÆö„Åô„Çã„ÇÇ„ÅÆ„Åß„ÅØ„Å™„ÅÑ„ÅÆ„Åß„Åô„Åå‚Äï Ëá™Ë∫´„ÅÆÂÜÖ„Å™„Çã„Éç„Ǩ„ÉÜ„Ç£„Éñ„Å™ÊÑüÊÉÖÔºà‰∏çÂÆâ„ɪÊÄí„Çä„ÄÅËãõÁ´ã„Å°„ɪËÖπÁ´ã„Å°„ÄÅ„Å™„Å©Ôºâ„Çí„ÄÅ„Åü„ÅÝ„Åü„ÅÝÂèçÂ∞ÑÁöÑ„Å´Âêê„ÅçÂá∫„Åó„ÄÅ„Å∂„ŧ„Åë„ÄÅÁ§æ‰ºö„Å´ÂèçÈüø„ɪ¢óÂπÖ„Åï„Åõ„Çã„Åì„Å®„ÅØÁôæÂÆ≥„ÅÇ„Å£„Ŷ‰∏ÄÂà©„Å™„Åó„ÄÅ„Å®ÊÑü„Åò„Åæ„Åô„ÄÇ
何であれ、それが社会的な表出(表現)であるのなら、幾らかの反省(推敲)があって然るべきで、もちろん、(瞬発反射芸など)いろんな芸風があっていいのですが、それが見れるレベル、何かを感じさせるレベルになっているかですね。
黙っているのって、バカにはできないし、
黙っているからって、何の意見も考えもないわけではないし、
„Åù„ÇåËᙉΩì„ÄÅÈ´òÂ∫¶„Å™ÈÅ∏Êäû„Åß„ÅÇ„ÇãÂÝ¥Âêà„ÇÇ„ÅÇ„Çã„ÅÆ„ÅÝ„Å®ÊÄù„ÅÑ„Åæ„Åô„ÄÇ
それがいつか表現されるときも。
9/15-24 内観コース
ÊòÝÁîª „ÄéÊó•Êú¨È¨ºÂ≠ê„Äè
https://www.dailymotion.com/video/x5v3287
https://www.dailymotion.com/video/x5vcmmr
https://www.dailymotion.com/video/x5vcmms
https://www.dailymotion.com/video/x5vcmmt
https://www.dailymotion.com/video/x5vcmmu
https://www.dailymotion.com/video/x5vcmmv
https://www.dailymotion.com/video/x5vcmmw